親の介護が必要になったとき、「介護保険を使えば費用が抑えられる」と聞いたことがある方も多いでしょう。しかし、実際に介護保険サービスを利用するには、事前に「介護保険申請」を行い、要介護認定を受ける必要があります。
この記事では、「介護 保険 申請」に関する手続きの流れや必要書類、申請後の注意点まで、初めての方にもわかりやすく解説します。制度を正しく理解し、スムーズに介護サービスを利用できるよう備えておきましょう。
介護保険サービスを利用するには申請が必要

介護保険は、65歳以上の高齢者(または40歳以上で特定疾病がある方)が、要介護状態になったときに、訪問介護やデイサービスなどの支援を受けられる制度です。
ただし、サービスを受けるには「要介護認定」を受ける必要があり、そのためには市区町村への「介護保険申請」が必須です。申請をしない限り、介護保険によるサービスは利用できません。
介護保険申請の流れ|6ステップで解説

介護保険申請からサービス利用開始までの流れは、以下の6ステップです。
① 要介護認定の申請をする
申請は、本人または家族が住んでいる市区町村の介護保険担当窓口で行います。地域包括支援センターでも相談・代行が可能です。
必要書類:
- 介護保険要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証(65歳以上の方に交付されている)
※自治体によって様式が異なるため、事前に確認しましょう。
② 主治医意見書の作成依頼
申請後、市区町村が本人の主治医に「主治医意見書」の作成を依頼します。これは、医師が本人の病状や生活状況を記載するもので、認定調査の参考資料になります。
※主治医がいない場合は、自治体が指定医を紹介してくれます。
③ 認定調査を受ける
市区町村の認定調査員が本人の自宅や施設を訪問し、心身の状態や生活状況を調査します。調査項目は約74項目あり、食事・排泄・移動・認知機能などが評価されます。
※家族が同席することで、補足説明ができるため安心です。
④ 要介護度の判定
調査結果と主治医意見書をもとに、コンピューターによる一次判定と、介護認定審査会による二次判定が行われます。最終的に「非該当」「要支援1・2」「要介護1〜5」のいずれかに認定されます。
⑤ ケアプランの作成
要介護認定を受けたら、ケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプラン(介護サービス計画書)を作成します。どのサービスを、どれくらいの頻度で利用するかを決める重要なステップです。
※ケアマネジャーは地域包括支援センターや居宅介護支援事業所で紹介してもらえます。
⑥ 介護サービスの利用開始
ケアプランに基づいて、訪問介護・通所介護・福祉用具レンタルなどのサービスが開始されます。契約は各事業所と個別に行うため、内容や費用をしっかり確認しましょう。
申請からサービス開始までの期間は?

介護保険申請から要介護認定の結果が出るまでには、原則30日以内とされています。ただし、主治医意見書の作成や認定調査のスケジュールによっては、1〜1.5か月程度かかることもあります。
その後、ケアプラン作成や事業所との契約を経て、サービス開始までにはさらに1〜2週間かかるのが一般的です。
退院後すぐに介護が必要な場合は、早めの申請が重要です。
申請時の注意点とよくある疑問

最後に、介護保険の申請に関する疑問に一問一答形式でお答えします。
Q1.本人が入院中でも申請できる?
はい、申請は可能です。ただし、介護保険サービスは入院中には利用できないため、退院後の生活に備えて申請しておくのが理想です。
Q2.要介護度が実際の状態と合っていない気がする…
その場合は「不服申し立て」や「再申請」が可能です。状態が変化した場合は、改めて申請し直すことで、より適切な要介護度が認定されることがあります。
Q3. 認定調査ではどんなことを聞かれる?
- 食事や排泄の自立度
- 着替えや入浴の介助の有無
- 認知症の有無や程度
- 薬の管理や服薬状況
- 社会的な交流の有無
※調査員は専門職ですが、家族の補足説明があるとより正確な評価につながります。
介護保険申請後にできること・すべきこと
申請が終わったら、結果を待つ間に以下の準備を進めておくとスムーズです。
- ケアマネジャーの候補を探しておく
- 利用したい介護サービスや施設を調べておく
- 親の生活環境(手すり設置、段差解消など)を見直す
- 家族間で介護の分担や費用負担について話し合う
介護は制度だけでなく、家族の協力体制や生活環境の整備も重要です。
まとめ|介護保険申請は「早め」「正確」「相談」がカギ
「介護 保険 申請」は、親の介護を始めるうえで欠かせない第一歩です。制度の流れを理解し、必要書類を整え、早めに申請することで、スムーズに介護サービスを受けられるようになります。
不安なことがあれば、地域包括支援センターや自治体の窓口に相談するのがベスト。一人で悩まず、制度と地域の力を借りながら、安心できる介護体制を整えていきましょう。
こちらの記事もおすすめ
【2025年最新版】介護サービスはいくらかかる?費用の目安と賢い備え方
在宅介護のメリットとは?家で介護する選択の意味と限界への備え方
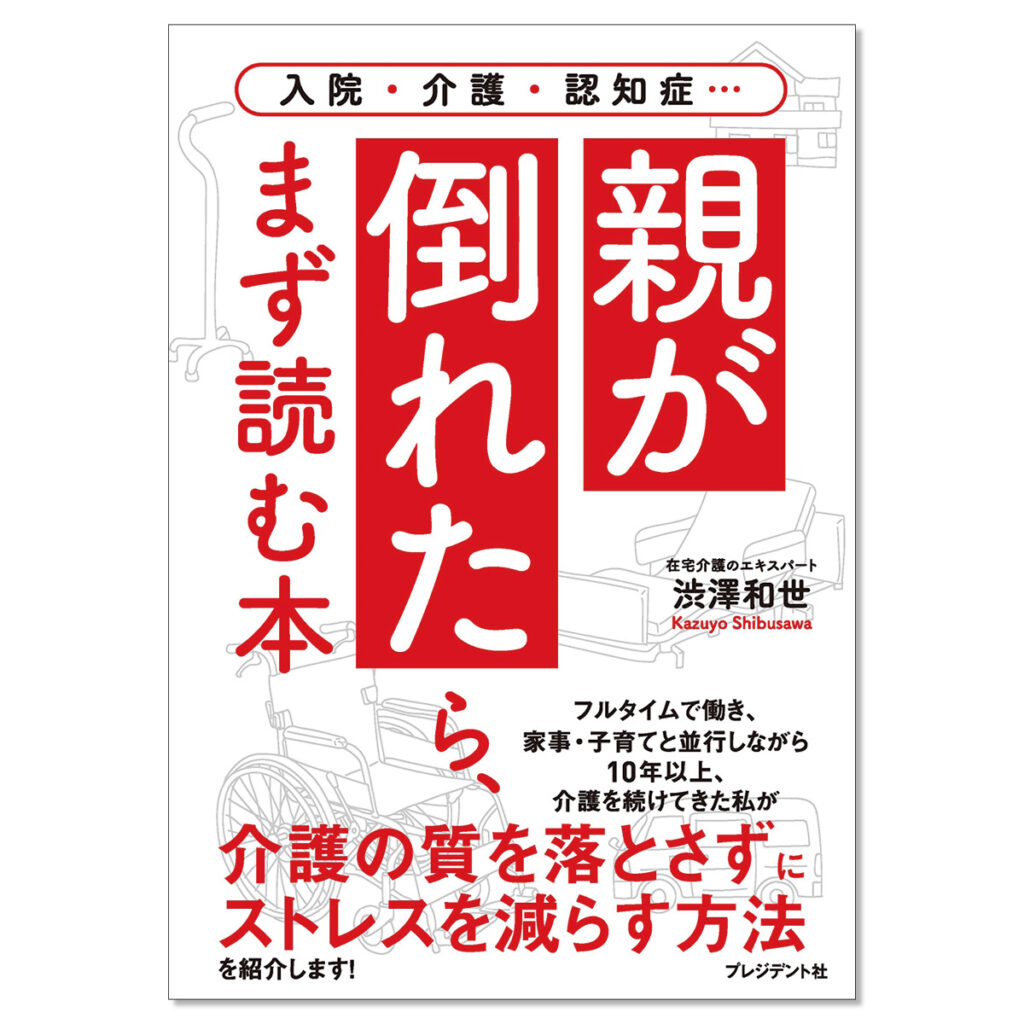
親が倒れたら、まず読む本
頑張らない介護とは、考え方のコツを知っているかどうかにかかっているのです。
①必要なサービスやモノにはお金を使って
(良い意味で)手抜きする、介護はお金で買う
②時間をかけるもかけないも結果的に得するかを判断する
③介護に完璧はない!良いことを考えながら気持ちを切り替える。
介護の質を落とさずにストレスを減らす方法を教えてくれる1冊です。
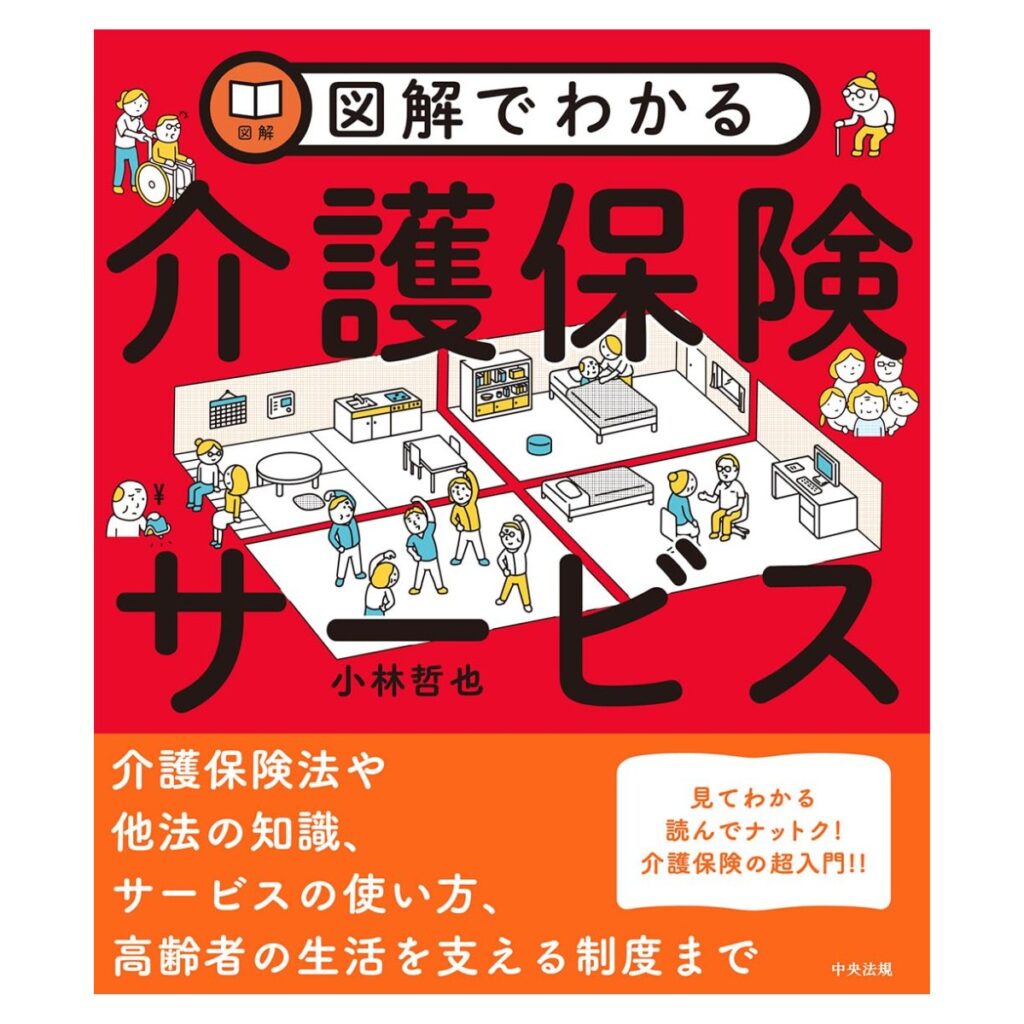
図解でわかる介護保険サービス
高齢者をとりまく課題から、介護保険制度や介護保険サービス、その他関連制度の知識をわかりやすく解説。豊富な図とイラストで視覚的に理解できる構成。介護保険サービスの従事者や新人職員、ケアマネ等の相談援助職など、高齢者支援にかかわるあらゆる方にオススメ。
投稿者プロフィール

- 神奈川県在住。Webライター。新卒で福祉企業に入社。ショートステイ、デイサービスで勤務したのち、デイ管理者や新規施設の立ち上げを担当。介護福祉士。2児のわんぱく男子を育てるフリーランスワーママ。
最新の投稿
 介護の豆知識2023年1月23日要介護認定の判定シミュレーション|想定要介護度をチェックしよう
介護の豆知識2023年1月23日要介護認定の判定シミュレーション|想定要介護度をチェックしよう 介護の豆知識2023年1月10日要介護認定の申請代行が出来る人は誰?|ケアマネージャーに依頼しよう
介護の豆知識2023年1月10日要介護認定の申請代行が出来る人は誰?|ケアマネージャーに依頼しよう 介護の豆知識2023年1月5日要介護認定の基準を知ろう|8つの認定段階と判定基準をご紹介
介護の豆知識2023年1月5日要介護認定の基準を知ろう|8つの認定段階と判定基準をご紹介 介護の豆知識2023年1月5日【保存版】介護保険申請の流れと必要書類|サービス利用までの手続き完全ガイド
介護の豆知識2023年1月5日【保存版】介護保険申請の流れと必要書類|サービス利用までの手続き完全ガイド











コメント