在宅介護にはメリット・デメリットがあります。
7年前に父の在宅介護が始まったときは突然のことで、メリットやデメリットなど考える暇もありませんでした。
この記事では、父の介護の経験により得た知見を元に、在宅介護のメリットやデメリット、限界を感じたときの対応策について解説しています。
在宅介護のデメリットを知ったからといって避けられるものではありませんが、そういった面にどう対応したらよいかを考えるきっかけになります。心配が少しでもぬぐえるよう、ぜひ最後までお読みください。
父の在宅介護が始まった経緯

父は2015年に脳出血で倒れ、病気により左半身に麻痺が残りました。麻痺はあるものの自力で移動でき、トイレも1人で行くことができたので、家族としては施設への入所の選択肢は頭になく、父は在宅介護を希望しました。
右も左も分からないままに、当然のように在宅での介護が始まったのです。
退院前には病院の作業療法士やケアマネージャーと相談し家を整え、在宅介護の準備をしました。病院からスタートした介護だったため、専門家とすぐにつながることができ、助言をいただけたのは本当に助かりました。
そんな私たちが感じた在宅介護のメリットとデメリットについてみていきましょう。
在宅介護のメリット

在宅介護を行ううえで私が感じたメリットは以下の3つです。
- 本人が住み慣れた家で安心して暮らせる
- 費用が抑えられる
- 本人の自立を促す
1. 本人が住み慣れた家で安心して暮らせる
父の入院中の目標は、自宅に帰ることでした。ほとんどの人が、施設や病院でなく、住み慣れた自宅に帰ることを希望します。慣れた環境で過ごすことは、精神的な安定はもちろん、家族と過ごすことでリハビリへの意欲、症状の改善につながることもあります。施設では、会話が減ってしまったりと、刺激が減ってしまい、認知症やうつ病などにつながってしまうことも少なくないようです。
介護状態になり、心も体もストレスを抱えている父にとって、自宅は精神的に安心できる場所でした。住み慣れた家に住むことは要介護者にとって、大きなメリットです。
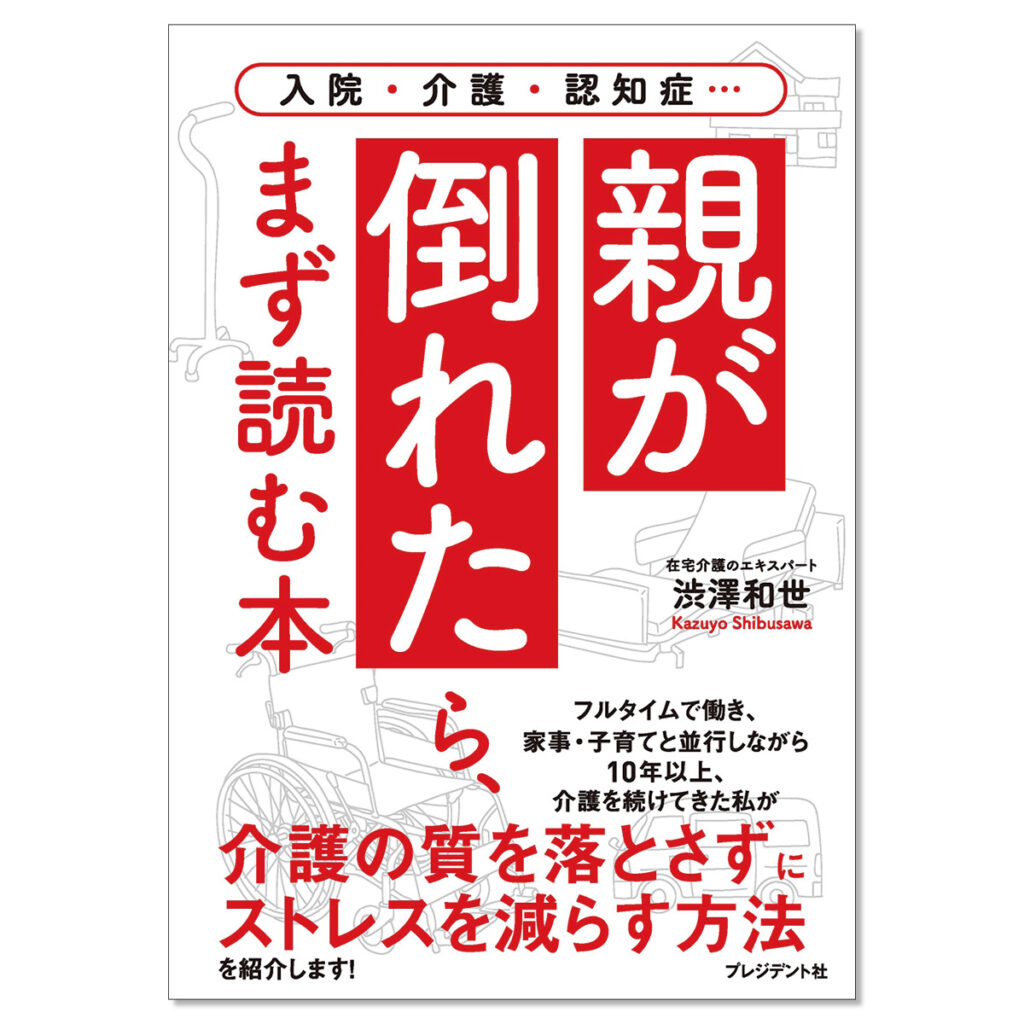
親が倒れたら、まず読む本
頑張らない介護とは、考え方のコツを知っているかどうかにかかっているのです。
①必要なサービスやモノにはお金を使って
(良い意味で)手抜きする、介護はお金で買う
②時間をかけるもかけないも結果的に得するかを判断する
③介護に完璧はない!良いことを考えながら気持ちを切り替える。
介護の質を落とさずにストレスを減らす方法を教えてくれる1冊です。
2. 費用が抑えられる
在宅介護では必要なサービスと時間を選べるので、費用を抑えることができます。
例えば、父は平日の午前か午後にしぼり、デイケアに通っています。通う場所は筋力向上を目的にした場所、作業療法士など専門家が在籍するところを選んでいます。
そのため、施設入所のように1日を通してサービスを受けられる場所と比べると、家族の負担はありますが、費用の面では抑えられます。
介護は意外とお金がかかります。在宅介護では、家族の状況や経済状況と照らし合わせながらサービスを選択できるので、費用面の見通しが立てられます。家族も安心して介護を続けられるのが、2つ目のメリットです。
3.本人の自立を促す
一緒に暮らしているため、父も生活のいろいろを共にします。そのため、自分でできることは自分でやってもらいます。
日常生活の一部を継続的に行うことで、本人の自立を促し、身体的・精神的な健康を保ちやすくなります。
在宅介護のデメリット

一方、在宅介護のデメリットは、一緒に同居する家族へ負担がかかることです。
我が家でいえば、特に、父の介護を主にしている母に休みはありません。
1日のうち、起きている時間の大半を父に気を配っています。介護は365日休みがないので、家族といえども想像以上に大変です。現在、介護生活も7年を超え、身体的・精神的疲れは増し、疲労が蓄積されています。
また、介護者中心の生活を送るため、自分を後回しにする場面が多くなります。
父がデイケアに行っているうちに買い物をすませ、帰宅後すぐに食べられるようご飯を準備。消耗品の買い出しや福祉用具の洗浄など父の時間軸に沿って生活するため、自分をないがしろにしているようでつらくなるようです。
なぜ自分ばかり苦労しなければならないのか思い悩む場面もあります。
在宅介護は介護者の拘束が長く、身体的、精神的な疲労を招くのがデメリットでしょう。
認知症の親へのイラッとする気持ちがスーッと消える本
接し方の工夫で症状が改善!介護の負担も軽減!
認知症になると、できないことが徐々に増えて自信と意欲を失い、時とともに自分が自分でなくなってしまう……。
認知症の親がとる不可解な行動の多くは、本人が抱える不安や恐怖から起こります。
本書では、認知症の初期・中期に現れる問題行動の理由&対処法について専門医がアドバイス。
接し方の工夫で症状が改善して、介護の負担も減っていきます。
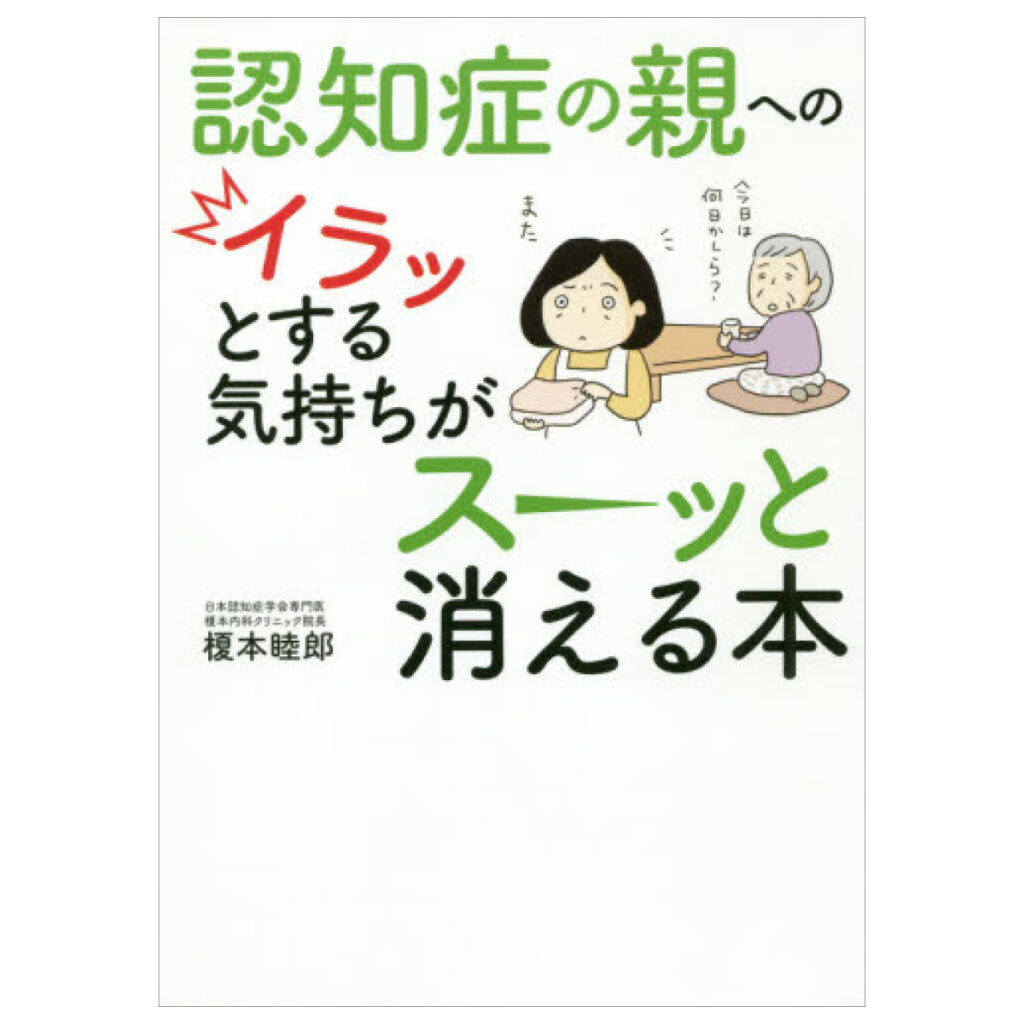
在宅介護の限界点に達する前の対応策

在宅介護が長くなると、疲れやイライラなどのストレスがたまり、限界を迎えるときがあります。
その場合、状況を変えるためショートステイを利用したり、ケアマネージャーに施設入所について相談したりしてみましょう。
父は介護生活6年目のころから、身なりに気を使わなくなりました。
トイレを終えると、オムツやズボンを上げ切らずに部屋に戻ることが増えたため、母が衣服を整えます。その都度自分で直すように声をかけますが父は聞く耳をもたず、母との小競り合いが増えてきました。それ以外にも、母は父へのストレスからイライラが募り、疲れた顔をするのが日常茶飯事になったのです。
このままでは母の「限界」がくると感じました。
そこで、ショートステイを利用。
最初はすっきりと心が晴れますが、元の生活が始まると好転しない現状に、強いストレスを感じているようでした。
そのため、さらに踏み込んでケアマネージャーに施設入居できないか相談。
結局、年齢や介護の度合いから、希望してもすぐに入れないことが分かり、在宅介護の継続となったのですが、ケアマネジャーに相談したことがきっかけで気持ちが吹っ切れたようです。
介護者が疲れ果てると、共倒れになる危険性があります。
- 気分転換に好きなことをする
- 介護者と離れた時間を過ごす
- ケアマネージャーなどに相談する
限界に達する前に、気持ちが楽になる方法を選びましょう。
施設入所について知りたい方は、こちらもご覧ください。
在宅介護のコツをつかんで、快適に暮らそう

在宅介護にはメリットがある半面、支える側のメンテナンスも重要です。
介護者が過ごしやすい空間を整えながら、介護者自身も息抜きに好きな時間を過ごして、心も体も整えましょう。
在宅介護のメリットとデメリット、限界に達したときの対応策を知ったうえで、介護に向き合ってみてください。
それでも、繰り返される介護のストレスやイライラ、悲しみ、困りごとに心が占拠されることもあります。誰かに愚痴を吐き出し、相談にのってほしい。そのときは、当サイトの「つぶやきたい」や公式LINEからご相談を承っています。お気軽に投稿してください。
公式LINEによる相談
介護情報を読む・介護用品の購入ができるだけでなく、気軽にご相談をしていただけます。
当サイトには介護・看護従事者が多数所属しており、ご相談にできる限りお答えいたします。
つぶやきスペース
誰かに聞いてほしいけど、近くに話せる人がいない。
同じ境遇の人と、この気持ちを共有したい。
そんなときは「つぶやきたい」のスペースでつぶやいてみてください。このサイトには介護をしている人たちが集まってきます。きっと共感してくれる人がいるはずです。
投稿者プロフィール

-
父が脳卒中により、介護生活がスタート。
メインの介護者である母をサポートしながら、2人の子育てに奮闘しています!孫育てをリハビリ代わりにして、今日も家族で力を合わせて過ごしてます。
最新の投稿
 病気・ケガ2023年6月5日親が病気に!会社への報告方法や利用できる休暇について解説
病気・ケガ2023年6月5日親が病気に!会社への報告方法や利用できる休暇について解説 病気・ケガ2023年5月30日病気の親と同居すべき?一緒に住む3つのメリットと5つのデメリットを解説
病気・ケガ2023年5月30日病気の親と同居すべき?一緒に住む3つのメリットと5つのデメリットを解説 介護の豆知識2023年3月24日在宅介護のメリット・デメリット|在宅の限界点への対策も解説
介護の豆知識2023年3月24日在宅介護のメリット・デメリット|在宅の限界点への対策も解説 介護の悩み2023年3月16日在宅介護で眠れない方へ|睡眠不足を解消する対応策を紹介
介護の悩み2023年3月16日在宅介護で眠れない方へ|睡眠不足を解消する対応策を紹介

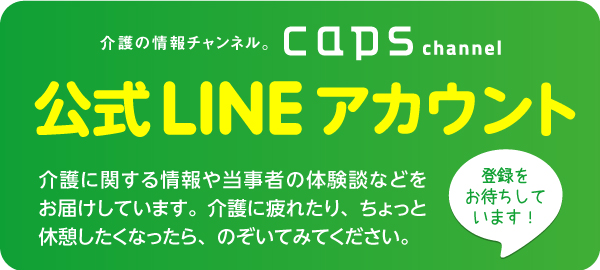











コメント