介護サービス利用時の自己負担額はどれくらいかかるのでしょうか。介護する側の身体や生活を守るためにも介護サービスを利用する方も多いでしょう。この記事では、介護サービスの費用について詳しく説明しています。
介護サービス利用時の自己負担額
介護サービスを利用した際の自己負担額の割合は、世帯人数や生活状況、要介護度、所得金額、介護サービス利用日数、利用時間などによって異なります。
まず、ひと月に使うことのできる介護サービスは、要介護度によって限度額が決まっており、この限度額に内で介護サービスを組み合わせて利用します。その限度額に対し、1割~3割の負担となります。
所得が220万円以上の場合は2割・3割負担、所得が220万円未満の場合は1割負担となります。
介護度が上がれば上がるほど限度額が上がりますが、自己負担額もそれに応じて上がります。
| 介護度 | 給付限度額 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
| 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
訪問・短期入所・通所などの在宅サービスや施設に入居して24時間ケアが受けられる施設サービスなど、介護者の負担を軽くすることができるサービスはいくつかありますが、在宅よりも経済的負担は大きくなります。
小規模多機能ホームやグループホームなど、比較的安価で手軽に利用することができる地域密着型サービスや、居住や食事や医療的ケア、入浴や掃除や買い物などのサポートが手厚いホテルのようなホスピタリティ溢れる施設もありますが、自己負担割合が高かったり、施設によって一時金や月額費用などが個別で決まっており、大きく差があるのでしっかりと調べる必要があります。
このような介護サービスや介護施設の利用に関しては、地域包括支援センターやケアマネジャーなどの介護分野のプロが相談に乗ってくれます。要介護者本人の所得や希望、家族の状況などを鑑みながらアドバイスしてくれますので、ひとりで抱え込まず、相談してみましょう。
その他、全額自費となりますが、民間サービスも多くあります。
介護保険サービスでは対応できない見守りや家族の食事など、介護者の負担を軽減してくれたり、家族が遠方にいて、親の側にいられないなどの場合、交通費を使って都度対応するよりも安く、有資格者によるこうしたサービスはとても安心です。通院介助や日々の見守りなどの単発の利用も可能で、介護保険サービスの自己負担分と全額自費のサービスを組み合わせることもできます。

身近な人に介護が必要になったときの手続きのすべて
鈩 裕和 (監修)
親が倒れた! どうする?
どこに相談すればいいの?お金は?申請はどうしたらいいの?在宅介護をするには?
そんな介護の不安を一気に解消してくれる1冊です。
見やすく、読みやすい大判サイズ。
急に訪れる介護に備えるために
介護はほとんどの場合、急に訪れます。
自己負担額を見て多いと感じましたか?または、この程度なのかと安心したでしょうか。
介護費用の負担は、基本的には親の年金や預貯金から捻出するべきとされていますが、例えば両親ともに介護が必要となった場合や、親の年金や預貯金をあてにできないこともあるでしょう。
突然介護が必要となり、突然自分たちが費用を負担しなければならないということもあります。
まずは日頃から親の将来のことを考え、お金について話し合いをしておくことが大切です。もしものときに、子供の立場として何をする必要があり、お金はどうしたらいいのか。
ほとんどの家庭では、親子間でのお金の話(預貯金はいくらあって、どこに預けているか、など)はしていないでしょう。離れて暮らしていて、親が認知症になったことに気づけずいた、その時にはもう銀行からお金をおろせなくなっていたということもあるかもしれません。
切り出しにくい話ではありますが、できる限り親とお金の話をきちんとすること、使える支援サービスや給付金について知っておくことが大切です。
まとめ

介護サービスを利用した際の自己負担額は、利用内容や生活状況など利用者によって違います。ニーズに合った最適なケアを受けられるようにするためにも、早めの対策を講じて十分な資金を確保しておくことが大事です。しっかり備えて安心を手に入れましょう。
こちらもおすすめ
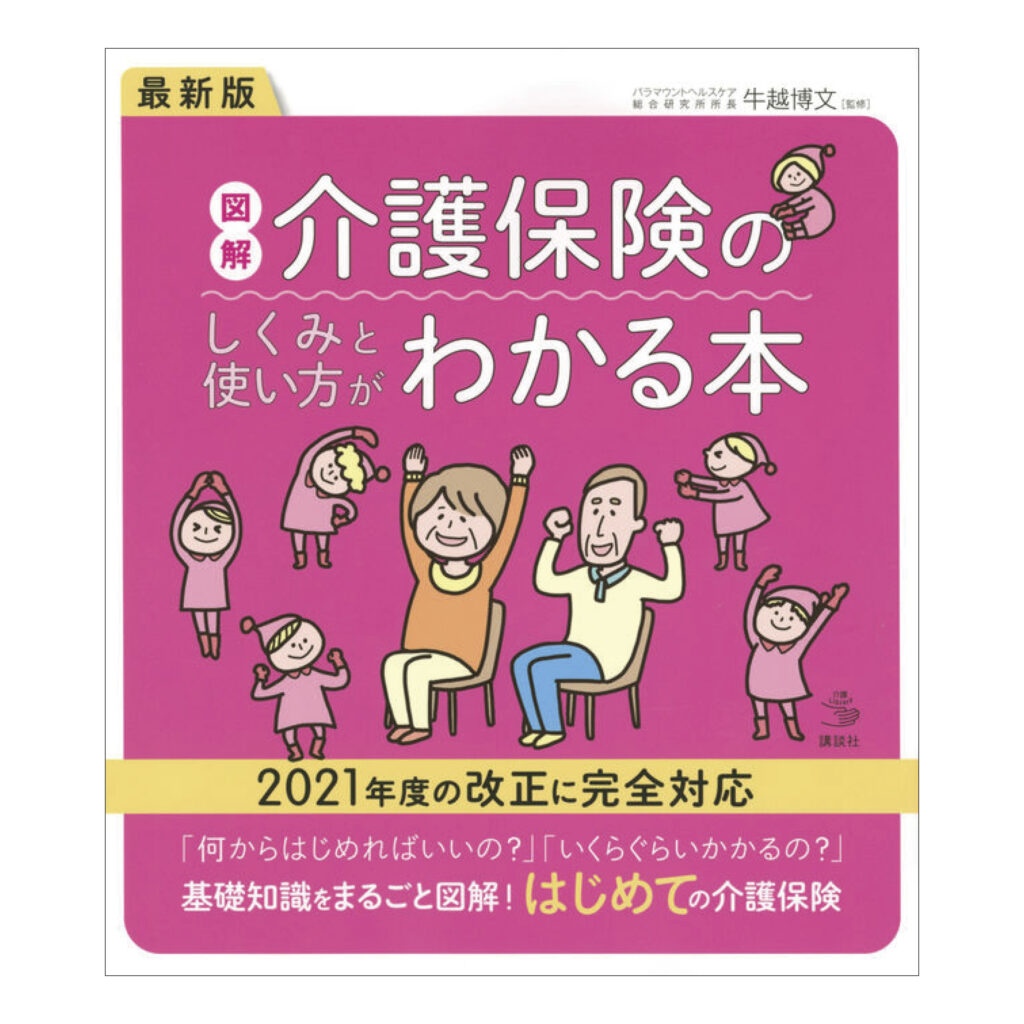
介護保険のしくみと使い方がわかる本
牛越 博文(監修)
介護保険を最大限に活用するためにいま知っておきたいことをイラスト図解。
申請の仕方、ケアマネの探し方、ケアプランの作り方、介護保険で受けられるサービス、お金の話、介護保険で入れる施設など複雑な介護保険のしくみと使い方がわかります。
介護保険をはじめて利用する人、はじめて介護の仕事に携わる人、今使っているサービスを見直したい人におすすめの一冊です。
親の介護は9割逃げよ
黒田尚子 (著)
心を軽くする家族介護者必読の1冊。
親子が共倒れにならないために、バランスをとりながら依存しない関係を築くことが求められてます。この本では認知症や介護に対する心構え、住まいや資産、家計の管理、相続や葬儀、お墓についての備えなど、「親の老後」の悩みをすべて解決します。家族に介護が必要になったらぜひ読んでいただきたい1冊です。
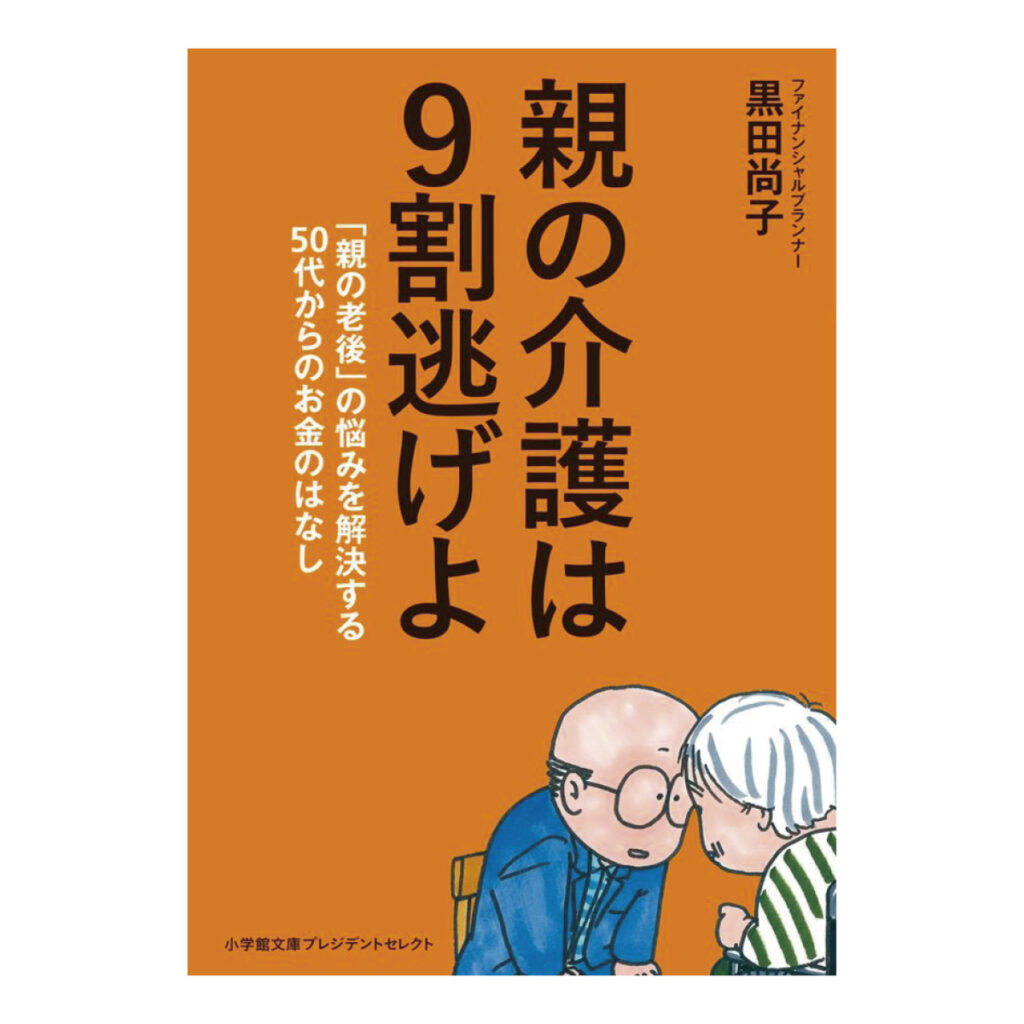
投稿者プロフィール

- 介護の経験を持つ方に体験談を教えて頂くシリーズ。
最新の投稿
 介護の悩み2023年2月10日20代で親の介護が必要になった。仕事と介護の両立の仕方
介護の悩み2023年2月10日20代で親の介護が必要になった。仕事と介護の両立の仕方 親の介護コラム2023年2月10日30代独身で親の介護|シングルマザーの私の生活はどうなる?
親の介護コラム2023年2月10日30代独身で親の介護|シングルマザーの私の生活はどうなる? 介護の悩み2023年2月10日在宅介護が辛いとき。経験者が語る辛い気持ちを軽減させる方法
介護の悩み2023年2月10日在宅介護が辛いとき。経験者が語る辛い気持ちを軽減させる方法 若年性認知症2023年2月10日家族が若年性認知症に!どんな支援がある?支援は受けられる?
若年性認知症2023年2月10日家族が若年性認知症に!どんな支援がある?支援は受けられる?












コメント