親の介護が必要になったとき、「施設に入れるべきか」「自宅で介護できるのか」と悩む方は多いでしょう。中でも在宅介護のメリットについて考えている人は、できるだけ親を住み慣れた家で支えたいという思いを持っているのではないでしょうか。
この記事では、在宅介護のメリットとデメリット、そして限界を感じたときの対処法まで、実体験をもとにわかりやすく解説します。
父の在宅介護が始まった経緯

父は2015年に脳出血で倒れ、病気により左半身に麻痺が残りました。麻痺はあるものの自力で移動でき、トイレも1人で行くことができたので、家族としては施設への入所の選択肢は頭になく、父は在宅介護を希望しました。
右も左も分からないままに、当然のように在宅での介護が始まったのです。
退院前には病院の作業療法士やケアマネージャーと相談し家を整え、在宅介護の準備をしました。病院からスタートした介護だったため、専門家とすぐにつながることができ、助言をいただけたのは本当に助かりました。
そんな私が感じた在宅介護のメリットとデメリット、限界を感じたときの対策をご一読ください。
在宅介護のメリットとは?

在宅介護には、施設では得られない「生活の質」や「精神的な安心感」があります。主なメリットは以下の3つです。
1. 本人が住み慣れた家で安心して暮らせる
父の入院中の目標は、自宅に帰ることでした。「自宅に帰りたい」という希望を持つ高齢者は多く、在宅介護はその願いを叶える選択肢となります。
施設ではなく自宅で過ごすことで、本人は環境の変化によるストレスを感じにくくなります。慣れた空間で家族と過ごす時間は、認知症やうつ症状の予防にもつながります。
2. 費用を抑えられる
施設介護に比べて、在宅介護は費用の調整がしやすいのも特徴です。介護保険を活用すれば、訪問介護やデイサービスなどを1〜3割の自己負担で利用できます。施設入所のように1日を通してサービスを受けられる場所と比べると、家族の負担はありますが、費用の面では抑えられます。
サービスの頻度や内容を家族の状況に合わせて選べるため、無理のない範囲で介護を続けることが可能です。
3. 本人の自立を促しやすい
家族と一緒に暮らすことで、本人が「できることは自分でやろう」と意欲を持ちやすくなります。日常生活の一部を継続することで、身体的・精神的な健康維持にもつながります。
在宅介護のデメリットと限界

もちろん、在宅介護には負担もあります。特に介護者が同居している場合、生活の中心が介護になりやすく、心身の疲労が蓄積しがちです。
1. 介護者の拘束時間が長い
在宅介護は365日休みがなく、介護者が自分の時間を持てなくなることもあります。買い物や食事の準備、通院の付き添いなど、生活のすべてが介護中心になると、疲れやストレスが限界に達することも。
2. 介護者の精神的な負担
「なぜ自分だけが苦労しなければならないのか」と感じる場面も出てきます。認知症の親とのやり取りや、思うようにいかない介護生活に、孤独や悲しみを抱えることも少なくありません。
3. 介護者の健康リスク
介護者が疲れ果ててしまうと、共倒れのリスクも高まります。特に高齢の配偶者が介護を担っている場合、体力的な限界が早く訪れる可能性があります。
限界を感じたときの対処法

在宅介護が長くなると、疲れやイライラなどのストレスがたまり、限界を迎えるときがあります。
在宅介護を続ける中で「もう無理かもしれない」と感じたら、以下のような対策を検討しましょう。
1. ショートステイの活用
一時的に施設で介護を受ける「ショートステイ」は、介護者の休息にもつながります。数日〜数週間の利用が可能で、介護保険の対象となるため費用も抑えられます。
2. ケアマネジャーへの相談
介護のプロであるケアマネジャーに相談することで、在宅介護の限界を見極め、必要な支援や施設入所の選択肢を提案してもらえます。
3. 家族間での役割分担
介護を一人で抱え込まず、兄弟姉妹や親戚と協力体制を築くことも重要です。経済的な支援や、定期的な訪問など、できる範囲で分担することで負担が軽減されます。
在宅介護を続けるための工夫

在宅介護を長く続けるには、介護者自身のケアも欠かせません。
- 好きなことをする時間を意識的に作る
- 介護者向けの相談窓口やSNSで気持ちを共有する
- 福祉用具や住宅改修で介護環境を整える
- デイサービスや訪問介護を組み合わせて負担を分散する
在宅介護のメリットを最大限に活かすには、介護者の心と体の余裕が必要です。
まとめ|在宅介護は“家族の選択”であり“支え合いの形”
在宅介護には、本人の安心感や費用面のメリットがありますが、介護者の負担も大きくなりがちです。だからこそ、制度やサービスを活用しながら、無理なく続けられる体制を整えることが大切です。
「在宅 介護 メリット」を検索したあなたは、きっと家族のことを真剣に考えている方でしょう。その思いを大切にしながら、必要な支援を受け、家族みんなで支え合える介護の形を見つけていきましょう。
在宅介護を行う人におすすめの本
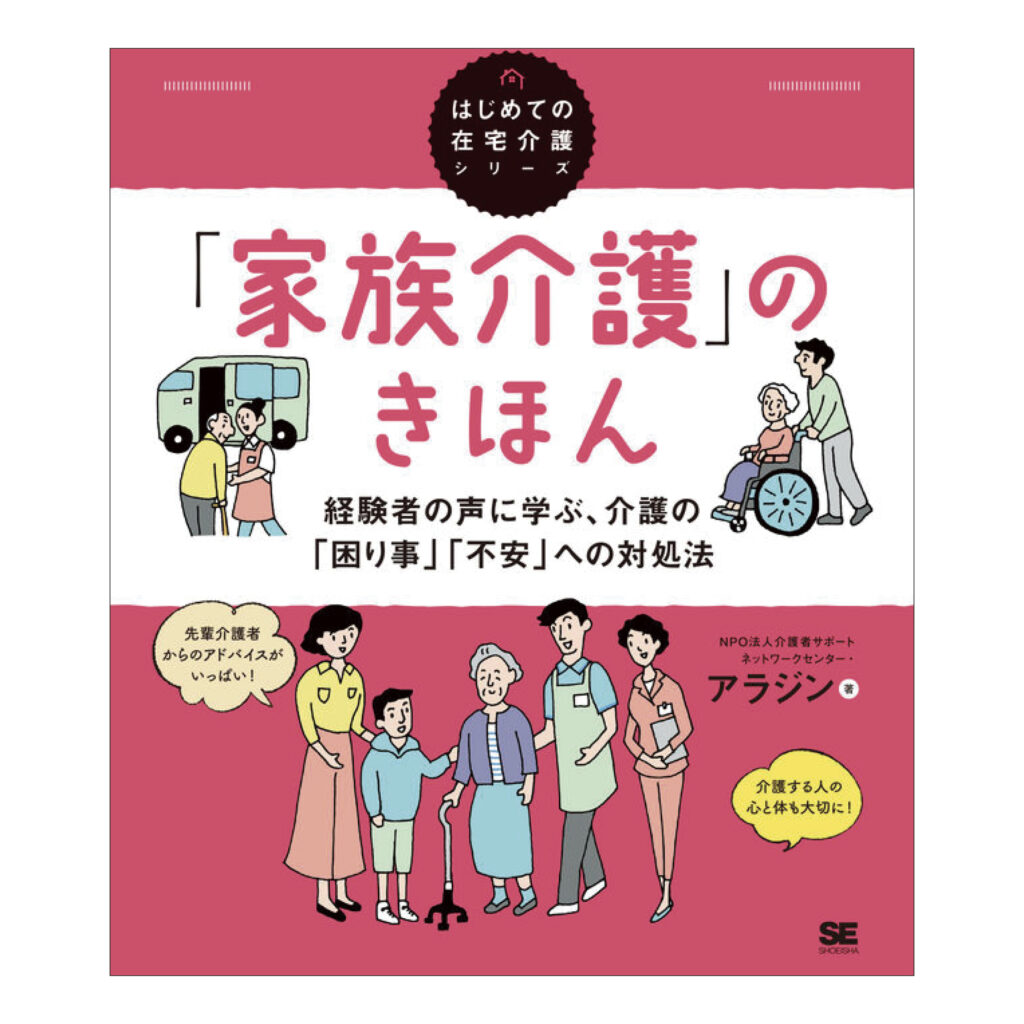
「家族介護」のきほん
アラジン(著)
「介護する人」に寄り添う、在宅介護の実用書!
20年以上にわたり、介護をしている家族の相談やサポートを続けているNPO法人の「アラジン」の蓄積された経験や豊富な相談事例をもとに、介護者の暮らしや人生に寄り添った、リアルな介護の乗り切り方を伝授します。
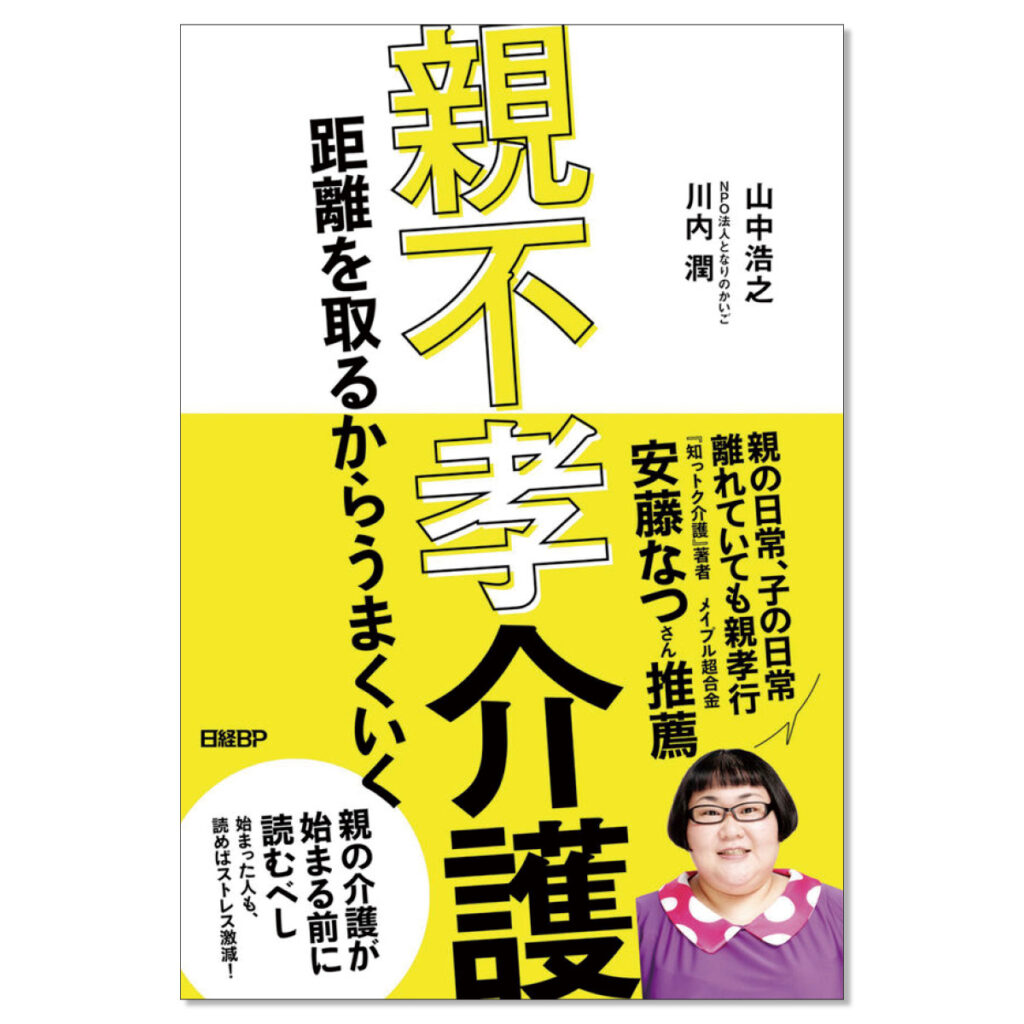
親不孝介護 距離を取るからうまくいく
「長男だから、親を引き取るか実家に帰らないと」「家族全員で、親を支えてあげないと」「親のリハビリ、本人のために頑張らせないと」「親が施設に入ったら、せめて、まめに顔を見せに行かないと」そんなものは必要なし!
「親と距離を取るから、介護はうまくいく」。
一見、親不孝と思われそうなスタンスが、介護する側の会社員や家族を、そしてなにより介護される親をラクにしていきます。

身近な人に介護が必要になったときの手続きのすべて
親が倒れた! どうする?
どこに相談すればいいの?お金は?申請はどうしたらいいの?在宅介護をするには?
そんな介護の不安を一気に解消してくれる1冊です。
見やすく、読みやすい大判サイズ。
こちらの記事もおすすめ
- 要介護5で在宅介護は無理?介護事例や施設選びのコツなど詳しく解説!
- 【体験者1100人に聞いた】在宅介護で大変なことランキング|1位は「コミュニケーション」
- 親の介護を行う30代40代が介護離職しないために知っておいて欲しいこと
投稿者プロフィール

-
父が脳卒中により、介護生活がスタート。
メインの介護者である母をサポートしながら、2人の子育てに奮闘しています!孫育てをリハビリ代わりにして、今日も家族で力を合わせて過ごしてます。
最新の投稿
 病気・ケガ2023年6月5日親が病気に!会社への報告方法や利用できる休暇について解説
病気・ケガ2023年6月5日親が病気に!会社への報告方法や利用できる休暇について解説 病気・ケガ2023年5月30日病気の親と同居すべき?一緒に住む3つのメリットと5つのデメリットを解説
病気・ケガ2023年5月30日病気の親と同居すべき?一緒に住む3つのメリットと5つのデメリットを解説 介護の豆知識2023年3月24日在宅介護のメリットとは?家で介護する選択の意味と限界への備え方
介護の豆知識2023年3月24日在宅介護のメリットとは?家で介護する選択の意味と限界への備え方 介護の悩み2023年3月16日在宅介護で眠れない方へ|睡眠不足を解消する対応策を紹介
介護の悩み2023年3月16日在宅介護で眠れない方へ|睡眠不足を解消する対応策を紹介











コメント