高齢の親が遠方で一人暮らしをしていると、健康状態の変化に気づきにくく、突然の病気や入院に慌ててしまうことがあります。「離れて 暮らす 親 病気」という状況は、誰にでも起こり得る現実です。仕事や家庭の事情で頻繁に帰省できない中、どのように親を支えればよいのでしょうか。
この記事では、離れて暮らす親が病気になったときにできるサポート方法や、介護保険制度の活用、働きながら支援するための工夫について詳しく解説します。
離れて暮らす親が病気になったとき、まずすべきこと

親が病気になったという連絡を受けたとき、多くの人が「すぐに駆けつけたい」と思うでしょう。しかし、仕事や家庭の事情で動けない場合もあります。まずは冷静に状況を把握することが大切です。
- 病院の診断内容と治療方針を確認する
- 緊急連絡先や主治医の情報を把握する
- 親の生活環境(自宅の安全性、食事、服薬状況など)をチェックする
可能であれば、短期間でも帰省して直接顔を見て話すことが望ましいですが、それが難しい場合は、電話やビデオ通話でこまめに様子を確認しましょう。
離れて暮らす親とのコミュニケーションを深める工夫
親が病気になったとき、物理的な距離以上に気になるのが「心の距離」です。会いに行けないもどかしさや、何もできないという罪悪感を抱える人も少なくありません。そんなときこそ、精神的なつながりを意識したコミュニケーションが大切です。
親の不安や愚痴を受け止める姿勢を持つ
病気になると、親も弱音を吐きたくなるものです。「そんなこと言わないで」と否定せず、「そう思うよね」と共感することで、親の気持ちに寄り添えます。
定期的な連絡を欠かさない
電話やビデオ通話で、親の体調だけでなく気持ちにも寄り添うような会話を心がけましょう。「今日はどうだった?」という一言が、親にとって大きな安心になります。
感謝や励ましの言葉を伝える
「頑張ってるね」「無理しないでね」といった言葉は、親の孤独感や不安を和らげる力があります。介護や治療に前向きになれるよう、心の支えになる言葉を意識して届けましょう。
写真や手紙など“形に残るもの”を送る
スマホが使えない親には、手紙や写真を送るのも効果的です。部屋に飾れるものや、何度も読み返せるものは、親の心を落ち着かせる大切なツールになります。
病気や介護に備えて知っておきたい制度
親が病気になったとき、医療費や介護費用が心配になる方も多いでしょう。以下のような制度を活用することで、負担を軽減できます。
1. 介護保険制度
要介護認定を受けることで、訪問介護やデイサービスなどの介護サービスを1〜3割の自己負担で利用できます。申請は市区町村の窓口や地域包括支援センターで行えます。
2. 高額介護サービス費制度
1か月の自己負担額が一定額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。所得に応じて上限額が設定されており、家計の大きな助けになります。
3. 特定入所者介護サービス費(補足給付)
施設介護にかかる食費・居住費の負担を軽減する制度です。所得や資産が一定以下の方が対象で、申請により補助が受けられます。
4. 地域包括支援センターへの相談
各自治体に設置されている「地域包括支援センター」では、介護保険の申請やサービスの紹介、生活支援の相談などを無料で受けることができます。
働きながら親を支援する方法

介護のために仕事を辞めるのは現実的ではありません。そこで、働きながらでもできる支援方法を工夫することが重要です。
1. 見守りサービスの導入
スマートフォンや見守りカメラを使って、遠隔で親の様子を確認できるサービスがあります。月額数千円で利用できるものもあり、費用対効果の高い支援手段です。
2. 配食サービスの利用
高齢者向けの配食サービスを利用すれば、栄養バランスの取れた食事を定期的に届けてもらえます。買い物や調理が難しい親にとって、大きな助けになります。
3. 地域のボランティアや民間サービスの活用
公的サービスだけでなく、地域のボランティア団体や民間の見守りサービスなども活用できます。多少費用がかかっても、自分の生活を大きく変えずに親を支援できる方法として有効です。
離れて暮らす親の介護のための移動費をサポートしてくれる制度
航空会社によっては、要介護・要支援認定を受けた親族の介護を目的とした帰省に対して割引を提供しています。
| 航空会社 | 割引名 | 割引率 | 条件 |
|---|---|---|---|
| JAL | 介護帰省割引 | 約35% | 要介護者の二親等以内の親族など。事前登録が必要。 |
| ANA | 介護割引 | 約34% | 同上。ANAマイレージクラブ登録が必要。 |
また、北海道など一部の自治体では、遠距離介護者向けの交通費補助制度を設けている場合がありますので、親の居住地の自治体に問い合わせてみても良いでしょう。
実家の環境を整えることもサポートの一環
親が一人で暮らす自宅の安全性を確認し、必要に応じて改善することも重要です。
- 手すりの設置や段差の解消
- 照明の明るさやスイッチの位置の見直し
- ガス器具や電気製品の安全確認
- 緊急時に連絡できる体制の整備
これらの対策を講じることで、親が安心して暮らせる環境を整えることができます。
親の病気に備えて、今できること
離れて暮らす親の病気に備えるには、以下のような準備が有効です。
- 親の健康状態や生活習慣を把握する
- 年金・保険・預貯金などの経済状況を確認する
- 介護保険制度や地域の支援サービスを調べておく
- 家族で役割分担や連絡体制を話し合っておく
親が元気なうちに、少しずつ準備を進めることで、いざという時に慌てずに対応できます。
まとめ:離れて暮らす親が病気になっても、できることはある

親が病気になったとき、離れて暮らしていると「何もできない」と感じてしまうかもしれません。しかし、制度の活用や遠隔支援の工夫によって、働きながらでも親を支えることは可能です。
大切なのは、親が元気なうちから情報を共有し、家族で話し合い、将来に備えておくこと。「離れて 暮らす 親 病気」という不安を少しでも軽減するために、今できることから始めてみましょう。
こちらもおすすめ

身近な人に介護が必要になったときの手続きのすべて
親が倒れた! どうする?
どこに相談すればいいの?お金は?申請はどうしたらいいの?在宅介護をするには?
そんな介護の不安を一気に解消してくれる1冊です。
見やすく、読みやすい大判サイズ。
親不孝介護 距離を取るからうまくいく
「長男だから、親を引き取るか実家に帰らないと」「家族全員で、親を支えてあげないと」「
親のリハビリ、本人のために頑張らせないと」「親が施設に入ったら、せめて、まめに顔を見せに行かないと」そんなものは必要なし!
「親と距離を取るから、介護はうまくいく」。
一見、親不孝と思われそうなスタンスが、介護する側の会社員や家族を、そしてなにより介護される親をラクにしていきます。
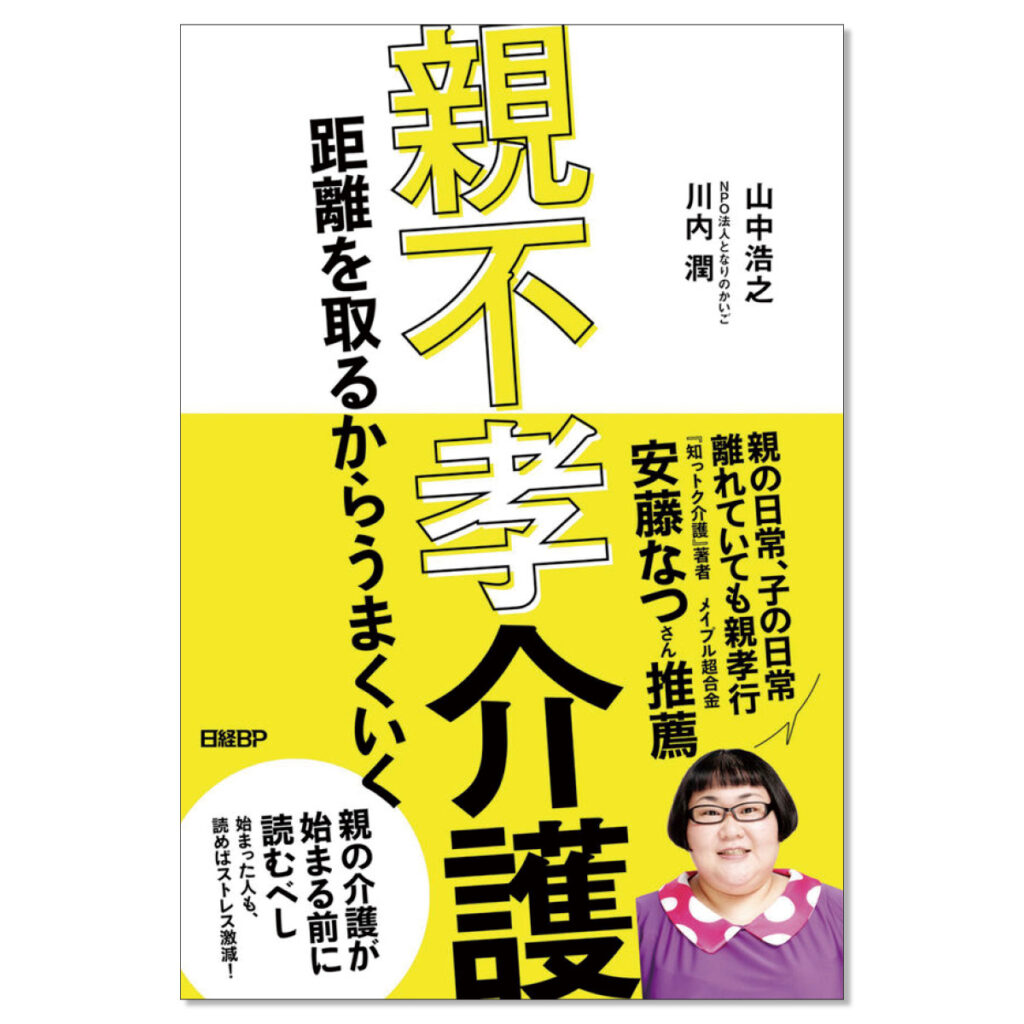
投稿者プロフィール

- 介護の経験を持つ方に体験談を教えて頂くシリーズ。
最新の投稿
 介護の悩み2023年2月10日20代で親の介護が必要になった。仕事と介護の両立の仕方
介護の悩み2023年2月10日20代で親の介護が必要になった。仕事と介護の両立の仕方 親の介護コラム2023年2月10日30代独身で親の介護|シングルマザーの私の生活はどうなる?
親の介護コラム2023年2月10日30代独身で親の介護|シングルマザーの私の生活はどうなる? 介護の悩み2023年2月10日在宅介護が辛いとき。経験者が語る辛い気持ちを軽減させる方法
介護の悩み2023年2月10日在宅介護が辛いとき。経験者が語る辛い気持ちを軽減させる方法 若年性認知症2023年2月10日家族が若年性認知症に!どんな支援がある?支援は受けられる?
若年性認知症2023年2月10日家族が若年性認知症に!どんな支援がある?支援は受けられる?












コメント