親の介護が始まると、兄弟間の関係に変化が生じることがあります。特に「自分ばかりが負担している」と感じると、不満やストレスが積み重なり、トラブルに発展することも。実際、「親の介護 兄弟 不公平」と検索する人は年々増えており、介護が家族関係に与える影響の大きさがうかがえます。
この記事では、兄弟間で介護の負担が不公平になる理由と、トラブルをこじらせないための具体的な対処法を解説します。。
なぜ親の介護で兄弟間に不公平が生じるのか?
介護の負担が偏る背景には、さまざまな要因があります。以下は、よくある4つのケースです。
1. 長男・長女への“当然”という押しつけ
「長男だから」「長女だから」という理由で、親や兄弟から介護を当然のように任されるケースがあります。しかし、民法上の扶養義務は兄弟全員に等しくあるため、役割を一方的に押しつけるのは不公平です。
2. 親の近くに住んでいるからという理由
「近くに住んでいるんだから、介護はお願いね」と言われてしまうことも。実家暮らしの場合は「住まわせてもらっているんだから当然」といったプレッシャーを感じることもあります。
物理的な距離は確かに介護のしやすさに影響しますが、それだけで負担を決めるのは危険です。
3. 育児や仕事を理由に介護を避ける兄弟
「子どもが小さいから」「仕事が忙しいから」といった理由で、介護を手伝わない兄弟もいます。事情は理解できても、すべての負担が一人に偏ると不満が募ります。
4. 役割分担が曖昧なままスタートしてしまう
「とりあえず私がやるね」と始めた介護が、いつの間にか“全部自分”になってしまうケースも。兄弟間で明確な分担がないと、負担の偏りが常態化しやすくなります。
不公平が続くとどうなる?兄弟間トラブルの実例

介護の不公平が続くと、以下のようなトラブルに発展することがあります。
- 金銭的な負担を巡る争い
- 施設入所の判断を巡る対立
- 相続時の感情的な衝突
- 配偶者や子どもを巻き込んだ家族間の亀裂
「介護はしていないのに、口だけ出してくる」「お金は出さないのに、文句ばかり言う」——こうした不満が積み重なると、兄弟間の信頼関係が崩れてしまいます。
トラブルを防ぐための対処法
兄弟間の不公平を感じたときは、感情的になる前に以下のような対策を講じましょう。
1. 介護の実態を“見える化”する
まずは、誰がどれだけ介護に関わっているかを整理しましょう。
- 通院の付き添い回数
- デイサービスの送迎頻度
- 食事や排泄の介助時間
- 金銭的な支出額
これらを一覧にすることで、負担の偏りが客観的に見えるようになります。
2. スケジュールと役割を共有する
兄弟それぞれの生活状況を踏まえたうえで、できること・できないことを明確にします。
- 週末だけでも訪問できるか
- 金銭的支援は可能か
- 緊急時の連絡体制はどうするか
「できる範囲で関わる」ことを前提に話し合うことで、納得感のある分担が可能になります。
3. 配偶者や義理の家族は“頭数に入れない”
「嫁が専業主婦だから介護できるでしょ」といった発言は、トラブルの火種になります。介護は基本的に“実子”が担うものとし、配偶者には無理をさせないことが原則です。
4. 介護をしていない人は口を出さない
実際に介護をしていない兄弟が、介護の内容に口を出すと、現場の負担者は強いストレスを感じます。お金を出しているからといって、介護の方針に干渉するのは避けるべきです。
兄弟間で感情的な対立が起きてしまった場合は、第三者を交えて話し合うことが有効です。地域包括支援センターの相談員やケアマネジャーは、介護の現場をよく理解しており、家族間の調整にも慣れています。 「家族だけで話すと感情的になってしまう」「冷静に話し合えない」という場合は、中立的な立場の人に同席してもらうことで、話し合いが前向きに進むことがあります。介護は制度やサービスの選択肢も多いため、専門家の視点を取り入れることで、兄弟それぞれが納得できる分担案を見つけやすくなります。
感情のケアも忘れずに

介護は身体的な負担だけでなく、感情面の疲労も大きいものです。兄弟間で愚痴を言い合える関係性があるだけで、負担の感じ方は大きく変わります。
- 「ありがとう」「助かるよ」といった言葉を意識的にかける
- 介護者同士で定期的に話す時間を設ける
- 第三者(ケアマネジャーなど)を交えて話し合う
感情のケアは、介護を長く続けるための大切な土台です。
まとめ|親の介護で兄弟間に不公平を感じたら、まずは“見える化”と対話から
親の介護について兄弟と不公平感を感じたとき、まずは冷静に状況を整理し、話し合いの場を持つことが大切です。介護は一人で抱えるものではなく、兄弟それぞれができる範囲で関わることで、負担を分散できます。
不満や怒りを溜め込む前に、言葉にして伝えること。そして、感情ではなく事実をもとに話し合うこと。それが、兄弟間の信頼関係を守りながら、親の介護を乗り越えるための第一歩です。
介護について悩むあなたにおすすめの本
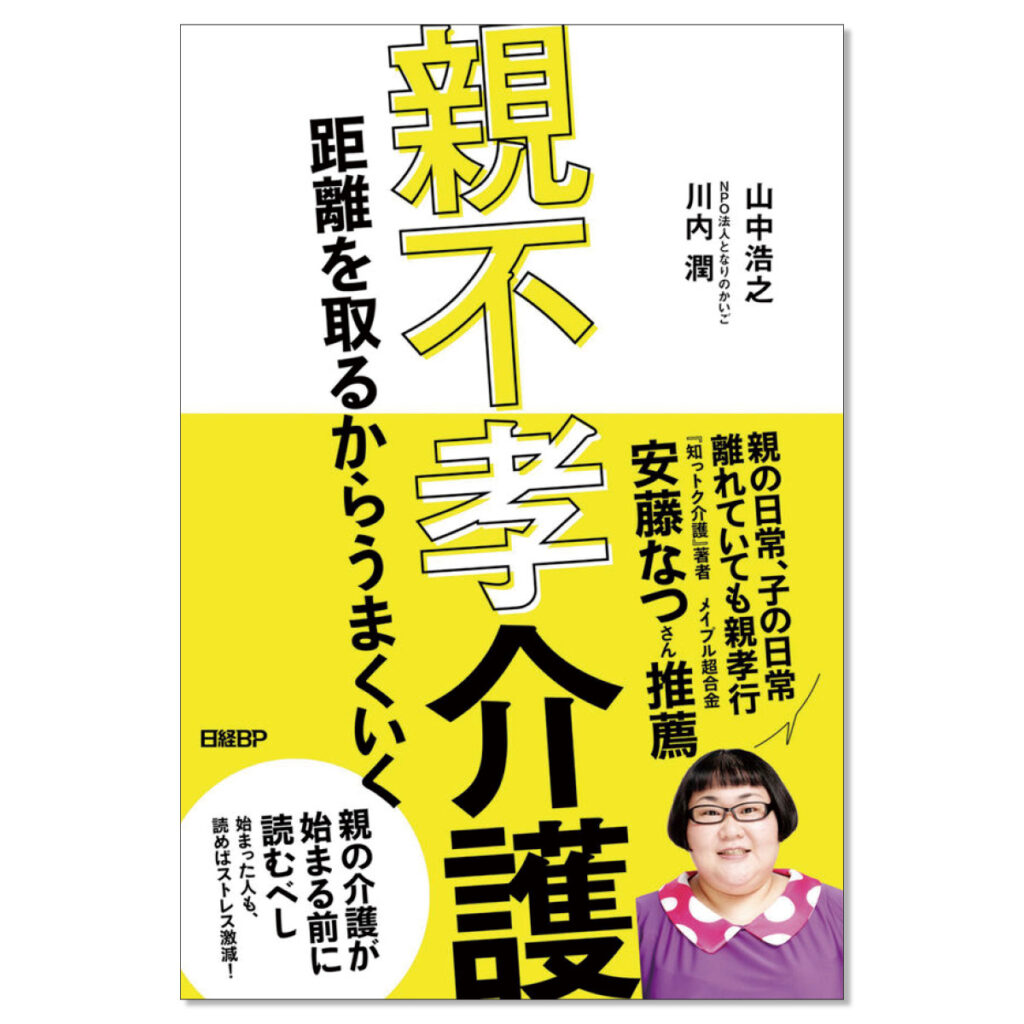
親不孝介護 距離を取るからうまくいく
「長男だから、親を引き取るか実家に帰らないと」「家族全員で、親を支えてあげないと」「
親のリハビリ、本人のために頑張らせないと」「親が施設に入ったら、せめて、まめに顔を見せに行かないと」そんなものは必要なし!
「親と距離を取るから、介護はうまくいく」。
一見、親不孝と思われそうなスタンスが、介護する側の会社員や家族を、そしてなにより介護される親をラクにしていきます。
「家族介護」のきほん
「介護する人」に寄り添う、在宅介護の実用書!
20年以上にわたり、介護をしている家族の相談やサポートを続けているNPO法人の「アラジン」の蓄積された経験や豊富な相談事例をもとに、介護者の暮らしや人生に寄り添った、リアルな介護の乗り切り方を伝授します。
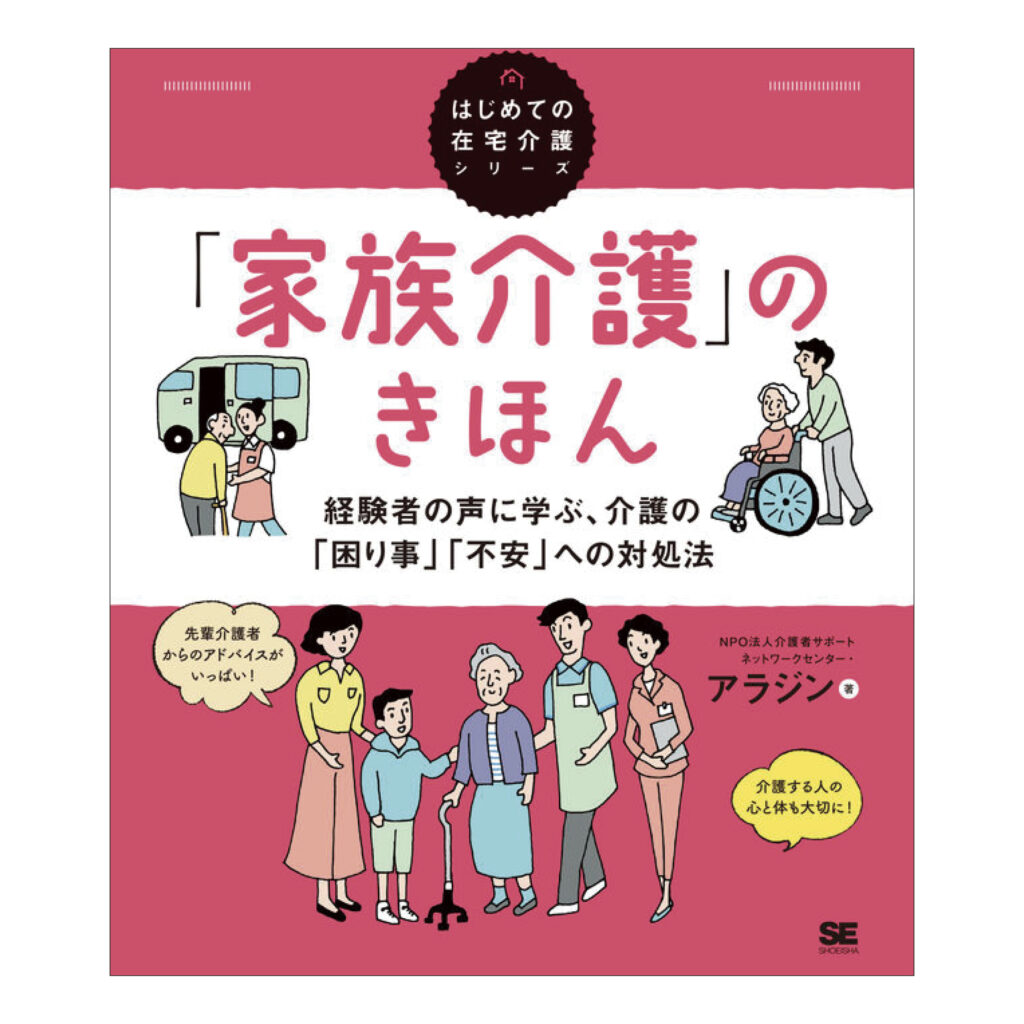
こちらの記事もおすすめ
投稿者プロフィール

- 介護の経験を持つ方に体験談を教えて頂くシリーズ。
最新の投稿
 介護の悩み2023年2月10日20代で親の介護が必要になった。仕事と介護の両立の仕方
介護の悩み2023年2月10日20代で親の介護が必要になった。仕事と介護の両立の仕方 親の介護コラム2023年2月10日30代独身で親の介護|シングルマザーの私の生活はどうなる?
親の介護コラム2023年2月10日30代独身で親の介護|シングルマザーの私の生活はどうなる? 介護の悩み2023年2月10日在宅介護が辛いとき。経験者が語る辛い気持ちを軽減させる方法
介護の悩み2023年2月10日在宅介護が辛いとき。経験者が語る辛い気持ちを軽減させる方法 若年性認知症2023年2月10日家族が若年性認知症に!どんな支援がある?支援は受けられる?
若年性認知症2023年2月10日家族が若年性認知症に!どんな支援がある?支援は受けられる?











コメント