脳梗塞は、脳の血管が詰まることで血流が止まり、脳細胞が損傷を受ける病気です。特に高齢者は発症リスクが高く、60代以降から増加し、80代で最も多くなります。突然の発症や後遺症の可能性があるため、早期発見と適切な対応が重要です。
高齢者が脳梗塞になりやすい理由
高齢者が脳梗塞を発症しやすい背景には、以下のような要因があります。
✅ 血管の老化
加齢により血管が硬くなり、動脈硬化が進行します。これにより血流が悪くなり、血栓ができやすくなります。
✅ 高血圧・糖尿病・脂質異常症
これらの生活習慣病は、脳梗塞の主要なリスク因子です。高齢者はこれらの疾患を複数抱えていることが多く、血管への負担が大きくなります。
✅ 心臓疾患(不整脈・心房細動など)
心臓でできた血栓が脳に飛び、脳の太い血管を詰まらせる「心原性脳塞栓症」が高齢者に増えています。
脳梗塞の予兆と初期症状
脳梗塞は突然発症することが多いですが、前兆(TIA:一過性脳虚血発作)が現れる場合もあります。以下のような症状が見られたら、すぐに医療機関を受診しましょう。
主な予兆・初期症状
- 手足のしびれや脱力(片側だけ)
- 顔の片側が麻痺している
- 言葉が出にくい、ろれつが回らない
- 視野が欠ける、片目が見えにくい
- 歩行が不安定になる
- 急に意識がぼんやりする
TIAは数分〜30分程度で症状が消えることがありますが、放置すると本格的な脳梗塞につながる危険性があります。
脳梗塞の種類と特徴
脳梗塞は、原因によって以下の3つに分類されます。
✅ ラクナ梗塞
脳の深部にある細い血管が詰まるタイプ。進行がゆっくりで、軽度の麻痺やしびれが主な症状。高血圧が主な原因。
✅ アテローム血栓性脳梗塞
太い血管の動脈硬化によって血栓ができ、脳の一部が塞がれるタイプ。糖尿病や脂質異常症が関係。
✅ 心原性脳塞栓症
心臓でできた血栓が脳に飛び、太い血管を急に塞ぐタイプ。突然の重い症状が特徴で、命に関わることも。
高齢者の脳梗塞治療と回復の可能性
脳梗塞は、発症からの時間が治療の成否を左右します。特に「t-PA療法」は発症から4.5時間以内に行う必要があります。
✅ t-PA療法
血栓を溶かす薬を静脈注射する治療法。早期に血流を再開させることで、後遺症を軽減できます。
✅ 血管内治療
カテーテルを使って血栓を取り除く方法。発症から8時間以内が目安。t-PAが使えない場合にも有効です。
✅ リハビリテーション
後遺症が残った場合は、理学療法・作業療法・言語療法などを組み合わせて、機能回復を目指します。高齢者でも、適切なリハビリによって生活機能を維持・改善することが可能です。
脳梗塞後の介護で注意すべきポイント

脳梗塞の後遺症には個人差がありますが、介護が必要になるケースも少なくありません。以下の点に注意しましょう。
✅ 生活動作のサポート
麻痺や言語障害がある場合、食事・入浴・排泄などの日常動作に介助が必要になります。本人の残存能力を活かしながら、できることは自分で行ってもらう工夫が大切です。
✅ 再発予防の支援
薬の服用管理、食事の塩分・脂質制限、適度な運動など、生活習慣の見直しをサポートしましょう。
✅ 精神的ケア
後遺症によるストレスやうつ状態に注意が必要です。本人の気持ちに寄り添い、前向きな声かけを心がけましょう。
✅ 介護サービスの活用
訪問介護、デイサービス、福祉用具のレンタルなど、介護保険制度を活用することで、家族の負担を軽減できます。
脳梗塞後の介護では、身体的なサポートだけでなく、本人の「心のケア」が非常に重要です。突然の発症や後遺症によって、自信を失ったり、社会とのつながりを断たれたように感じる高齢者も少なくありません。こうした心理的な不安に寄り添い、安心感を与える関わり方が回復を支える鍵となります。
たとえば、本人ができることを尊重し、「ありがとう」「助かったよ」といった前向きな言葉をかけることで、自己肯定感が育まれます。介護者がすべてを代行するのではなく、少しでも自分でできることを見つけてもらう工夫が、リハビリへの意欲にもつながります。
また、脳梗塞後は感情の起伏が激しくなることもあります。怒りっぽくなったり、涙もろくなったりすることがありますが、これは脳のダメージによる自然な反応です。介護者は「性格が変わった」と捉えるのではなく、冷静に受け止め、必要に応じて医師や専門職に相談することが大切です。
さらに、家族自身の心身のケアも忘れてはいけません。介護は長期にわたることが多く、介護者の疲労やストレスが蓄積すると、共倒れのリスクも高まります。地域の介護支援サービスや相談窓口を活用し、無理なく続けられる体制を整えることが、本人にも家族にも良い影響をもたらします。
要介護認定とサービス利用の流れ
脳梗塞によって介護が必要になった場合は、要介護認定を受けることで、介護保険サービスを利用できます。
手続きの流れ
- 市区町村の窓口で申請
- 調査員による訪問調査
- 主治医の意見書提出
- 判定結果の通知(要支援1〜要介護5)
- ケアマネジャーとケアプラン作成
- サービス開始(訪問介護・通所リハなど)

身近な人に介護が必要になったときの手続きのすべて
鈩 裕和 (監修)
親が倒れた! どうする?
どこに相談すればいいの?お金は?申請はどうしたらいいの?在宅介護をするには?
そんな介護の不安を一気に解消してくれる1冊です。
見やすく、読みやすい大判サイズ。
まとめ:高齢者の脳梗塞は早期対応と支援が鍵
高齢者の脳梗塞は、突然の発症と後遺症のリスクがある一方で、早期発見・早期治療によって回復の可能性も十分あります。日頃から予兆に注意し、生活習慣を見直すことで予防につながります。
また、脳梗塞後の介護は、本人の尊厳を守りながら、家族の負担を軽減するために、介護保険サービスの活用が不可欠です。医療と介護の両面から支えることで、高齢者がその人らしく暮らせる環境を整えていきましょう。
こちらもおすすめ
「家族介護」のきほん
アラジン(著)
「介護する人」に寄り添う、在宅介護の実用書!
20年以上にわたり、介護をしている家族の相談やサポートを続けているNPO法人の「アラジン」の蓄積された経験や豊富な相談事例をもとに、介護者の暮らしや人生に寄り添った、リアルな介護の乗り切り方を伝授します。
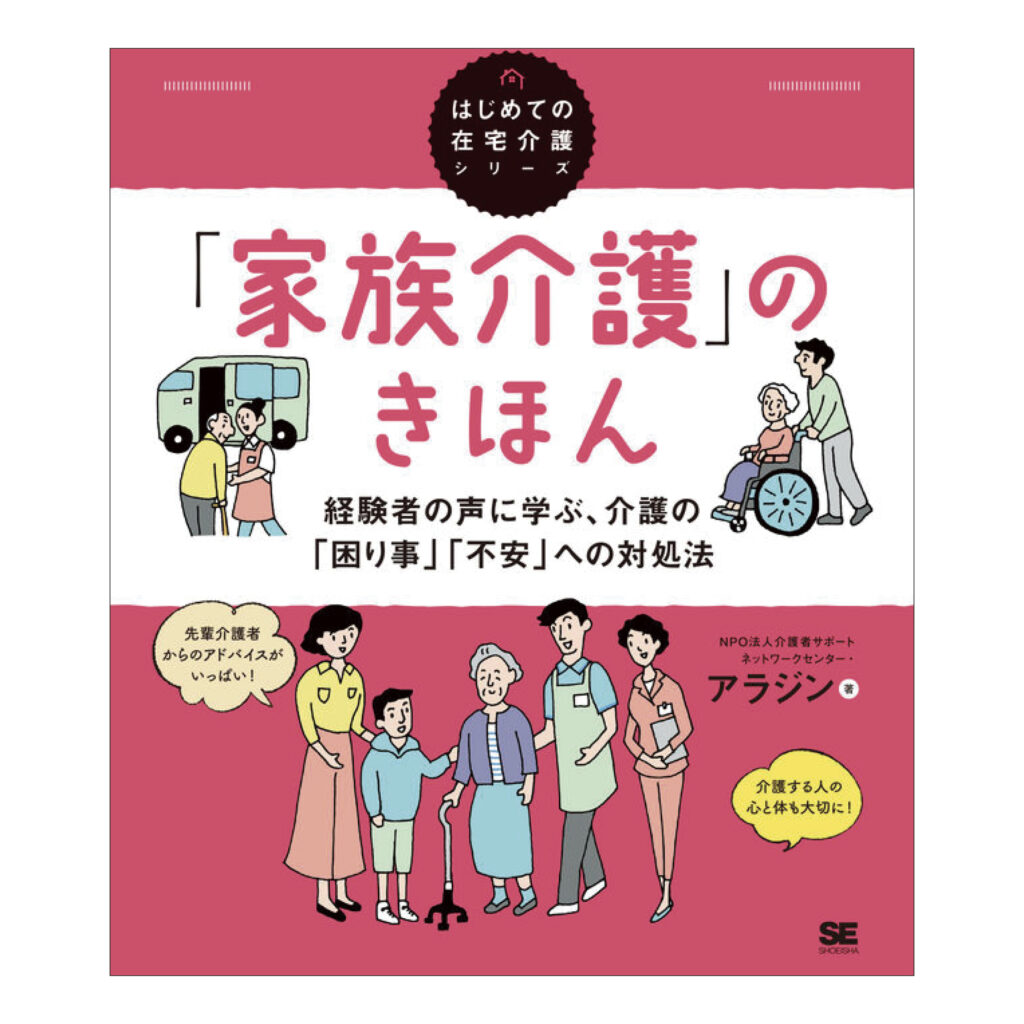
投稿者プロフィール
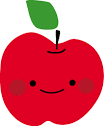
-
5年にわたり祖母の介護を経験。その経験を元に、介護の世界へ。
現在はライターとして介護の記事を中心に執筆中。
最新の投稿
 親の介護2024年12月19日母は精神科病棟へ…認知症の人を精神科で治療するとは?
親の介護2024年12月19日母は精神科病棟へ…認知症の人を精神科で治療するとは?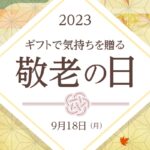 おすすめグッズ・サービス2023年8月21日【2023年】敬老の日のプレゼントにおすすめグッズ特集!
おすすめグッズ・サービス2023年8月21日【2023年】敬老の日のプレゼントにおすすめグッズ特集! おすすめグッズ・サービス2023年6月5日大人用おむつとパッドはどう使う?各メーカーのお試しも可能!
おすすめグッズ・サービス2023年6月5日大人用おむつとパッドはどう使う?各メーカーのお試しも可能! いきいきファミリー2023年5月8日介護あるある漫画|第98話 え、どっち?
いきいきファミリー2023年5月8日介護あるある漫画|第98話 え、どっち?











コメント