親のお金の話は認知症になる前が理想です。親のお金に関する話し合いは、家族にとって非常に敏感な問題ですが、それでも進めなければならない場合もあります。このコラムでは揉めやすい内容でも、スムーズに話せるようなコツとポイントを体験談も踏まえてご紹介します。
親が認知症になる前に、必要な手続きや準備、そして対話の仕方について知りたい方は必見です。
親とお金の話をするタイミングは?

親にお金の話を切り出すタイミングは、「あれ?」が増えてきた時です。
例えば、親が高齢になってきて介護が必要になった場合、介護費用や老人ホームの費用など、大きな出費が必要になります。
「あれ?」と感じるような出来事が増えてきた時に、お金の話をしておけば、本格的な介護の費用についてもスムーズに話を進めることができます。
筆者の場合は、父が一人で預金を下ろそうとした時でした。あんなにしっかりしていた記憶が、口座の暗証番号があやふやな記憶しかなかったのです。
「あれ?〇〇か、△△どっちかのはずなんだけどなぁ」
「次、間違えたらロックされちゃうよ」
金融機関にもよりますが、暗証番号はだいたい3回前後間違えるとロックがかかってしまい、再開するには印鑑や身分証など手続きに手間がかかります。
それからは「お金下ろしたいからついてきて」と言われるようになりました。もちろん、暗証番号も共有しています。暗証番号の再発行が、よほど面倒だったようで、一人では対処できないと本人も不安なんだと思います。
周りの方にも聞いてみると、やはり「あれ?」が増えてきてから一緒に管理もしくは娘様が管理する方が圧倒的に多く見受けられます。
お金の話をする際の揉めないポイント

親にお金の話をすると喧嘩になってしまったり、「まだボケてないバカにするな!」「みんなが自分のお金を狙っている」など、不信感が出る親御さんもいらっしゃるでしょう。
警戒されてしまうんですよね。我が家もそうでした。心を開いてもらうには普段からコミュニケーションの進め方がとっても大切です。
真正面から「管理はコチラでやる」と伝えると衝突する原因にもなります。
本人の気持を尊重する
親のお金ですから、まずは本人の気持ちや考えを尊重してあげましょう。もしも、お金の話で衝突したら、冷静に話し合うことが大切です。
まずは、親の考えや意見を聞き、自分の考えや意見を伝えます。子供本位に話を進めないことが重要です。
家族もこれから始まる介護や、生活費が心配になります。ですが、主導権を子供が握ろうとすれば、反発も生まれます。親御さん本人に「どうしてほしいか?」本人が答えてくれるならそれが一番なんです。
知人の女性は、平日は施設に、週末は要介護5のお母様をご自宅でお世話をされています。施設代金だけでなく、お葬式はどんな規模で、お金もどこから出すのか?すべてお母様と話し合って終活されているそうです。
このように親とお金の話をするのは、簡単なことではありませんが、早めに話し合うことで、将来的な不安を軽減することができます。親を介護する側としては理想的なカタチだと思います。
ですが、そうもいかない場合は、どう対処したらいいのでしょうか?
衝突するなら「例え話」をしてみよう!
お金の話ばかりする親御さんなら、例え話をすることで本人からの反発も抑えられます。
以前、父が転んで、肋骨を骨折したこともありました。
「入院にならなくてよかったなぁ~、あれ?(診察代金の)支払いしたっけ?」
そう言われたときに、こう切り出しました。
「入院した時、費用も全部出してあげたいんだけど、私ひとりじゃ無理なんだ、ごめんね」
「俺の金を使えばいい、〇〇に入ってるから、覚えといて」
お金の場所がわからないと、自分が困ることがあるということを、へりくだって話します。怒り狂って、喧嘩したのがウソのようにあっさりと場所を教えてくれました。
この時は、タイミングよくお金の話になりましたが、普段からは、例え話をしてもいいかもしれません。相手を否定せず「どうすれば父(親)が困らずに済むか」を肯定する表現に変えるのです。
ご近所さんで起きた例え話や、万が一の時に親が困らない様にしておきたいということを、あの手この手で伝えました。このように抵抗があるお金の話は、普段から時間をかけてコミュニケーションをとる必要があります。筆者は2年~3年程かかりました。
また、家族だと角が立ちますが、福祉サービスには、情報共有してくれるものがあります。第三者に介入してもらうのも方法の一つです。家族に興奮しやすい方は、他人には丁寧に接することも多いのです。
自治体のサービスなら、気軽に相談もできますよね。自分の代わりに対処してくれる身近な存在はとても助かります。
福祉課の「日常生活自立支援事業」

役所の福祉課で取り扱うサービスの中に「日常生活自立支援事業」があります。書類や通帳、印鑑などの管理の補助をしてくれます。もちろん、通帳や印鑑の置き場所の情報も共有してくれます。自宅介護者の頼もしい味方です。
「日常生活自立支援事業」とは、日常生活の支援が必要な人が利用できる福祉課の支援サービスです。
例えば、光熱費などの支払いが滞っていたら生命の危険も心配ですよね。このサービスでは、電気料金などの支払いも代行してくれます。
通帳や土地などの重要書類も安全な場所で保管も可能。サービスの利用は有料ですが、介護認定されていれば低額で利用もできます。相談=契約ではないんです。
「まだ認知症ではないから早いかしら……」
なんて思わずに、気軽に相談してみてください。認知症になる前の予備知識として知っていれば、一人で抱え込まなくて済みます。
通帳・印鑑の管理

生活に切り離せないのが「現金管理」です。高齢の方は、通帳と印鑑の場所を決めており、同じ場所に保管している人が殆どです。
ただ、物忘れなどの「あれ?認知症かな?」と感じたら注意が必要です。たとえば、新聞の集金で玄関で支払って、そのままどこに置いたか覚えていない、なんてことも。
通帳と印鑑の管理は、場所だけでも家族が知っていたほうが良いでしょう。そして、できれば印鑑と通帳は別の場所が理想です。
それと、暗証番号が予想できそうなもの(誕生日の記載のある保険証など)も、印鑑通帳と別の場所が安全です。
親の預金が引き出せない!そうなる前にできること
認知症が発覚したら、まず暗証番号は覚えていないでしょう。意外と知られていませんが、金融機関は口座名義人が認知症と知った時点で口座を凍結してしまうので、現金が引き出せなくなります。
親子でも預金は引き出せません。凍結はされていなくても、暗証番号を変更するには、本人からの委任状がないと手続きすらできません。そんな時、口座管理で出来ることの一つに「代理人指名手続き」があります。
「代理人指名手続き」
代理人指名手続きは、事前に口座名義人本人が金融機関で手続きをする必要があります。手間はありますが、代理人になった人にもキャッシュカードが発行されるので、預金管理は便利になります。
口座凍結は、ご本人の資産を守るため、家族といえども簡単に預金を出し入れできなくなるのです。そうなる前に、お金に関する価値観や考え方も話し合い、意見を共有することで、将来的なトラブルを防ぐことができます。
銀行に勤めていた時にこんなこともありました。窓口に来た男性が大声で怒鳴り、机をたたき大騒ぎしています。認知症になった親の預金を引き出そうとしたようですが、即座に凍結されてしまい1円も引き出せなくて暴れていました。
「自分の親なのになんで金をだせないんだ!必要な金なんだよ」
もしかしたら施設などの介護費用だったのかもしれません。ですが、口座を凍結してしまうと、脅されようが、殴られようがお金は引き出せません。皆さんもお気を付けください。
こちらもおすすめ
親の介護をはじめたらお金の話で泣き見てばかり 増補改訂版
「認知症になった親の口座が凍結してしまいお金が引き出せない!」まさにここで書いたことを体験された著者が、「お金で泣きを見ない」ための体験談と裏ワザがギュッと詰まっています。
親のお金問題で困ったら必読の一冊です!
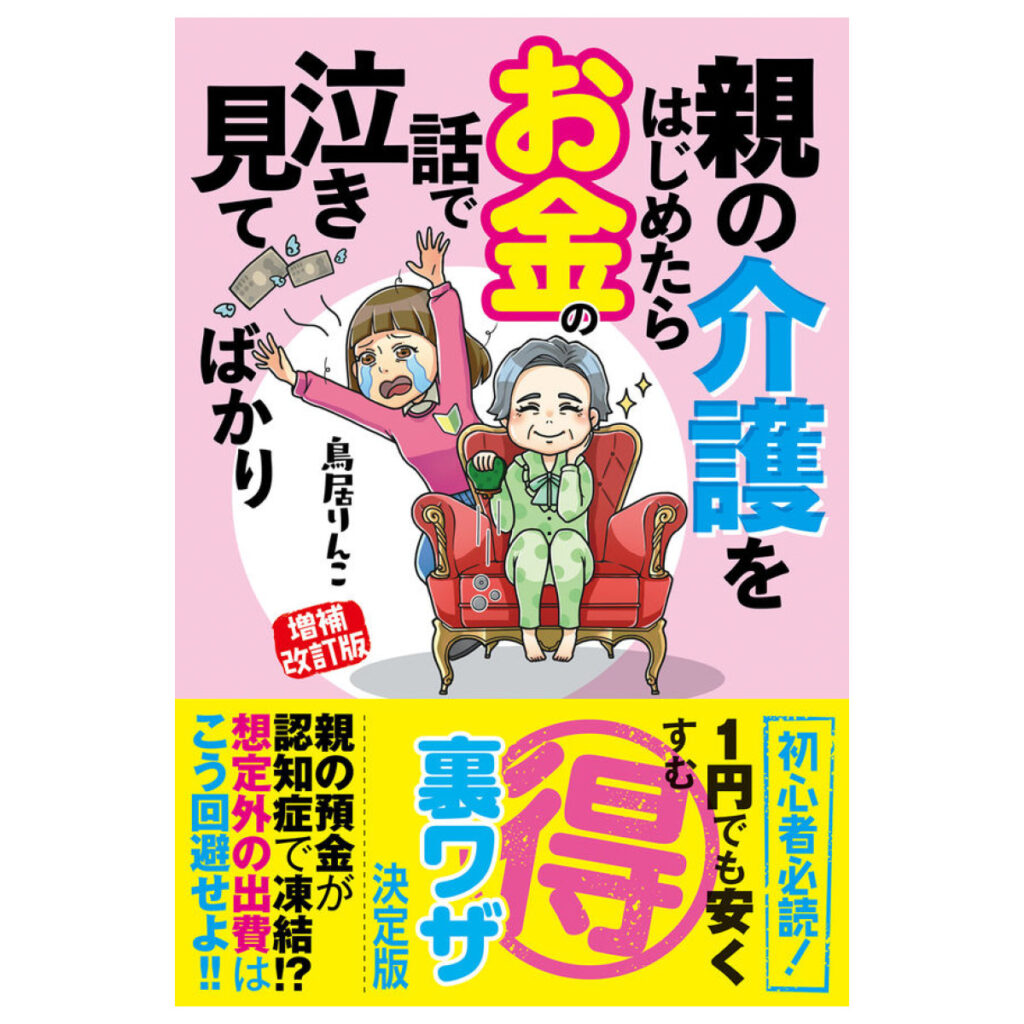
資産の把握

認知症になる前に出来ることの一つに「資産の把握」があります。
「国債なんてもってないよ、国債って何だっけ?」
これは、高齢のご婦人のお客様に実際に言われた言葉です。
娘様が通いで介護されていたので、預金がらみの手続きは無事に済みましたが、誰も把握してない場合は、後々面倒なことになります。
認知症になる前に、親御さんには「資産はどんなものがあって、いくら位なのか?」を、一緒に確認出来たら安心です。
- 利用銀行はいくつあるのか?
- 普通預金なのか定期預金なのか?口座を認識しておく
- 運用用品や年金は年に一度届く報告書なども気にかけておく
- 土地や家の名義は誰なのか?
- 貸金庫があればそのカギの場所はどこか?
これらも、すんなり教えてくれればいいのですが、そうもいかない場合は、やはり時間をかけてさりげなく聞き出してみましょう。
土地や家の名義などは、役所に行けば登記簿も取り寄せられます。それが無理なら「日常生活自立支援事業」などの専門サービスをうまく利用してみましょう。
ご家族には話さなくても、公的機関の人には案外、素直に話すケースもあります。
誰が何を管理するのか決めておく
資産といっても多様にわたります。
・家などの不動産
・口座
・自動車
・タンス貯金などの現金
兄弟姉妹で協力可能なら、分担するのが理想です。1人ですべての管理はなかなか骨が折れるものです。銀行口座は複数お持ちの方がほとんどですし、持ち家があれば、毎年税金の支払いも出てきます。
銀行の通帳やカードは長女、不動産関係は長男など、大まかでも「誰が何を管理するのか」決めておくと、いざというときにスムーズに対処できます。
専門家や専門サービスを利用

自治体の福祉サービス以外でも、認知症になる前に出来ることはあります。
親御さんの希望を聞きながら、その家庭に合った制度も探してみましょう。
成年後見制度
「成年後見制度」とは国が管轄している制度のことです。
認知症や精神障害など、一人で判断するには不安な場合に、手続きのお手伝いをしてくれる「後見人」という助っ人を選んで支援してくれる制度です。
後見人の選出または監督者を、裁判所が行います。
例えば、精神障害がある人が詐欺被害にあった場合、選ばれた助っ人(後見人)が解約等の手続きを行ってくれます。制度には、選ばれる助っ人(後見人)によって2種類あります。
「任意後見制度」
ご本人が希望する人に支援してもらうケース。
ただし、家庭裁判所がきめた任意後見監督人(第三者の監督する人)が選任されて成立します。
「法定後見制度」
当人の病状や環境など、どのような状況で、どんな支援が必要なのか?
助っ人(後見人)は裁判所によって決定されます。
その為、親族以外でも弁護士や福祉士などの専門家が選ばれることもあれば、福祉関係の公益な法人が選ばれることもあります。
忙しくて認知症の親の元までいけない方や、ご自身の親御さんの状況などによっては、裁判所選出の助っ人後見人なら、安心してお任せできます。
ご家庭の状況などによって、候補の一つとして考えてもいいでしょう。
厚生労働省「成年後見はやわかり」
https://guardianship.mhlw.go.jp/
信託制度
専門家にお任せする方法で「信託制度」があります。これは漢字のまま信じて託すものです。信託の免許を持つ金融機関などが請け負います。信託は、ある程度資産があるなら親族の手間も減るので便利です。
家族信託
認知症などで管理能力がなくなった場合、本人の代わりに家族が管理、手続きができます。
事業継承などがある場合などは、継承する親族がそのまま管理できます。
資産承継信託
家族信託と違い、信託銀行が資産を管理してくれるものです。
あらかじめ資産の相続先を決めておけば、金融機関が代わりに処理してくれます。
認知症になる前に信託銀行に託しておくことで余計な相続争いも避けられます。その為、「事前に誰に何を託すのか」決めておく必要があります。
逆にいうと、決めておきさえすれば、信託のプロが代行して手続きをしてくれるので、乱雑な手続きもさほどなく安心できます。
例えば、残された家族に年金代わりに定期的に預金を渡すことも可能です。
まとめ

親とお金の話をするタイミングは、「あれ?」が増えてきた時がいいでしょう。スムーズに話せるなら、どんな資産があって、誰が管理するのか決めておく。
衝突する、もしくはすんなり話し出せない時には、例え話をしたり、第三者にも相談したり、時間をかけてコミニケーションを取ってみてください。
認知症がきっかけで考える「親の老後」お金の問題もきれいごとでは済みませんよね。
こちらの一冊もおすすめです。
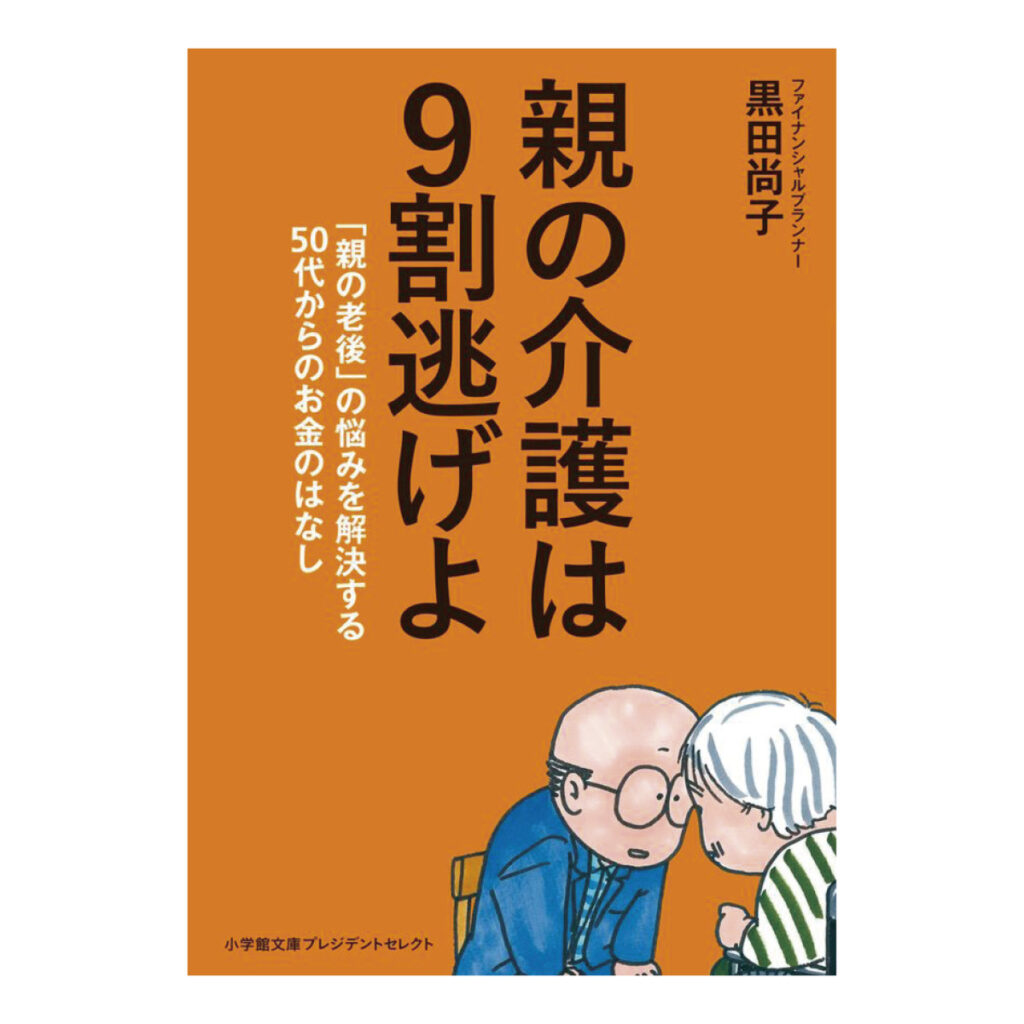
親の介護は9割逃げよ
親を介護する世代へ向けた、お金の話。
資産や家計の管理、葬儀代金など、親の老後の「お金」について、あらゆる角度からの知識を教えてくれます。
サブタイトルは「50代からのお金のはなし」とありますが、世代関係なく親のお金に関する幅広い内容となっています。家に常備しておきたい一冊です。
また、私たちキャプスには介護の有識者や、看護師の有資格者など「介護の専門家」が多数在籍しています。公式LINEでは、それぞれの専門家たちが、出来る限り質問にお答えいたします。もちろん無料です。
「親の介護が限界、どうしたらいいの」「聞いてみてもいいのかな」
怖がらず、介護の悩みの第一歩は相談からです。そんな方も是非、公式LINEをご登録くださいませ。
さらに、キャプスには匿名の掲示板があります。名前は公開されません。辛い気持ち、イライラした日……。日々の愚痴や思いをつぶやいていいんです。
あなたに共感してくれる人もきっといるはずです。辛い思いをしているかもしれない、そんな貴方のために作りました。遠慮せずに是非、利用してみてくださいね。
投稿者プロフィール

-
元銀行員。40代副業ライター。
得意分野は介護と金融
時々犬(愛犬家・証券外務員2種保有)
脳卒中による半身麻痺、
大腸がんなど病気のオンパレードで
認知症状も増えてきた父親の介護を
10年以上やっています。
モットーは「毎日明るく」マンガと小説好き。
介護ストレスと上手に付き合っています。


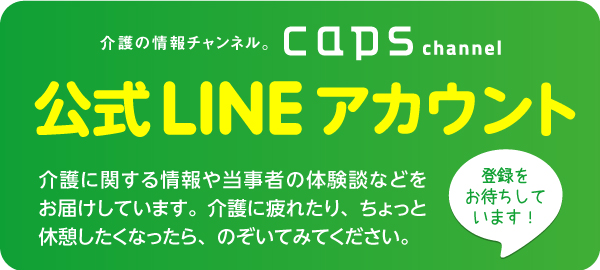
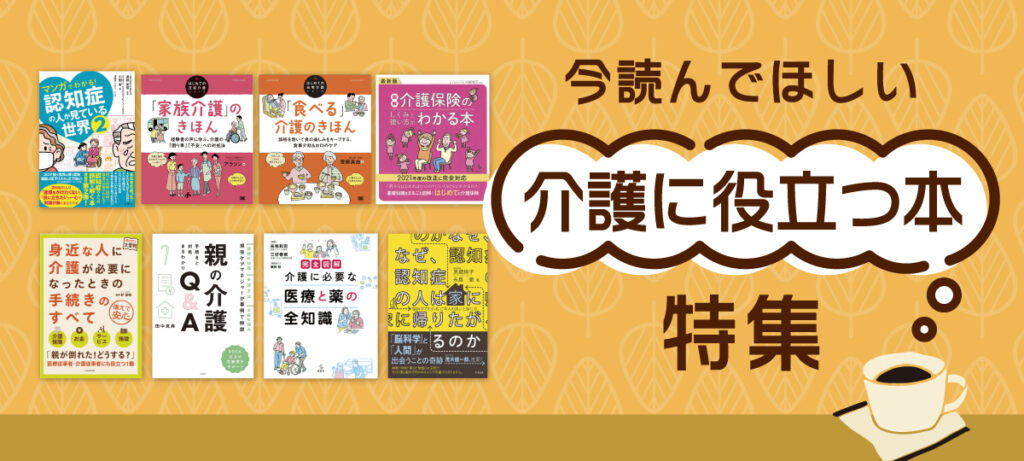



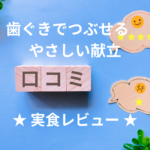










コメント