親の介護が必要になったとき、兄弟姉妹がいれば分担できることも、一人っ子の場合はすべて自分にのしかかります。 「仕事を続けながら介護できるのか」「お金が足りない」「誰にも相談できない」——そんな不安や孤独を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、「親の介護 一人っ子」という視点から、実際に起こりがちな悩みとその乗り越え方、使える制度や支援の活用法までをわかりやすく紹介します。
一人っ子が親の介護で直面する主な悩み
一人っ子が親の介護で直面する主な悩みは以下のとおりです。
1. 介護の全責任を一人で背負う
- 通院の付き添い、食事・排泄の介助、服薬管理など、日常のすべてを担うことに。
- 判断もすべて自分で行うため、精神的な負担が大きい。
2. 経済的な不安
- 介護のために仕事を減らしたり辞めたりすることで、収入が減少。
- 親の年金だけでは足りず、自分の貯金を切り崩すケースも。
3. 孤独と相談相手の不在
- 兄弟姉妹がいないため、悩みを共有できる相手がいない。
- 周囲に介護経験者が少なく、話しても理解されにくい。
4. 介護と自分の生活の両立が困難
- 自分の時間が取れず、趣味や人間関係が希薄になる。
- 心身ともに疲弊し、うつ状態に陥ることも。
さらに、一人っ子ならではのプレッシャーとして、「親の介護を誰にも代わってもらえない」という孤独感があります。兄弟がいれば、物理的な分担だけでなく、精神的な支えにもなりますが、一人っ子の場合はその選択肢がありません。
また、親が複数人(両親や祖父母)同時に介護を必要とするケースでは、負担は倍以上に膨らみます。介護だけでなく、医療手続きや金銭管理、施設選びなど、すべての判断を一人で背負うことになり、「間違えたらどうしよう」「誰かに相談したいけど誰もいない」と不安が募ります。
社会的にも、一人っ子の介護は見えにくい問題です。周囲からは「親思いで偉いね」と言われる一方で、実際には仕事との両立や経済的な限界に苦しんでいる人も多く、理解されにくい現実があります。
そしてもうひとつ、一人っ子が抱えがちな悩みが「自分の老後はどうなるのか」という不安です。親の介護に人生の時間と資源を費やすことで、自分の将来設計が後回しになり、「このまま誰にも頼れないまま年を取るのでは」と感じる人も少なくありません。
実例:母と祖母のW介護を担った一人っ子の体験

筆者は32歳の一人っ子。母と祖母の介護を同時に担うことになり、在宅勤務に切り替えて対応。 祖母は認知症と大腸がんを併発し、母も肺炎で入院。 介護サービスを活用しながらも、食事作り・排泄介助・服薬管理・仕事をすべて一人でこなす日々に限界を感じていました。
一人っ子が親の介護で使える支援制度
そんな筆者も本当に助けられた支援制度をご紹介します。
介護保険制度
- 要介護認定を受けることで、訪問介護・デイサービス・福祉用具レンタルなどが1〜3割負担で利用可能。
高額介護サービス費制度
- 月額の自己負担が一定額を超えた場合、超過分が払い戻される。
ショートステイ
- 一時的に施設に預けることで、介護者が休息を取れる。
- 1泊2日で約1万円前後。親の年金でまかなえるケースも。
地域包括支援センター
- 介護の相談、ケアプランの作成、家族間の調整などを無料で支援。
ケアマネジャーの活用
小さな悩みでも相談でき、精神的な支えにもなる。介護サービスの選定や調整をしてくれる専門職。
一人っ子は、「親の介護を誰にも代わってもらえない」という孤独感があります。兄弟がいれば、物理的な分担だけでなく、精神的な支えにもなりますが、一人っ子の場合はその選択肢がありません。
また、親が複数人(両親や祖父母)同時に介護を必要とするケースでは、負担は倍以上に膨らみます。介護だけでなく、医療手続きや金銭管理、施設選びなど、すべての判断を一人で背負うことになり、「間違えたらどうしよう」「誰かに相談したいけど誰もいない」と不安が募ります。
社会的にも、一人っ子の介護は見えにくい問題です。周囲からは「親思いで偉いね」と言われる一方で、実際には仕事との両立や経済的な限界に苦しんでいる人も多く、理解されにくい現実があります。
そしてもうひとつ、一人っ子が抱えがちな悩みが「自分の老後はどうなるのか」という不安です。親の介護に人生の時間と資源を費やすことで、自分の将来設計が後回しになり、「このまま誰にも頼れないまま年を取るのでは」と感じる人も少なくありません。
一人っ子が介護を乗り越えるための工夫

在宅介護は、体力に加えて精神的な負担もかかります。ときには、疲れからイライラしてしまったり、逃げ出したくなることもあるのは自然なこと。
つらくなったときには、心ゆるせる友人に話す、介護サービスを活用する、ケアマネジャーに相談をするなど、まずは自分のケアをすると、また力が湧きはじめます。
介護が必要な状態になった親も、老いていく体や自分でもコントロールできない症状に混乱したり、反発したくなったりすることもあるでしょう。
そんな親の状況や苦しみがわかっていても、自分を育ててくれた親の弱った姿や見たこともない言動を目の当たりにすると、ショックが大きくて、逃げ出したくなってしまう。それは大切な家族だからこそではないでしょうか。
それでも介護を続けなければならい。そんなあなたに伝えたいことがあります。
完璧を目指さない
- すべてを自分でこなそうとすると、心身が持ちません。
- 「できることだけやる」「頼れるところは頼る」意識が大切。
自分の時間を意識的に確保する
- 5分でもいいから、好きなことをする時間を作る。
- リフレッシュすることで、介護への向き合い方が変わる。
感情を吐き出す場を持つ
「一人っ子でも、一人ではない」と感じられる場を見つけることが重要。
ケアマネジャーや地域の介護者カフェなどで、気持ちを話すだけでも心が軽くなります。
介護に疲れたあなた読んで欲しい1冊
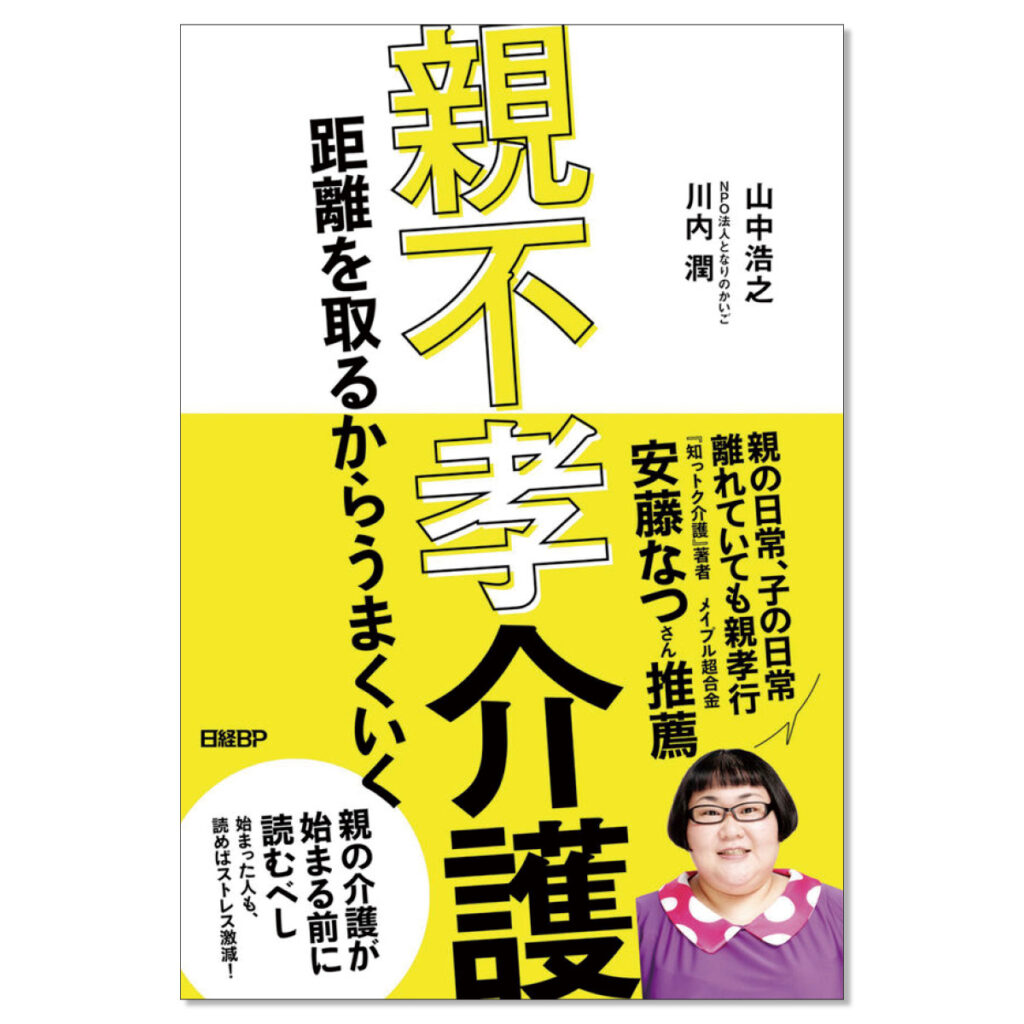
親不孝介護 距離を取るからうまくいく
「長男だから、親を引き取るか実家に帰らないと」「家族全員で、親を支えてあげないと」「親のリハビリ、本人のために頑張らせないと」「親が施設に入ったら、せめて、まめに顔を見せに行かないと」そんなものは必要なし!
「親と距離を取るから、介護はうまくいく」。
一見、親不孝と思われそうなスタンスが、介護する側の会社員や家族を、そしてなにより介護される親をラクにしていきます。
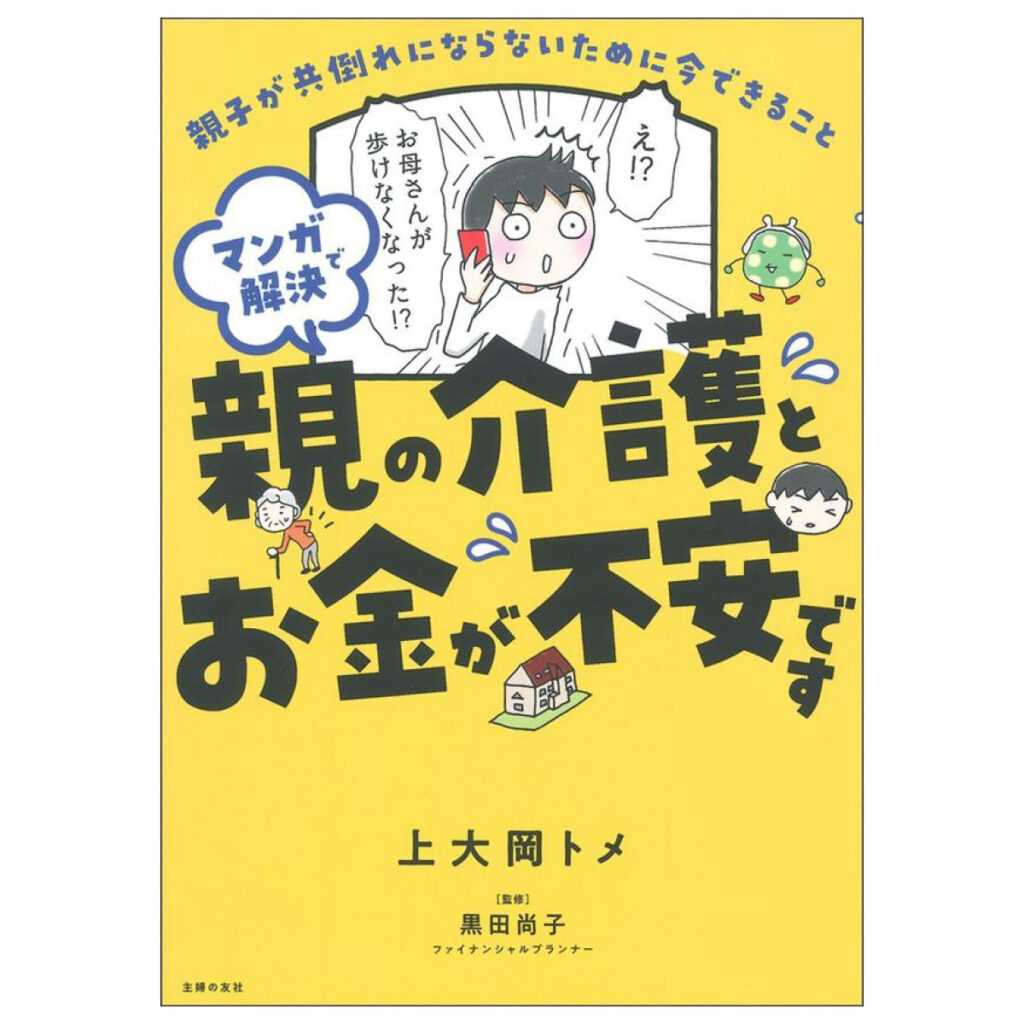
マンガで解決 親の介護とお金が不安です
「お母さんとお父さん、なんか老けた?」と思ったら、今すぐ読むべき1冊。
「いま、親に何かあったら、どうしよう?」超高齢社会で長生きしても、最期の数年は不健康である場合が多い。
今何をしたらいいのかわからないけれど、漠然と不安を持っている方に、「親の介護とお金」の超入門編。
まとめ:親の介護を一人っ子が担うときこそ、支援と制度を味方に
親の介護を一人で担うという状況は、責任も負担も大きく、孤独を感じやすいものです。 しかし、制度や支援を活用することで、介護の質も自分の生活も守ることができます。
完璧を目指さず、頼れるところには頼る。 「一人で頑張る」から「一人でも支えられる」へ——その一歩を踏み出すことで、介護は少しずつラクになります。












コメント