介護をしていると、「親がデイサービスに行きたがらない」「何度勧めても断られる」といった悩みに直面することがあります。介護者としては、少しでも自分の時間を確保したい、親の心身のリフレッシュにつなげたいという思いがある一方で、本人が強く拒否する場合、どう対応すればよいのか迷ってしまいます。
この記事では、「親がデイサービスを嫌がる」という視点から、嫌がる理由の背景と、納得してもらうための具体的な対応策を解説します。
なぜ親はデイサービスを嫌がるのか?主な理由と心理

高齢者がデイサービスを嫌がる理由は、単なるわがままではなく、さまざまな心理的・環境的な要因が絡んでいます。
✅ 知らない場所・人への不安
初めての場所に行くことや、知らない人と過ごすことに対して不安を感じる高齢者は多くいます。特に認知症の初期段階では、環境の変化に敏感になり、混乱や拒否反応が強く出ることがあります。
✅ 自分には必要ないという思い
「まだ元気だから」「介護なんて必要ない」といった自己認識がある場合、デイサービスの利用を“弱者の証”のように感じてしまうことがあります。
✅ 過去の嫌な経験
以前に利用した施設での不快な体験(スタッフとの相性、プログラムが合わなかったなど)があると、「また嫌な思いをするかもしれない」と考えて拒否することがあります。
✅ プログラムが面白くない・合わない
レクリエーションや活動内容が本人の興味と合っていない場合、「退屈」「子ども扱いされている」と感じてしまい、行きたくないという気持ちにつながります。
✅ スタッフの言葉遣いや対応
一部の施設では、利用者に対して子ども扱いのような言葉遣いや態度が見られることがあります。高齢者は人生経験が豊富であり、尊厳を大切にした対応が求められます。
デイサービスを嫌がる親への対応策
親がデイサービスを嫌がるときに大切なのは、本人の「嫌がる気持ち」を否定せず、まず受け止める姿勢です。「どうしてそんなに嫌がるの?」と問い詰めるのではなく、「行きたくない気持ち、わかるよ」と共感を示すことで、心の壁が少しずつほぐれていきます。
また、本人が「選べる立場」であることを意識させるのも効果的です。施設や曜日、参加するプログラムなどを一緒に選ぶことで、「自分で決めた」という納得感が生まれ、拒否感が和らぐことがあります。
家族以外の第三者からの働きかけも有効です。ケアマネジャーやかかりつけ医、信頼している友人などから「行ってみると意外と楽しいよ」といった言葉をもらうことで、本人の気持ちが動くことがあります。
さらに、初回利用の前後には「どうだった?」「疲れなかった?」など、感想を聞きながらポジティブな体験を一緒に振り返ることが大切です。小さな成功体験を積み重ねることで、次回への抵抗感が減っていきます。
✅ 理由を丁寧に聞く
「なぜ行きたくないのか」を具体的に聞き出すことが第一歩です。過去の経験や不安、体調、気持ちなど、本人の言葉に耳を傾けることで、解決の糸口が見えてきます。
✅ 自分の気持ちも伝える
介護者としての負担や、少し休みたいという気持ちを率直に伝えることで、親も「協力しよう」という気持ちになりやすくなります。
✅ 体験利用から始める
いきなり定期利用を勧めるのではなく、まずは1日だけの体験利用を提案してみましょう。「見学だけでも」「お風呂だけでも」といった柔らかいアプローチが効果的です。
✅ 興味のあるプログラムを選ぶ
本人の趣味や関心に合ったプログラムがある施設を選ぶことで、「行ってみようかな」と思えるきっかけになります。
✅ 相性の良い施設を探す
施設によって雰囲気やスタッフの対応は大きく異なります。複数の施設を比較し、本人に合った場所を見つけることが、継続的な利用につながります。
デイサービスのメリットを伝えるには?

親が納得して通うようになるためには、デイサービスのメリットをわかりやすく伝えることが重要です。
- 人との交流ができる:孤立を防ぎ、会話や笑顔が増える
- 生活リズムが整う:外出することで昼夜逆転を防げる
- リハビリや運動ができる:体力維持や転倒予防につながる
- 介護者の負担軽減:介護者が休息できることで、より良い関係が築ける
これらのメリットを、本人の生活や価値観に照らし合わせて伝えることで、納得感が高まります。
どうしても嫌がる場合の選択肢
どうしてもデイサービスを嫌がる場合は、無理に通わせようとするのではなく、本人のペースに合わせた代替手段を探ることが大切です。介護者の「休みたい」「安心して任せたい」という気持ちと、本人の「知らない場所は不安」「人と関わるのが億劫」という気持ちの両方を尊重する必要があります。
たとえば、地域包括支援センターや自治体が開催する少人数制の交流会や、趣味活動を中心としたサロンなどは、デイサービスよりも気軽に参加できる場として活用できます。本人が「行ってみたい」と思えるテーマ(音楽、園芸、手芸など)を選ぶことで、抵抗感が薄れることもあります。
また、在宅での支援を充実させることも選択肢のひとつです。訪問介護や訪問リハビリ、看護師による定期訪問などを組み合わせることで、外出せずに必要なケアを受けることができます。本人が安心できる自宅という環境で支援を受けられることは、精神的な安定にもつながります。
さらに、家族や介護者が一時的に介護から離れられる「レスパイトケア(介護者の休息支援)」の制度を利用することも検討してみましょう。本人がデイサービスを使わなくても、介護者が心身を休める方法は他にもあります。
- 訪問介護や訪問リハビリの活用
- 地域のサロンや交流会への参加
- 家族や知人との外出機会を増やす
- 在宅でできる趣味活動の支援
本人のペースを尊重しながら、少しずつ外とのつながりを持てるように工夫することが大切です。
「家族介護」のきほん
アラジン(著)
「介護する人」に寄り添う、在宅介護の実用書!
20年以上にわたり、介護をしている家族の相談やサポートを続けているNPO法人の「アラジン」の蓄積された経験や豊富な相談事例をもとに、介護者の暮らしや人生に寄り添った、リアルな介護の乗り切り方を伝授します。
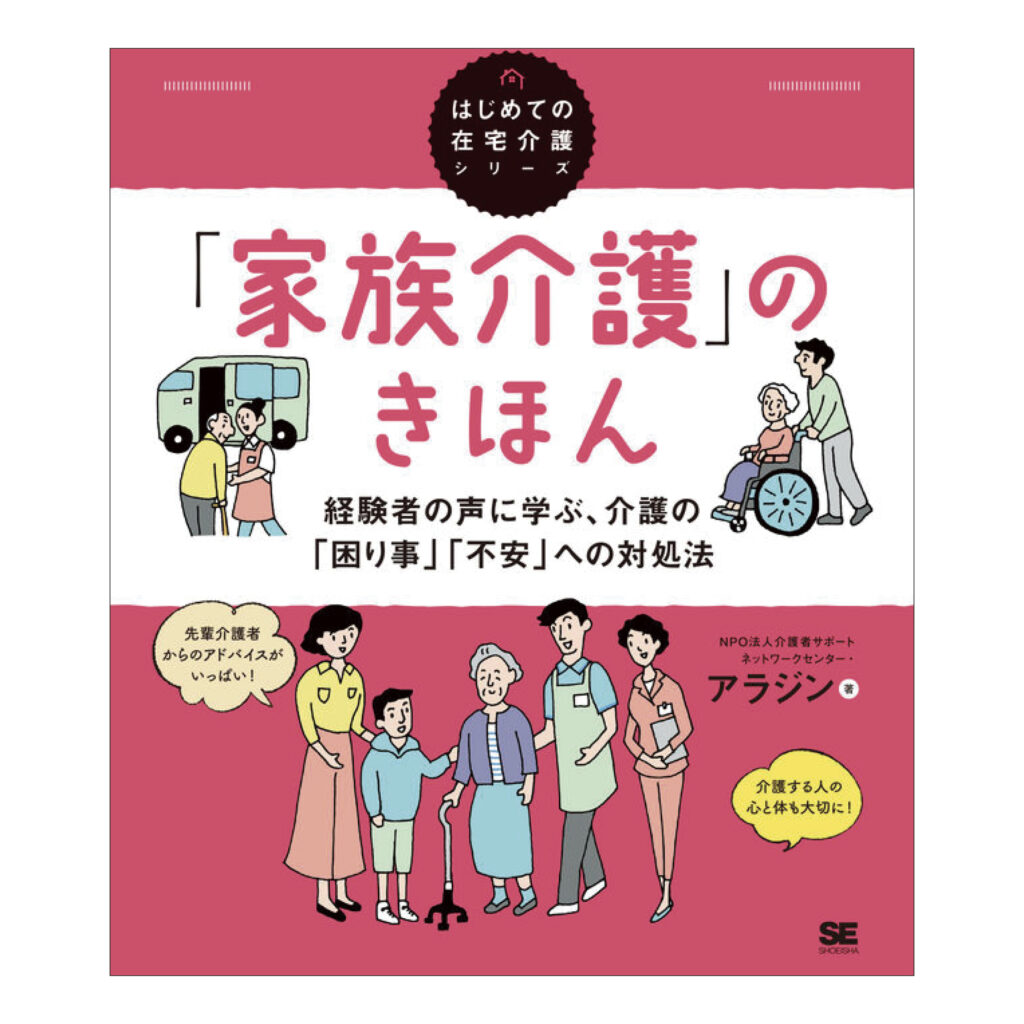
まとめ:嫌がる気持ちの奥にある「理由」に寄り添う
デイサービスに通うのを嫌がる親にの悩みというのは、多くの介護者が経験するものです。しかし、嫌がる理由には必ず背景があります。本人の気持ちを理解し、尊重しながら、少しずつ納得してもらえるような関わり方をすることで、状況は変わっていきます。
介護は一人で抱え込むものではありません。デイサービスは、本人の生活の質を高めるだけでなく、介護者の心身の健康を守るためにも大切な選択肢です。焦らず、寄り添いながら、最適な形を一緒に探していきましょう。
こちらもおすすめ
親の介護 手続きと対処まるわかりQ&A
田中克典 (著)
介護の悩みをスッキリ解決!
親や身内が病気や怪我で倒れたり、認知症になったとき、その家族には突如として介護の負担( 生活の変化・精神的負担・お金)がのしかかります。
本書では、最低限知っておきたい介護保険制度の申請から、施設選び、高齢期の親との付き合い方など、多くの人が直面する悩みを、相談の多い64テーマに絞って紹介。
400人以上の高齢者をサポートしてきた現役ケアマネジャーが事例をもとに解説しています。
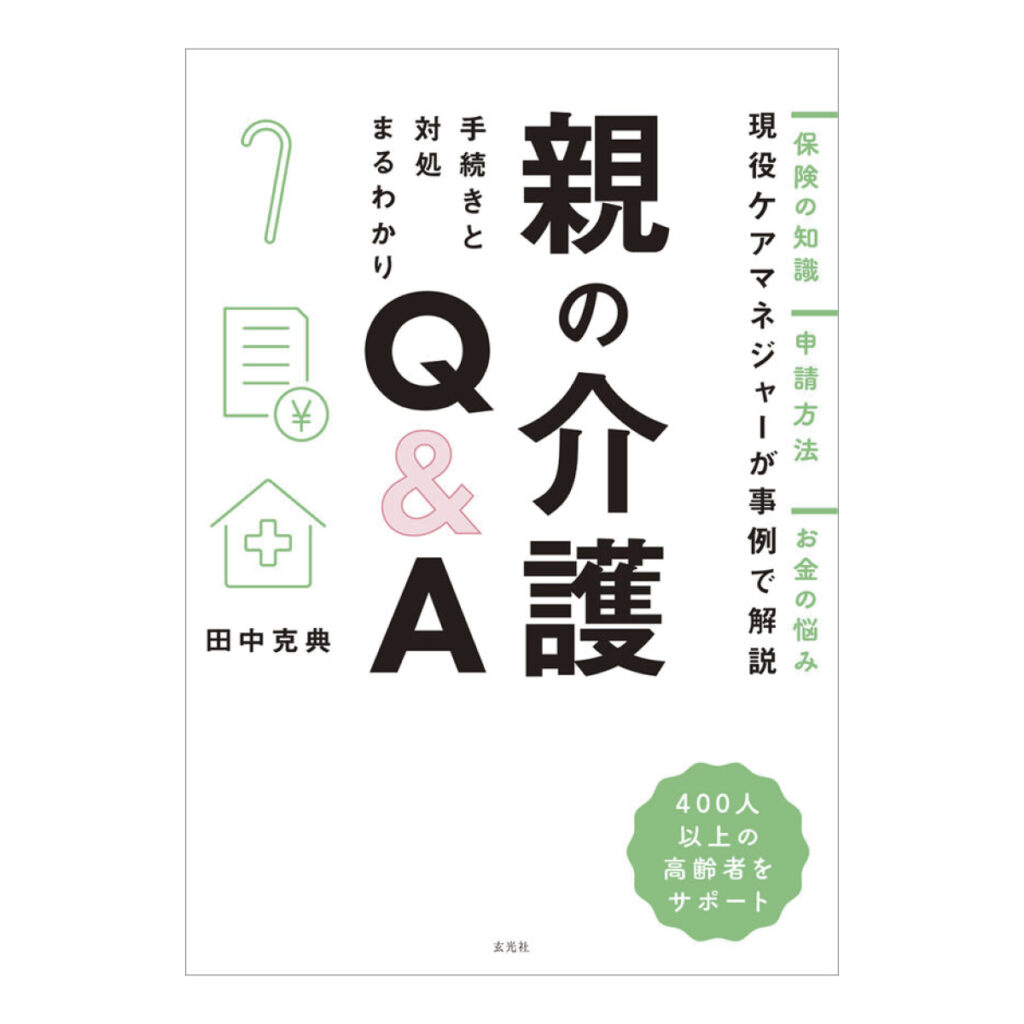
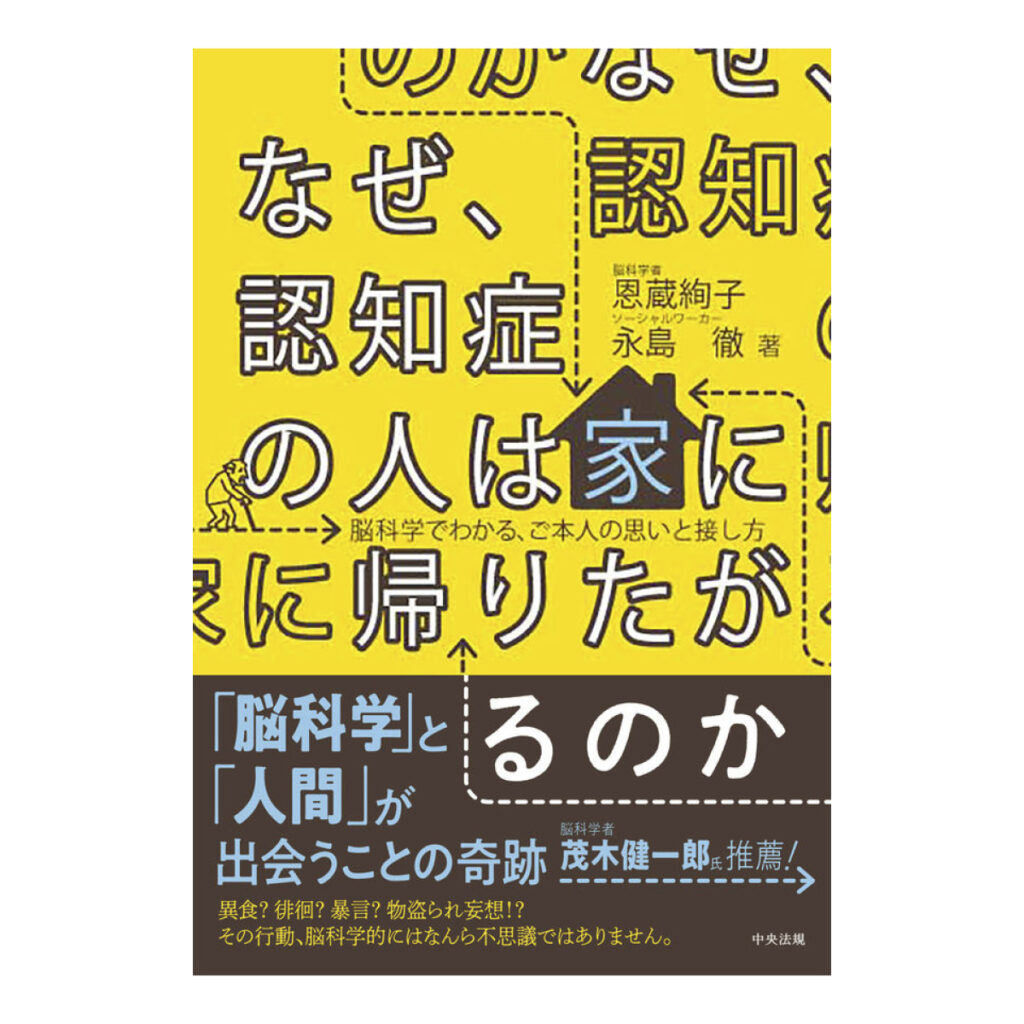
なぜ、認知症の人は家に帰りたがるのか 恩蔵 絢子/ 永島 徹 (著)
「なぜ、同じことを何度も聞いてくるのか」「なぜ、受診の話をすると怒り出すのか」「なぜ、同じものをいくつも買ってしまうのか」
家族や介護者が抱く認知症の人に対する「なぜ?」「どうして?」はたくさん。
しかし、脳科学の視点からみれば、ご本人の行動の理由は説明がつく真っ当なものばかり。
家族や介護者が「なぜ?」と思う認知症の人の行動を、34の事例で取り上げ、その理由を脳科学で説明しています。
投稿者プロフィール

- 広島県在住。Webライター。海外で13年間生活し帰国。日本ではIT関係の仕事でコンサルティング等で企業のサポートを行なっている。
最新の投稿
 介護とお金2023年1月19日在宅介護で利用できる補助金や給付金はあるの?お金の心配を最小限にする知識
介護とお金2023年1月19日在宅介護で利用できる補助金や給付金はあるの?お金の心配を最小限にする知識 介護の悩み2023年1月19日親がデイサービスを嫌がる理由とは?納得してもらうための対応策と施設選びのポイント
介護の悩み2023年1月19日親がデイサービスを嫌がる理由とは?納得してもらうための対応策と施設選びのポイント 介護の豆知識2023年1月19日家で介護をするのに資格は必要?
介護の豆知識2023年1月19日家で介護をするのに資格は必要? 介護の悩み2023年1月19日義理の親の介護は義務でしょうか?
介護の悩み2023年1月19日義理の親の介護は義務でしょうか?











コメント