認知症は、誰でも発症する可能性のある病気ですが、家族が認知症になると、介護をする側の精神的負担はとても大きなものになります。
認知症の家族を自宅で介護するようになると、毎日が介護に明け暮れてしまう可能性があります。上手に介護保険や近所の人のサポート、公的機関の支援を受けることが必要です。
ここでは、認知症の母親を在宅で介護し、最終的に施設入所になった娘さんたちの話から「認知症の家族介護」について考えていきたいと思います。
認知症の家族を介護するある家庭のケース

今回紹介する家族は、筆者がケアマネ―ジャーとして対応した一家です。
認知症の母と精神疾患のある父、うつ病の姉、結婚して近所に住む妹の4人です。妹さんとそのご主人は仕事があり、家のことはうつ病のお姉さんが一手に引き受けていました。お姉さんは車の運転ができなかったので、妹さんが受診などの補助をしていました。
そんな中、2~3か月ほど前からお母さんの歩行が不安定になり、転びやすくなってきました。一日中ぼんやりしていて物忘れや無関心な様子も多くなりました。また、トイレの失敗も多くなってきました。
病気が治ったら元通りになると思っていた
姉:その時母はまだ75歳、父は77歳だったんです。病院に連れて行ったら「『水頭症』です。」と言われました。治療をして良くなればまた元の生活が戻ると思いました。
妹:歩き方も変だったし、一日中ぼーっとしていて喋ったり笑ったりすることが段々少なくなっていきました。父は我関せずだし、ともかく姉と相談して入院して手術をしようと決心しました。お医者さんも歩行障害は良くなるはずだと言われたので。
水頭症とは、主に70~80代に多く発症し、脳に脳脊髄液が必要以上に脳室にたまって脳を圧迫する病気です。特に歩行障害と認知障害、排尿障害の3つの症状が現れます。多くは、アルツハイマー病などほかの病気を併発していますが、手術によって歩行障害は緩和されることも多いと言われています。
姉:水頭症の手術は無事成功し、リハビリで歩行は可能になりましたが、食事や排せつ、コミュニケーション、すべてに介助が必要な状態でした。
「家に連れて帰る」と決めたけれど
姉:医療的ケアは必要ないので、入院の継続はできませんでした。かといってすぐに施設に入れる決断もできなかった。私も病気だし、父も介護ができるような人じゃないけど「自分の親だし、何とかなる」と思っていました。妹も近くに居たし。
妹:私は大丈夫なのかなあ、くらいの不安はありました。姉も父も安定した精神状態が続かないし。でも姉が出来るって言うんで「まあ、やってみよう」と賛成したんです。でも、ここから大変な毎日が始まりました。
在宅介護のスタート
私はケアマネージャーとして、まず、お母さんの介護度の区分変更の申請(本人の状態が変化し、これまでの要介護度では支障が出てしまう場合に、次の更新を待たずに認定調査を行うこと)をして在宅介護のチームを増やし、家庭の状況からなるべく同居家族に重い負担がかからないように計画を立てました。
当初、日中の食事と排泄の介助は訪問介護、入浴はデイサービスとしていましたが、意思の疎通が難しいことから介助を嫌がられることも多く、特に入浴介助は噛みつく、引っ搔くなどの拒否行動があり、介助に非常に時間がかかりました。結果、デイサービスはお試しの利用だけで終了せざるを得ませんでした。
デイサービスでの入浴ができなくなり、訪問介護のヘルパーさんと、自宅のお風呂で介助をすることにしました。ヘルパーが2人付く「二人介助」だと費用と点数がかさむため、1人のヘルパーと、2人の娘さんでなんとか力を合わせて行いました。体力のいる介助でしたが、部分浴や着衣シャワー、ドライシャンプーなど、安全に配慮し、娘さんの声掛けと支援で何とかやり続けることができました。
デイサービスが利用できなくなったため、1泊2日の短期入所を月3~4回利用することで、介護者の休息を確保することにしました。短期入所を利用する頃には、車に乗って移動することや介助への抵抗が徐々に減っていたため、受け入れてもらうことができたのです。
しかし、最大の問題点は「徘徊」でした。
姉:お風呂も大変でしたが、一番大変だったのは、母が外に出て行ってしまうことでした。歩行が可能になったことでどんどん歩くんです。玄関の鍵の開け方は覚えていたのか、鍵も開けて出て行く。玄関の門や塀も高く開けにくくしたんですが、なぜか開けられる…。
二重ロックにしたり、GPSを使ったり、民生委員さんや近所の警察、各介護事業所にも予防線を張ったりと手を尽くしましたが、なかなかお母さんの徘徊を止めることができませんでした。
母を見かけませんでしたか?

姉:母が家にいないと分かった時には、いつもゾッとしました。どこで死んでるかわからんと思ったからです。私も朝や夕方は調子が悪い時が多く、そんな時は布団から出られません。父がいつも台所にいるんですが、「どこに行くとや~」と声をかけるだけで普通に出してしまいます。そんな時はいつも妹に連絡して「お母さんが出て行った、探して!」とSOSを出すんです。
妹:いつそれが起こるのか分らないので、いつも臨戦態勢でした。昼も夜も。朝から出て行って夕方まで見つからなかった時は、姉と私と主人とで警察や消防署、近所のスーパーから公民館まで「母を見かけませんでしたか?」と尋ね歩きました。
訪問介護のヘルパーさんも短期入所の介護職員さんも何度探し回ってくれたか分かりません。本当にこんなこと言っちゃだめだと分かっているんですが、「もう、お願いだから死んでくれ」と何度思ったかわからないです。
その時期には、私から施設に入所の申し込みの話を何度もしていました。それでもお姉さんは決心がつきませんでした。両親をバラバラにしたくないとお姉さんは話しました。介護のストレスから、すでに姉妹の関係も危うい状態だったため、「お母さんのためでもあります。それとあなたたち姉妹のためです。もう限界ですよ。」とお伝えしました。その言葉に「少し考えます。」と暗い顔で答えたお姉さんでした。
お母さん、もう無理だよ
そんな状態で約1年。お姉さんやお父さんの病状も徐々に悪化していきました。特にお姉さんは、うつ病で寝込んでしまえば2~3日は起きられないという状態となり、その間の介護は妹さんに任せ切りとなってしまいました。妹さんは仕事もパートに変更し、自分の家のことはご主人にお願いし、実家と家を往復する毎日。日中は介護保険サービスが入っても夜間は泊まり込まないと無理でした。
妹:そんなある日の明け方、「お母さんがいない!」と姉が叫ぶ声で目が覚めました。「またか、もういい加減にしてよ」と正直思いました。
姉:いつもと同じようにケアマネージャーや介護事業所に連絡、警察・消防に連絡、地域の民生委員さんに連絡。手分けして捜索。すぐに見つかると思ったんです、いつも通りに。でも、母は見つかりませんでした。
妹:どこに行ったのかも検討がつきませんでした。そしたら、翌日、介護事業所の職員さんが隣町の神社で見つけたと連絡がありました。
姉:妹と病院に駆けつけると、母は病院のベッドで疲れて寝ていました。そんな姿を見て「お母さん、もう私たち無理だよ、ごめん」と号泣してしまいました。
最終的に、私はケアマネージャーとして娘さんたちの意向を汲み、お母さんの入院中に施設への入所の申し込みを行い、それから半年後、施設入所となりました。
在宅介護のその後…
お母さんは、最後の長距離徘徊後の入院が原因で寝たきりの状態となってしまいました。
でも、入院先から入所されるまでの道のり、娘さんたちは実家に立ち寄ってお母さんに自分たちの家を見せてから施設に向かいました。
入浴介助の際、噛みつかれたり引っ掻かれたり、食事の時にはなかなか口を開けてくれなかったりと苦労が絶えなかった訪問介護のヘルパーさんたちや短期入所の介護の職員さんたち、近所の方々など苦労を分かち合った人たちがお母さんを見送ってくれていました。
姉:とても大変で辛かったけれど、在宅で介護をして良いこともありました。それは、私たちの周りににこんなに一生懸命になってくれる人たちがたくさんいてくれた、ということが分かったことです。
妹:下手したら母を殺して姉も殺してたかもしれないと思うくらい、追い込まれていました。でも、朝になったら「おはようございます!」とヘルパーさんが来てくれる、それだけが頼みの綱だったんです。
姉:母は喋ることも動くことも出来なくなりました。お医者さんは「脳が真っ白で、何もわからない状態です。」と説明されました。でもね、母は私たちを見ると笑うんですよ。
入所の日、そう話して2人は笑っていました。
ちょっと心を休めて
介護に休みはありません。この娘さんたちもそうでした。でも、やはり、自分の時間やホッとする時間は誰にだって必要なんです。ヘルパーさんが来る時間だけでもホッとする、短期入所の時間に自分の時間ができる、ちょっとしたことでも介護者の負担を減らす方法です。
ひとりで抱えてしまわないで、人の力を借りてください。誰かに話すだけでも心が軽くなるかもしれません。
最後に、認知症の家族を介護しているあなたに役に立つ書籍を紹介します。
認知症の人の気持ちが分かる本と認知症の親を介護している人の心の本です。
改めて「ああ、こんなことか」と気づくことがあるかもしれません。
おすすめ

マンガでわかる!認知症の人が見ている世界2
認知症の人が見ている世界と、周囲の家族や介護者が見ている世界との違いをマンガで克明に描き、困った言動への具体的な対応策を紹介しています。
本書を読んで認知症の人が見ている世界を理解することにより、認知症の人への適切な寄り添い方を知り、毎日の介護の負担を軽減する一助としてください。
認知症の親を介護している人の心を守る本
家族に認知症がいるすべての人必読!「介護疲れ」を無視して頑張ろうとしていませんか?
懸命に支えても、尽くしても止めれない進行への理解と「ケアを続けられるしくみ」づくりで、時間的、精神的、肉体的な負担が軽くなる方法。
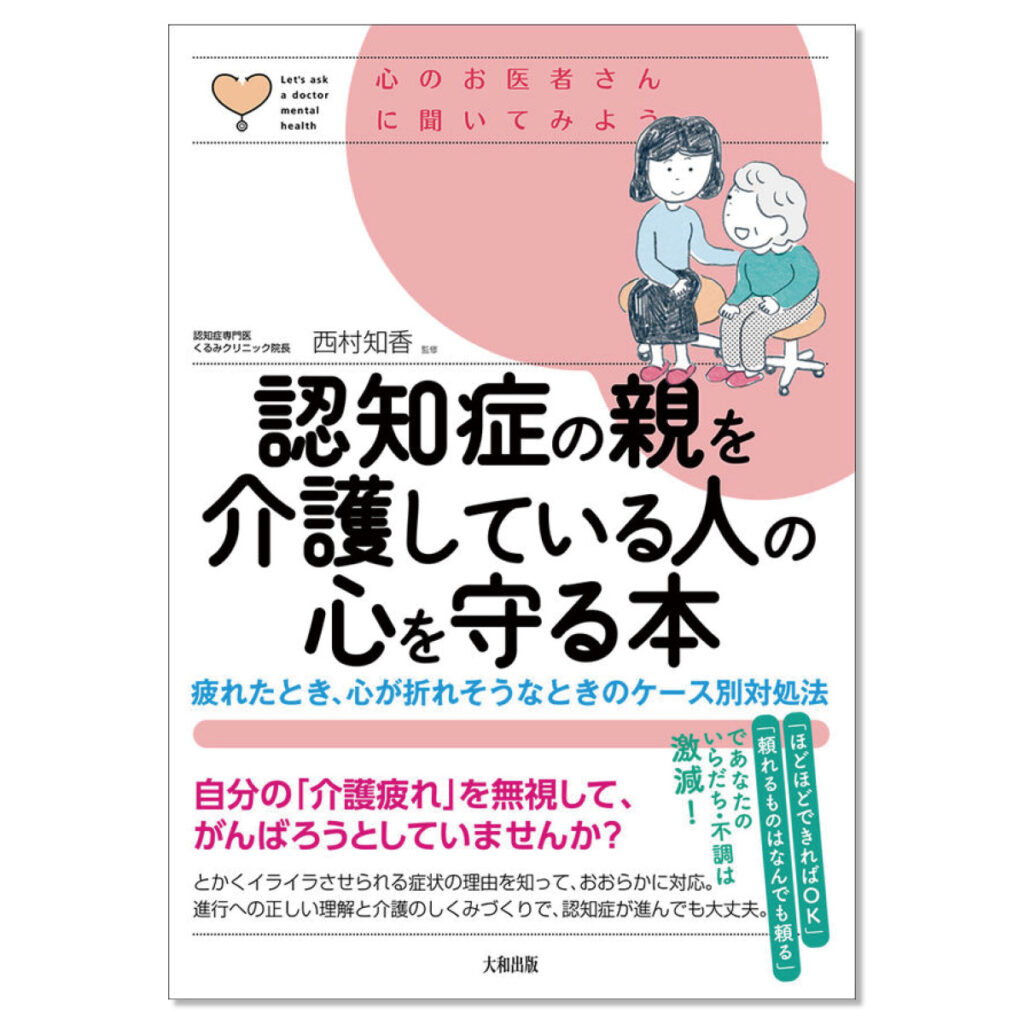
まとめ 4つの大切なこと

認知症の親の在宅介護は、「親であること」と「親が認知症であること」が相容れなくて、とてもつらい介護をしているご家族が大変多いです。
「親だから何とかなるんじゃないか」「親だからきっと大丈夫」と頑張って潰れかけた人を本当に多く見てきました。
- 疲れたら休む
- ダメになりそうだったら助けを呼ぶ
- チームでケアする
- 相談できる場所を作る
一度自宅で介護を始めたからと言って、最期まで自分で介護を行わなければいけないわけではありません。
あなたのそばにもこの事例の娘さんたちのように、自分たちのために一生懸命動いてくれる仲間がいるはずです。
辛くて苦しい胸の内を誰かに打ち明けて心の負担を軽くしてください。
自分1人で全てを抱え込まないようにしてくださいね。
投稿者プロフィール

- 介護福祉士・主任介護支援専門員・認知症ケア専門士・社会福祉士・衛生管理者・特別養護老人ホーム施設長・社会福祉法人本部長経験と、福祉業界で約25年勤務。現在は認知症グループホームでアドバイザー兼Webライター。
最新の投稿
 介護の豆知識2025年1月27日サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)と住宅型有料老人ホーム:どちらを選ぶ?
介護の豆知識2025年1月27日サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)と住宅型有料老人ホーム:どちらを選ぶ?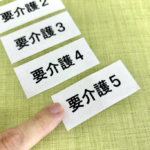 認知症2023年11月20日要介護5で在宅介護は無理?介護事例や施設選びのコツなど詳しく解説!
認知症2023年11月20日要介護5で在宅介護は無理?介護事例や施設選びのコツなど詳しく解説! おすすめグッズ・サービス2023年10月19日片麻痺の人におすすめの自助具とは?|体験・経験シリーズ
おすすめグッズ・サービス2023年10月19日片麻痺の人におすすめの自助具とは?|体験・経験シリーズ 介護の豆知識2023年8月31日訪問介護には掃除の範囲がある!知っておきたいヘルパーさんに頼めない掃除とは?
介護の豆知識2023年8月31日訪問介護には掃除の範囲がある!知っておきたいヘルパーさんに頼めない掃除とは?

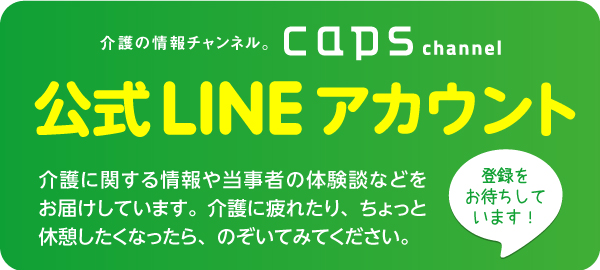










コメント