親の介護が現実味を帯びてくると、まず気になるのが「介護サービスはいくらかかるのか」という費用面の問題です。介護は長期化することも多く、経済的な負担が家計に大きく影響する可能性があります。この記事では、介護サービスの種類ごとの費用目安や、介護保険制度の活用方法、そして費用を抑えるための工夫まで、わかりやすく解説します。
介護サービスの種類と費用の目安
介護サービスには大きく分けて「在宅介護」と「施設介護」があり、それぞれ費用の構造が異なります。
1. 在宅介護サービスの費用
在宅介護では、介護保険を利用して訪問介護や通所介護(デイサービス)などを受けることができます。
| サービス内容 | 月額費用(自己負担1割の場合) | 備考 |
|---|---|---|
| 訪問介護(ヘルパー) | 約5,000〜20,000円 | 利用頻度による |
| 通所介護(デイサービス) | 約7,000〜30,000円 | 食費・送迎費含む場合あり |
| 訪問看護 | 約5,000〜15,000円 | 医療的ケアが必要な場合 |
| 福祉用具レンタル | 約1,000〜5,000円 | 介護ベッド・車椅子など |
※要介護度や利用回数によって変動します。
2. 施設介護サービスの費用
施設介護は、特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの入所型サービスです。
| 施設種類 | 月額費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 約80,000〜150,000円 | 所得に応じた減免制度あり |
| 介護付き有料老人ホーム | 約150,000〜300,000円 | 入居一時金が必要な場合も |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 約100,000〜250,000円 | 生活支援サービス付き |
施設介護は在宅介護よりも費用が高くなる傾向がありますが、24時間体制のケアが受けられる安心感があります。
介護保険制度を活用して費用を抑える
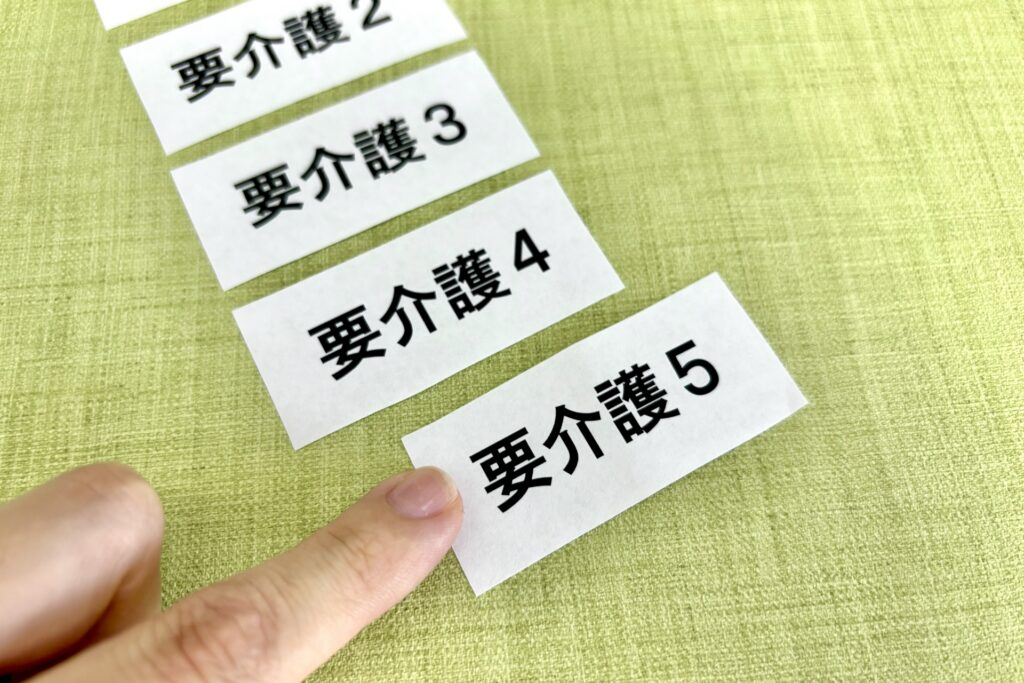
介護サービスの費用は、介護保険制度を利用することで大幅に軽減できます。
介護保険の基本
- 対象者:原則65歳以上(40歳以上でも特定疾病があれば対象)
- 自己負担割合:原則1割(所得に応じて2〜3割)
- 支給限度額:要介護度に応じて月額約50,000〜360,000円まで
例えば、要介護2の方が訪問介護とデイサービスを併用しても、限度額内であれば自己負担は1割で済みます。
高額介護サービス費制度
介護サービスの自己負担額が一定額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。世帯の所得に応じて上限額が設定されており、申請すれば後日還付されます。
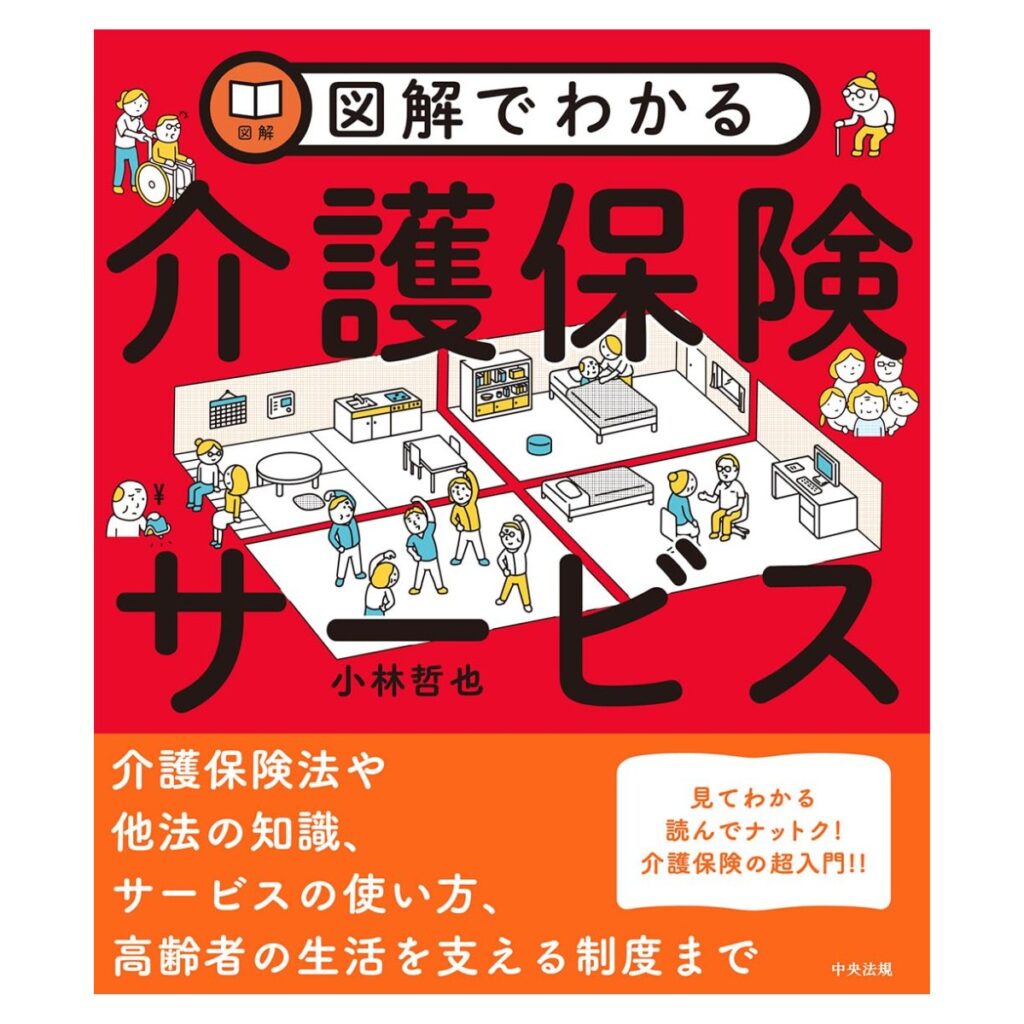
図解でわかる介護保険サービス
高齢者をとりまく課題から、介護保険制度や介護保険サービス、その他関連制度の知識をわかりやすく解説。豊富な図とイラストで視覚的に理解できる構成。介護保険サービスの従事者や新人職員、ケアマネ等の相談援助職など、高齢者支援にかかわるあらゆる方にオススメ。
介護にかかる“実際の”総費用は?

介護はサービス費用だけでなく、交通費・医療費・生活費なども含めて考える必要があります。
1. 月額の平均費用
- 在宅介護:約50,000〜100,000円
- 施設介護:約150,000〜300,000円
2. 介護期間の平均
厚生労働省の調査によると、介護期間の平均は約4年7ヶ月。つまり、総額で数百万円〜1,000万円以上かかるケースもあります。
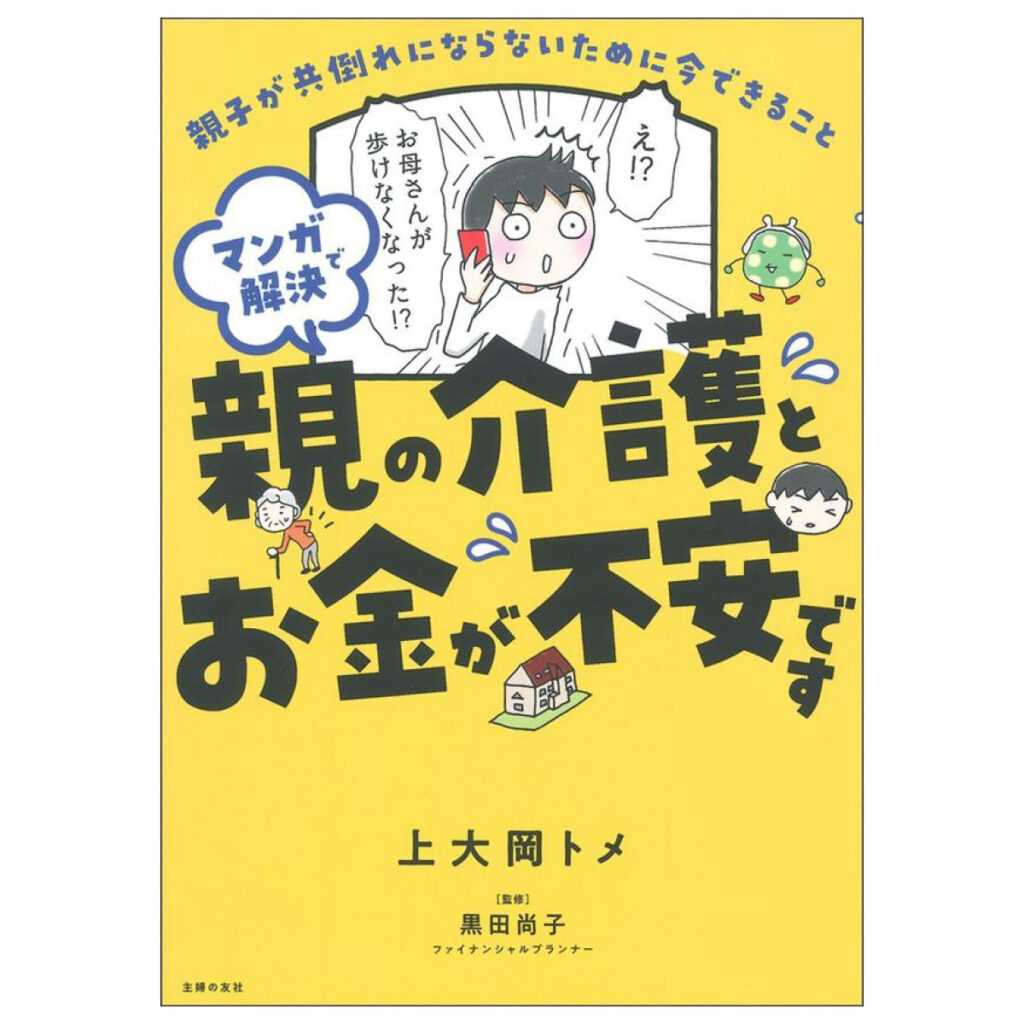
マンガで解決 親の介護とお金が不安です
「お母さんとお父さん、なんか老けた?」と思ったら、今すぐ読むべき1冊。「いま、親に何かあったら、どうしよう?」超高齢社会で長生きしても、最期の数年は不健康である場合が多い。
今何をしたらいいのかわからないけれど、漠然と不安を持っている方に、「親の介護とお金」の超入門編。

身近な人に介護が必要になったときの手続きのすべて
親が倒れた! どうする?
どこに相談すればいいの?申請はどうしたらいいの?施設選びは?在宅介護をするには?
不安を一気に解消してくれる1冊。
見やすく、読みやすい大判サイズです。
介護が必要になったらまずは手にとって欲しい1冊です。
介護費用に備えるためのポイント
介護費用の準備は、保険や貯蓄だけではありません。家族間での話し合いも、立派な備えのひとつです。親の希望や経済状況、兄弟姉妹の協力体制などを事前に共有しておくことで、いざという時にスムーズな対応が可能になります。 特に「誰がどこまで費用を負担するか」「どの介護サービスを使うか」といった点は、感情的なすれ違いを生みやすいため、元気なうちに少しずつ話題にしておくのが理想です。話しづらいテーマではありますが、“備える”という視点で冷静に向き合うことが、家族全体の安心につながります。
1. 介護保険外の民間保険を検討する
民間の介護保険では、要介護認定を受けた際に一時金や年金形式で給付されるタイプがあります。早めに加入しておくことで、将来の備えになります。
2. 自治体の支援制度を活用する
自治体によっては、交通費補助や介護用品の支給など、独自の支援制度を設けている場合があります。地域包括支援センターに相談すると、利用できる制度を教えてもらえます。
3. 介護休業制度の活用
会社員の場合、介護休業制度を使って一定期間仕事を休むことができます。収入が減るリスクはありますが、家族の介護に専念できる貴重な制度です。
まとめ|介護サービスはいくらかかる?不安を減らすには「情報」と「備え」

「介護サービス いくらかかる」と検索する人の多くは、親の介護が現実になりつつある方でしょう。介護は突然始まることも多く、費用面の不安が大きなストレスになります。
しかし、介護保険制度や自治体の支援、民間保険などをうまく活用することで、負担を軽減することは可能です。まずは情報を集め、できることから備えていくことが、安心につながります。
こちらの記事もおすすめ
投稿者プロフィール

- 介護福祉士・主任介護支援専門員・認知症ケア専門士・社会福祉士・衛生管理者・特別養護老人ホーム施設長・社会福祉法人本部長経験と、福祉業界で約25年勤務。現在は認知症グループホームでアドバイザー兼Webライター。
最新の投稿
 介護の豆知識2025年1月27日サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)と住宅型有料老人ホーム:どちらを選ぶ?
介護の豆知識2025年1月27日サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)と住宅型有料老人ホーム:どちらを選ぶ?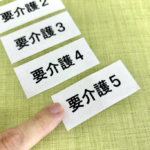 認知症2023年11月20日要介護5で在宅介護は無理?介護事例や施設選びのコツなど詳しく解説!
認知症2023年11月20日要介護5で在宅介護は無理?介護事例や施設選びのコツなど詳しく解説! おすすめグッズ・サービス2023年10月19日片麻痺の人におすすめの自助具とは?|体験・経験シリーズ
おすすめグッズ・サービス2023年10月19日片麻痺の人におすすめの自助具とは?|体験・経験シリーズ 認知症2023年10月17日親が認知症になったらどうする?介護の始め方と自宅で使える支援サービスを徹底解説
認知症2023年10月17日親が認知症になったらどうする?介護の始め方と自宅で使える支援サービスを徹底解説











コメント