まだ世の中に知られていない表現や作品を発掘する日本唯一のアウトサイダー・キュレーター櫛野展正(くしの・のぶまさ)によるコラム。
今回は、創作によって病気と上手くつきあい、自由な環境の中で作品を生み出す栗田淳一さんを取材しました。

「やまなみ工房」のアトリエにて
国内外での展覧会の開催に留まらず、ドキュメンタリー映画の公開やライブハウスの運営など、従来の福祉の枠をゆるやかに飛び越えるような活動を続けている滋賀県甲賀市にある障害者支援施設「やまなみ工房」。この施設を利用する障害のある人たちのなかから、次々と独創的な表現者が誕生し、いまや“ATELIER YAMANAMI ”の名は世界のアウトサイダー・アートの関係者からも、よく知られた存在になっている。
ただ、誤解のないように説明しておくと、施設を利用する人たちや働くスタッフも含め、決して特別な芸術的才能の持ち主が集まっているわけではない。「いかに日常をその人らしく過ごせるか」に重点を置いて日々の活動を続けていった結果、どこにも真似できない、のびのびとした創作環境が育まれていったのだ。
個性豊かな人たちの多い「やまなみ工房」のなかで、僕が特に興味を抱いたのは、ペンによる凛としたモノクロームの細密画が美しい栗田淳一(くりた・じゅんいち)さんの作品だ。栗田さんは、2015年から「やまなみ工房」へ通っているが、ちょうど彼が施設に通い始めた頃、僕は工房のアトリエでその絵に魅了され、ほんのわずかだが栗田さんと会話を交わした記憶がある。栗田さんも、そのときのことを覚えてくれていたようで、今回はじっくり彼の半生について話を伺うことができた。


やまなみ工房にある6畳ほどの居室が、栗田さん専用のアトリエになっている。室内には、近年制作を進める人形などの立体造形が並び、机や椅子、そして床のフローリングにまで絵が描かれている。
「机や椅子、そしてこの床は昨年12月くらいから誰の許可も取らずに勝手に描いてしまったんです」

そう不敵に笑みを浮かべる栗田さんは、1988年に、3人きょうだいの長男として大阪で生まれた。小学生の頃は、ソフトボールに熱中した。高校生になると野球部に所属し、控え選手だったため公式戦の出場経験はなかったものの、投手として練習に励んだ。
ところが、高校3年生になったとき、怪我が重なったり同級生のキャプテンから試合中のミスを気にかけてもらえなかったりしたことが引き金となり、退部。周囲の友だちが、次々と進路を決めていくなかで、将来の夢を持てずにいた栗田さんは、知人についていく形で大阪芸術大学を目指すことになった。
「受験のために、5月からはデッサン教室に通いはじめました。もともと絵を描くことは好きだったんですが、倍率の低い陶芸コースを受験したんです」
見事に現役合格し、2006年に大阪芸術大学工芸学科陶芸コースへ入学。栗田さんと同様に、同級生の多くは初めて陶芸に触れる人ばかりだったようだ。ここでモノづくりの楽しさを知り、友だちや先生にも恵まれた栗田さんは、4年間の大学生活を謳歌する予定だった。
「大学1年生のとき、遊び過ぎて単位を落とすような状態だったから『2年生になったら、ちゃんとしよう』と決めていたんです。2年生になってから、授業は毎日朝から晩まで受講し、終わったらテニス部で活動。週に何度かコンビニで夜勤のバイトをして、休みなくスケジュールをぎっしりと詰め込んでいました。そのときのことはほとんど覚えていないんですが、あるとき『ちょっとおかしいから病院に連れてってくれ』と母親に訴えていたようです」


躁うつ病になり創作できない日々
心身ともに限界に達していた栗田さんは9月に通院し、躁うつ病と診断を受けたため、大学を休学することになった。最初の通院先では、薬だけが増え続け、一向に症状が改善する兆しがなかったため、翌年1月に大学病院へ転院。一時は光が眩しくて目を開けることができなくなるなどの副作用にも悩まされたが、時間をかけて薬の調整を続けていった。
「こんなに長引くとは思ってもみなかったので、正直言って、大学を休学することになったときは、『これでしばらく休めるわー』と喜んでました」
2009年に、いちど復学したものの1ヶ月して再び体調を崩し入院。休学中は、家で寝たりインターネットでアニメを観たりして過ごした。栗田さんにとって何より幸運だったのは、友だちに恵まれていたことだ。家で休んでいるときも、高校時代の旧友や大学の友人が部屋を掃除しに来てくれたり車で外へ連れ出してくれたりと、僕が想像するよりもずっと楽しく過ごしていたようだ。

「いまではしんどくなったときの対処法が自分で分かっているんですが、当時は良くわからなかったから自分なりに必死で考えていました。2009年くらいからは、観ていたアニメの影響で、樹脂粘土などを使ってキャラクターのフィギュアをつくり始めたんです」
症状が落ち着いていた頃は、近所のレンタルビデオ店で夜勤のアルバイトをしていたこともあった。調子が悪くなったとき、1ヶ月ほど休ませてくれるような理解のある職場だったが、「病気を治して早く一般就労しなければならない」、当時は栗田さん自身がそんな思いを抱いていたようだ。
2012年からは、本格的にフィギュア制作を学ぶため、大阪総合デザイン専門学校へ通い始めた。毎日行くことは難しかったが、体調が悪いながらも何とか通学を続け、先生たちの配慮で2年生に進級することができた。ところが、翌年に家族の都合で滋賀県に転居。そうした環境の変化がきっかけとなり、栗田さんは再度大きく体調を崩してしまう。
「全く通学することができなくなって、そのときはさすがに落ち込みました。家で静養を続けていたんですが、家族にもずいぶん負担をかけました。母親からは『家族なんやから、迷惑って言葉は言わんといてな』と声をかけられたことを思い出します」

一口に「調子が悪い」と言っても、そのしんどさは一様ではない。電車に乗れない日もあったし吐いてしまうような日もあった。それに、うつ状態のときだけではなく躁状態で感情が昂ぶり苦しいときだってある。躁うつの症状は、第三者が見たときに、はっきりと分かるような身体的症状がないため、周囲に理解してもらえないことも多い。きっと栗田さんも、自分ではどうにもできないという葛藤に悩まされていたことだろう。
「そのうち自立支援医療や障害者手帳の申請手続きをするようになって、『これは一生もんやな』と思うようになりました。手帳を申請するとか、いまこうして障害者施設で活動するとか、昔は考えたこともなかったですから。『手帳を持っているから障害者なんやな』って思う程度で、自分では『障害者』なんて自覚はないんです。とにかく現状をなんとか打開したいって思いだけでした。それだけ、しんどくって、もがいていたんでしょうね、当時は、同級生がツイッターなどに作品をアップするのを見ることがつらかったんです。でも、自分ではしんどくて何もつくれない。もう、立体作品をつくることができなくなっていました」


体調で変わる作風
そんな栗田さんは、2014年1月から、誰に見せるわけでもなく絵を描き始めた。「絵を描くことで、しんどさをやり過ごすことができたし、白い紙に黒いペンで描いていたら『何かやった』という達成感を抱くことができたんです」と語る。しばらく経って、いくつかの公募展に出展してみたところ、次々に入選。そのことが、栗田さんにとって大きな自信となったようだ。
2014年のとき、偶然に「やまなみ工房」の存在を知り、「ここで絵を描いてみたい」と思いを寄せるようになった。同年12月、施設長の山下完和さん宛にメールを送り、市の障害福祉課を通じて翌年より通所がスタートした。
「いま考えたら失礼な話なんですが、やまなみ工房に来たときに『利用できるものは利用したい』って山下さんに話したんです。それだけ藁をもすがる思いで必死だったんだと思います」

現在、栗田さんは「やまなみ工房」へ週に3〜4回のペースで通っている。昨年8月からは初めての一人暮らしも開始した。近年では、作品が高い評価を受けるようになり、国内だけでなく香港など海外でも展示の機会が増えている。
「いろんなところに展示される機会が増えたことは嬉しいですし、展覧会に出展したり作品が売れたりすることで、『これを続けてていいんやな』って自分で安心するところがあるんです。まぁ、僕のちっちゃいプライドなんですけど、同年代の友だちに話すときも、『ただ描いているだけ』っていうよりも、やっぱり何か成果を話したいですしね」
栗田さんの表現で、何より興味深いのは、体調の変化によって描く絵が変化しているということだ。壁にかけられた不気味な絵や造形物は体調の悪いときにつくられている。制作のきっかけは、人の体に絵を描いてみたいという衝動に駆られたこと。


「昔から全身に入れ墨を入れてみたい、体中をペイントして生活をしたいという願望を持っていたんですが、その代用としてつくり始めました。いまでも感情が高揚したとき、自分の体を縫い合わしてみたい、血で描きたい、目をえぐりたいなどという危険な衝動が生まれるんですが、そういう思いをそらすための代償として人形に身代わりになってもらっています」
吊るされた立体造形は市販の全身タイツに新聞紙を詰め込んで、上から絵を描いたもので、額や目、肘などに刺さった爪楊枝が針のようにも見えて、どこか痛々しい。隣にある大きな布に人形が吊るされた作品は、「人間はみんな見えない何かで首を吊るされており、ときどき締め付けられている」という栗田さんの独特の死生観に基づいて生み出されている。
「傷つけたり首を切ったりするのは可愛そうだから、これらは『人間』ではなくて『ひとのかたち』をした何かなんです。『ひとのかたち』だったら何をしても許されますから。いまは色々な素材に描くことが楽しくて、どの素材も僕のわがままを受け止めてくれるんです。これだけ爪楊枝で刺しても文句ひとつ言わないんだから、『雑に描いたらあかん』って敬意だけは持ってますよ」


僕が初めて目にしたとき、つまり栗田さんの初期の絵画は、人物の隙間を線や丸で埋め尽くしていく表現が多用され、僕は少し息苦しさや切迫感を感じてしまう。それに比べ、「仏像の模写をしていたことで生まれた」という机や床などに描くキャラクターの集合体は、体調の良いときに描かれたものだ。どこか楽しげで、見るものに色々な物語を想起させる。描く支持体が二次元から三次元へと広がったように、栗田さんの心境も野心的なものから表現そのものを楽しむ方向に広がったのではないかと僕は推測する。

栗田さんによると、「調子が悪いとき、制作に没頭して時間をやり過ごすことで、症状が収まるのを待つ」のだそうだ。それを彼は「頓服代わり」という言い方で表現する。言い換えれば、自身に降りかかる何らかの災いを回避するために、それだけ「芸術」は有効なのだろう。
その意味において、アウトサイダー・アートの制作者の多くは、決して狂人だから制作しているわけではない。みずからの心を正気に保っておくためにつくり続けているのだ。それにしても、同じような障害で苦しんでいる人が多いなかで、みずからの障害との上手な付き合い方を見つけた栗田さんは、実に幸福な存在と言える。


作品ができるから大丈夫
現在でも、季節の変わり目や調子が良いときの反動などで、急に気分が落ち込んでしまうこともある。しかし以前と違うのは、「つくることができんねんから、どんなにしんどくなっても、もう大丈夫やな」という確固たる自信を持てるようになったことだ。栗田さんの話を伺っていると、むしろ「面白い作品がつくれるから」とそうした機会の到来を待ちわびているかのような錯覚さえ覚えてしまう。
「いま住んでいるアパートの白い壁一面に絵を描きたいけど、賃貸やから描くことができなかったんです。『やまなみ工房』なら、勝手に描いても許してくれるやろうと思って。許して貰うまで描きこんでから見せるようにしてます。天の邪鬼なんで『好きに描いてもいい』と言われたら、やる気がなくなっちゃうんで」

「あるがままを認める」という「やまなみ工房」の自由な雰囲気がなければ、栗田さんのこうした作品は規制されていたはずだから、ある意味で、施設スタッフとの絶妙な信頼関係で成り立っている様が、傍から見ると何とも愉快だ。
最後に、今後やりたいことを尋ねたところ、「こっそり壁や窓やカーテンなどにも描いて、部屋全体を埋めつくしてみたい」と教えてくれた。「それ宣言しちゃっても大丈夫ですか」と聞き返すと、「あぁ、しまった。言わないほうが良かったですね。人前で言ったら、僕の性格からして、やらないですよね」と栗田さんは微笑んだ。


投稿者プロフィール
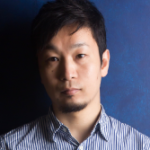
-
文・撮影
櫛野展正(くしの のぶまさ)
1976年生まれ。広島県在住。2000年より知的障害者福祉施設職員として働きながら、広島県福山市鞆の浦にある「鞆の津ミュージアム」 でキュレーターを担当。2016年4月よりアウトサイダー・アート専門ギャラリー「クシノテラス」オープンのため独立。社会の周縁で表現を行う人たちに焦点を当て、全国各地の取材を続けている。
住所:広島県福山市花園町2-5-20
クシノテラス http://kushiterra.com
最新の投稿
 アウトサイドからこんにちは!2020年4月13日#26(最終回) 彼方からの宿題
アウトサイドからこんにちは!2020年4月13日#26(最終回) 彼方からの宿題 アウトサイドからこんにちは!2020年2月10日#25 無限のサークル
アウトサイドからこんにちは!2020年2月10日#25 無限のサークル アウトサイドからこんにちは!2019年12月10日#24 永遠のトラック野郎
アウトサイドからこんにちは!2019年12月10日#24 永遠のトラック野郎 アウトサイドからこんにちは!2019年10月15日#23 「観客」から「演じ手」へ
アウトサイドからこんにちは!2019年10月15日#23 「観客」から「演じ手」へ
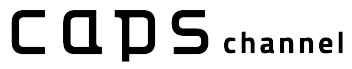

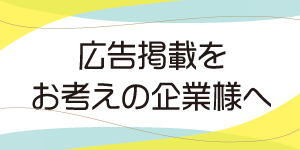


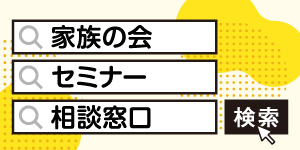





コメント