親が認知症になったとき、介護はどう始める?「なんか最近怒りっぽいな」「同じものが何個も買ってある」「家の掃除が出来ていない」…こうしたことが目立つようになったら要注意です。
この記事では、認知症の兆候から自宅で受けられる介護サービス、費用負担の仕組みまでを詳しく解説します。
親が認知症かもしれないと感じたら

「最近、親の様子がちょっと変…」 そんな違和感を覚えたことはありませんか? 認知症は、早期発見と適切な支援が何より重要です。この記事では、「親 認知症 介護」という視点から、認知症の兆候、診断の流れ、介護の始め方、そして自宅で受けられる支援サービスまでをわかりやすく解説します。
認知症の兆候とは?見逃しやすいサインに注意
認知症は、加齢による物忘れとは異なり、日常生活に支障をきたす症状が現れます。以下のような変化が見られたら、注意が必要です。
よくある兆候
- 同じ話を何度も繰り返す
- 財布や鍵などを頻繁に失くす
- 買い物で同じものを何度も購入する
- 急に怒りっぽくなる、感情の起伏が激しくなる
- 掃除や料理など、以前できていたことができなくなる
- 電話を何度もかけてくる
- 小銭ばかり使う、金銭管理が雑になる
こうした変化が続く場合は、「年のせい」と片付けず、早めに医療機関で診断を受けることが大切です。
病院を嫌がる場合の対応方法
認知症の兆候が見られても、親が病院に行きたがらないケースは少なくありません。「年のせいだから」「恥ずかしい」「何も問題ない」といった言葉で拒否されると、家族としてどう対応すればいいのか悩んでしまいます。
なぜ病院を嫌がるのか?本人の心理を理解する
- 病気と認めたくない気持ち:「認知症」という言葉に対する恐怖や偏見が根強く、診断されること自体を避けたいという心理が働きます。
- 自尊心の防衛:長年家族を支えてきた立場として、「弱った姿を見せたくない」「子どもに迷惑をかけたくない」と感じていることもあります。
- 過去の医療体験への不信感:以前の通院で嫌な思いをした経験があると、病院そのものに抵抗を持っている場合もあります。
こうした背景を理解したうえで、無理に説得するのではなく、本人の気持ちに寄り添うことが大切です。
病院に行ってもらうための工夫
- 目的を変えて伝える:「認知症の検査」ではなく、「最近ちょっと疲れてるみたいだから、健康チェックに行こう」と伝えると、受け入れやすくなります。
- かかりつけ医を活用する:普段から通っている内科やクリニックで相談することで、本人の警戒心が薄れます。医師から自然に認知機能のチェックをしてもらうのも有効です。
- 家族の健康診断に便乗する:「私も一緒に診てもらうから」と伝えることで、受診へのハードルが下がります。
- 第三者の声を借りる:ケアマネジャーや地域包括支援センターの職員など、信頼できる第三者からの助言は、本人の心を動かすきっかけになります。
受診につながらなくても焦らない
すぐに病院に行ってもらえなくても、日常の中で少しずつ信頼関係を築きながら、タイミングを見て再提案することが大切です。認知症は進行性の病気ですが、早期発見がすべてではありません。家族が冷静に見守り、必要な支援を準備しておくことで、いざという時にスムーズに対応できます。
認知症と診断されたらまずすべきこと
認知症と診断された場合、介護保険サービスを利用するためには「要介護認定」を受ける必要があります。
要介護認定の流れ
- 市区町村の窓口で申請
- 調査員による訪問調査
- 主治医の意見書の提出
- 判定・通知(原則30日以内)
認定結果に応じて「要支援1〜2」「要介護1〜5」に区分され、利用できるサービスや費用負担の上限が決まります。
自宅で受けられる介護サービス一覧

認知症の親を自宅で介護する場合、介護保険を活用することで、さまざまな支援を受けることができます。
訪問系サービス
- 訪問介護:食事・排泄・掃除などの生活支援
- 訪問入浴介護:浴槽を持参して自宅で入浴支援
- 訪問看護:医療的ケア(点滴・吸引など)を提供
- 訪問リハビリ:理学療法士などによる機能訓練
通所系サービス
- デイサービス:日帰りで入浴・食事・レクリエーションを提供
- 認知症対応型通所介護:少人数制で柔軟な対応が可能
- 通所リハビリ:病院や施設でのリハビリ中心のサービス
宿泊系サービス
- 医療型ショートステイ:医療的ケアが必要な方向けの施設
- ショートステイ:短期間の施設入所(介護者の休息にも活用)
認知症介護の費用と負担軽減の仕組み
介護保険サービスを利用する場合、自己負担は原則1割(所得に応じて2〜3割)です。 ただし、利用限度額を超えると全額自己負担になるため、ケアマネジャーと相談しながらプランを立てることが重要です。
負担軽減制度
- 高額介護サービス費制度:月額負担が一定額を超えた場合に払い戻し
- 福祉用具のレンタル・購入補助:介護ベッドや手すりなど
- 住宅改修費の助成:段差解消や手すり設置などの工事費補助
介護者の負担を減らすためにできること
認知症介護は、身体的・精神的に大きな負担がかかります。介護者が倒れてしまっては元も子もありません。
介護者支援のポイント
- レスパイトケア:ショートステイなどで一時的に介護を離れる
- 介護者カフェ・交流会:同じ悩みを持つ人との情報交換
- 地域包括支援センターの活用:相談・制度案内・ケアプラン作成支援
また、介護離職を防ぐために、介護休業制度や時短勤務制度の活用も検討しましょう。
早期から介護サービスを使うメリット

「まだ自分たちだけでなんとかなる」と思っていると、介護が限界を超えてしまうことがあります。 早期から介護サービスを利用することで、親も子もサービスに慣れ、スムーズな支援体制を築くことができます。
メリット例
- 介護のやり方が固定化されず、柔軟な支援が可能になる
- 親が外部の人に慣れることで、施設入所への抵抗が減る
- 子どもが介護のノウハウを学び、安心して対応できる
まとめ:親の認知症介護は「早めの準備」と「制度の活用」が鍵
親が認知症になったとき、介護は突然始まります。 しかし、早めに兆候に気づき、診断を受け、制度を活用することで、負担を大きく減らすことができます。
「親 認知症 介護」という課題に直面したときこそ、情報を集め、相談し、支援を受けることが大切です。 自宅での介護も、地域のサービスと制度を組み合わせることで、安心して続けることができます。
認知症を理解するおすすめの本
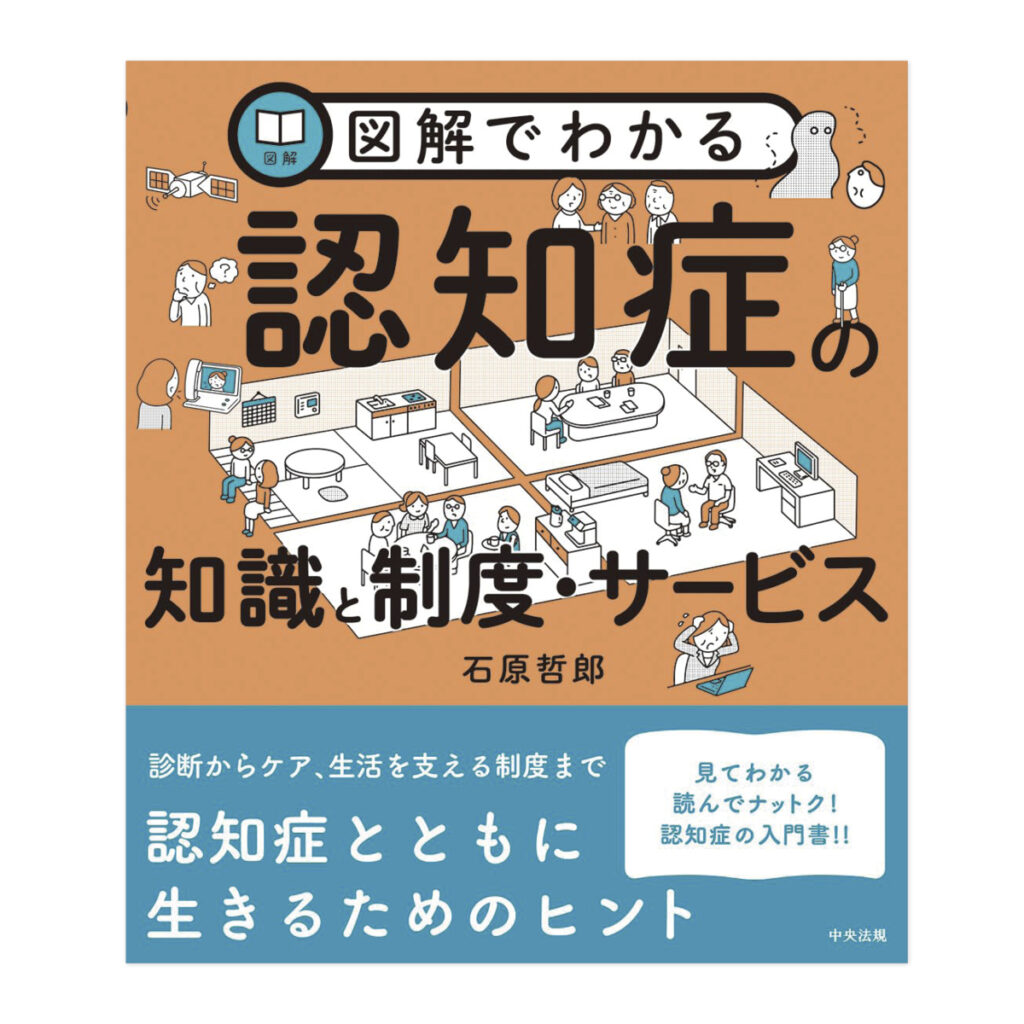
図解でわかる認知症の知識と制度・サービス
疾患としての認知症の知識や、使えるサービス・制度を解説した入門書。
認知症の原因疾患や検査・治療のほか、診断後にかかわる人(専門職)、サービスなどを網羅し、図とイラストでわかりやすくまとめられています。
専門職にも家族介護者にも、認知症を知る1冊目としておすすめ。

「認知症の人」への接し方のきほん
矢吹 知之(著)
一見して同じ現象でも、その原因も、そのとき感じている気持ちも一人ひとり異なっています。
そのため、認知症の人への接し方には、万人に通じる答えは存在しないのです。
はじめて認知症介護をする方はもちろんのこと、「本やインターネットに書いてある通りにやってみたけれど上手くいかなかった」という人にも、ぜひ読んでいただきたい一冊です。

マンガでわかる!認知症の人が見ている世界2
本書は、認知症の人が見ている世界と、周囲の家族や介護者が見ている世界との違いをマンガで克明に描き、困った言動への具体的な対応策を紹介していきます。
本書を読んで認知症の人が見ている世界を理解することにより、認知症の人への適切な寄り添い方を知り、毎日の介護の負担を軽減する一助としてください。
投稿者プロフィール

- 介護福祉士・主任介護支援専門員・認知症ケア専門士・社会福祉士・衛生管理者・特別養護老人ホーム施設長・社会福祉法人本部長経験と、福祉業界で約25年勤務。現在は認知症グループホームでアドバイザー兼Webライター。
最新の投稿
 介護の豆知識2025年1月27日サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)と住宅型有料老人ホーム:どちらを選ぶ?
介護の豆知識2025年1月27日サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)と住宅型有料老人ホーム:どちらを選ぶ?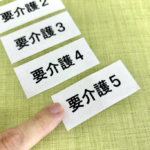 認知症2023年11月20日要介護5で在宅介護は無理?介護事例や施設選びのコツなど詳しく解説!
認知症2023年11月20日要介護5で在宅介護は無理?介護事例や施設選びのコツなど詳しく解説! おすすめグッズ・サービス2023年10月19日片麻痺の人におすすめの自助具とは?|体験・経験シリーズ
おすすめグッズ・サービス2023年10月19日片麻痺の人におすすめの自助具とは?|体験・経験シリーズ 認知症2023年10月17日親が認知症になったらどうする?介護の始め方と自宅で使える支援サービスを徹底解説
認知症2023年10月17日親が認知症になったらどうする?介護の始め方と自宅で使える支援サービスを徹底解説












コメント