支援者と支援を受ける高齢者家族のズレ
知人のヘルパーが嘆いていた。
「利用者さんに“うちの子はいい大学を出た”“東京の一流企業に勤めている”なんて自慢する人がおられる。でも、そんな人に限って、子どもの世話にはならないと言われる。だけど、私らにはすごくいろんな要求をされるんです。なかにはあんたらの給料はわたしらが払っとる、介護保険料を払い続けてきた。そういう人さえいます。この人、可愛くないなあ、子どもの世話にならんと言いながら、赤の他人のわたしらの世話になっていいんかい。そう思います」
似たような話を地域の高齢者支援に取り組む民生委員からも聞いたことがある。
「地域のひとり暮らしの方が怪我をした。連絡先を聞いていたので息子さんに電話したら、すごく叱られた。“息子に迷惑をかけないようにしているのに、いらんことをして!!」と。
いまの高齢者には「子どもの世話にはなりたくない」「迷惑をかけたくない」。そう考える人が多い。
介護家族の支援について、地域包括支援センターや施設の職員さんらとの関わりの中で研究してきた私にとって、これは不思議なことだった。
なぜなら、今は長寿時代、倒れるのが「今日かもしれない」「明日かもしれない」高齢者が増えている。それに入院や手術、施設入所の際には家族が身元引受人になることが求められる。
地域包括支援センターであれ、介護施設であれ、支援現場での高齢者支援は先ず、要介護高齢者の家族関係はどうなのか。ひとり暮らしなら、子どもはいるか、どこに住むか、キーパーソンになるのは誰か、どんな続き柄かという話から始まる。家族(夫婦、親子)は互いに助け合う形で作られているのが日本の社会保障制度だから。
しかし、「子どもの世話になりたくない、迷惑をかけたくない」と考える高齢者がいる。なら、そんな高齢者が考える「子どもの世話にならない」とは何なのだろう。自分が倒れた時どうするつもりだろう。ヘルパーやケアマネージャーなど支援者をどうみているのだろう。
そう思ったのだ。
元気高齢者は倒れたときどうするつもりか
そこで元気高齢者の聞き取り調査を始めた。
まず聞いたのは
「これから歳をとり世話が必要になった時、どうなさるつもりですか」
「子どもさんに頼られるつもりですか」だった。
「子どもに頼るつもり」と言う人はほんのわずかで、多かったのは次のような答えだ。
「その時はそのとき、成り行き任せ」
「誰かがどうにかしてくれるだろう」
「考えても仕方がないことは考えない」
「子どもの世話にはならない」
「子どもに迷惑かけるつもりはない」
「ピンピンコロリで死ぬから大丈夫」
元気な場合は80歳過ぎでもそう答える人が多い。
だから、重ねて
「でも、90代まで長生きする時代ですから、元気でも自分で出来ないことが増え、誰かの世話にならざるをえないですよね。その時はどうなさるつもりですか」と聞いた。
すると、「金があるから大丈夫」「介護保険でヘルパーや訪問看護師に頼む」。そんな人も少なくなかった。
わかってきたのは、元気な限り、いまの高齢者には「なりゆき任せ」「金さえあれば、何とかなる」「介護保険があるから大丈夫」、「身体を動かし栄養に気をつけていればピンピンコロリで死ねる」と考える人が多い。
だから、倒れたときのことを具体的に想定し、どう対処するかを子どもと話し合うこともなく、介護保険制度が厳しい状況という事実も知らず、自分で出来る備えもしない。なのに「子どもの世話にならない」と思っている。そんな事実だった。
そんななか、面白いデータを見つけた。
60~70代以上で別居の子どもがいる高齢者と60代以上の別居する親がいる子世代、各1000人を対象とした調査結果である。(ダスキンヘルスレント「“親のいま”に関する親子2世代の意識調査」2022年)
そこには親世代の97.8%が「子どもの負担になりたくない」と回答し、「これから先の親の老後について親子で真剣に話し合った経験がない」割合が、親世代で81.6%、子世代で75.0%を占める。
さらに「話し合ったことがない」と回答する親があげる理由で多いのは「迷惑をかけたくない」「まだ健康だから」「自分の子どもに頼ることを想定していないから」であり、それぞれ8割以上を占めると報告される。
この調査結果と合わせ考えると、知人のヘルパーや民生委員、私が話を聞いた高齢者に限ったことではなく、そうした意識は高齢者に広く分け持たれていると言ってよいだろう。
コロナ禍で激変した高齢者の境遇

だが、コロナ禍が「子どもの世話にならない」と考えていた高齢者を直撃した。そのとき、何が起こったか。
住み慣れた自宅で暮らし続けられなくなった人が少なくないというのである。
コロナ禍が始まりしばらく経った頃、信頼するケアマネージャーから「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)を含め、自宅を離れ施設入所する高齢者が増えている」という話を聞いた。本当だろうか。その時は半信半疑だった。
新聞・テレビなどでは、家族との面会が禁止されるなか、死に目に会えないかもしれないと病院、施設から自宅に戻り、そこで終末を迎える高齢者が増えているとの報道が多かったからである。
だが、特定のケアマネ―ジャーからだけでなく、あちこちで同じような話を聞くようになった。多くは外出機会が減り、運動量も減るなか足腰が弱り、骨折をきっかけに入院し、その後自宅に帰れないまま地域からいなくなったという話だ。なかでも高齢化が進む地域で住民支援を続けてきた世話役の話にはびっくりした。そんな地域もあるのかと。
「うちの集落にはコロナ禍以前300人弱の高齢者が住んでいました。ひとり暮らしの人が多い地域なんですが。でもコロナが始まって以来現在までに、2割ほどの高齢者が地域からいなくなりました。施設に入所されたり、子どもさんが住む地域に転居されたり。そんな人が結構おられて」と。
地域を去った高齢者の多くが以前は地域サロンや、介護予防体操に集まる人だったという。
「地域から消えていなくなる高齢者がいる」。子どもの世話にはならないと言っていた高齢者が現実に倒れた時、どんな事態が生じたのだろう。そんな疑問から、さらに、支援者や地域の世話役の話を聞いていった。
わかってきたのは次のようなことだ。
高齢者が口にする「子どもの世話にならない」暮らしとは、子どもとの同・別居に関わらず、自分が少々弱っても、自宅暮らしが可能な期間限定のものであって、倒れた後、子どもの世話にならないというものではない。
なぜなら、「その時はその時」「なりゆき任せ」として生きてきた人の場合、ひとり暮らしを続けるために必要な介護や医療に関する情報や家族以外の頼れる人間関係も蓄えていないことが多い。だから、自宅に住み続けたいと思っても、どうすればそれが可能となるかがわからない。その結果、どこで誰に世話して貰うかの身の振り方を子どもに「丸投げ」せざるをえない。
そして、背景に親子双方のどんな事情が関わるかもだんだんわかってきた。
先ず、ひとり暮らし高齢者の場合、コロナ禍以前は別居する子どもが頻回に電話したり、月に数回、買い物や様子を見に親元に通う形で親の生活が保たれていた。
しかし、そうした関係を維持することがコロナ禍で難しくなった。
そんななか病気や事故で親が倒れた場合、子どもの方が「以前より弱った親が退院後のひとり暮らしを続けるのは無理。安心できない。私らが心配」と、自分の居住地近くのサ・高・住やケア施設を探し、そこに転居させることを選択する。(親が心配と言いながら、周囲の人に「弱った親をひとり暮らしさせて」と悪口を言われるのが「心配」という人も多いのだが)。
さらに、同居の高齢者の場合は、子世代の在宅ワークや孫世代の休校などでこれまでの生活が激変する。そこに親が病気や事故で倒れた場合、その負担の重さで子世代夫婦間のトラブルも増え、家族の緊張が高まる。その結果、「同居継続は無理」と施設入居という流れになっていく。
しかし、ひとり暮らしであれ、同居の場合であれ、住み慣れた家で最期まで暮らし続けることが出来るのではないか、子どもがそうした自分の思いを汲み、何とかしてくれるのではないかと秘かに親が考えていた場合、それは不本意な選択に他ならない。
だから施設入居後、「こんな所に入りたくなかったのに、子どもに入れられた。あんな子だとは思っていなかった」と、子どもを悪者にし、身の不遇を託ちながら暮らす人も出てくる。
だが、子どもの決定に対し、「それは嫌だ」と自分の本音を言える高齢者は少ない。なぜなら、現代の高齢世代が自分の子育ての頃から重要視してきたのは「親は子どもの幸せを第一に考えねばならない」「親が子どもに迷惑をかけるようなことはあってはならない」という戦後の「子ども中心」「教育中心」の家族観だから。
そうして問題なのは窮地に陥った時の高齢者のこうした「丸投げ」や相手が自分の意向に添わない場合の相手への屈折した攻撃が、支援者との関係でも同様に作られることである。支援者に対し「わたしはよくわからないから、あんたが思うようにやってくれ」。そう言いつつ業務規定外のサポートなど支援者に要求をし、それが受け入れられない場合、「あんたらの給料は私らが払っとる」と居丈高になる。
「この人可愛くないなあ!」。ヘルパーやケアマネがそう思ってしまうのは当然だと言えよう。
投稿者プロフィール

-
九州大学大学院博士課程中途退学。元松山大学人文学部社会学科教授。専門は臨床社会学。父子家庭や不登校問題、高齢者介護の問題などについて永年研究。
現在、「高齢社会をよくする女性の会・広島」代表。
著書として、シングル子介護、夫介護など現代社会が抱える家族介護の危機状況を分析した『変わる家族と介護』(講談社現代新書)。山川菊栄賞受賞『介護とジェンダー』(家族社)。『介護問題の社会学』(岩波書店)。鶴見俊輔・徳永進・浜田晋共著『いま家族とは』(岩波書店)など。近著として『100まで生きる覚悟』(光文社新書)、中国新聞「夕映え、そのあと先」連載。





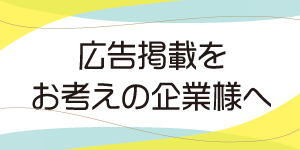


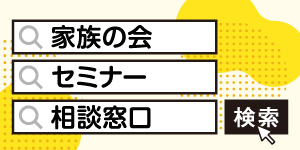





コメント