まだ世の中に知られていない表現や作品を発掘する日本唯一のアウトサイダー・キュレーター櫛野展正(くしの・のぶまさ)によるコラム。新刊「アウトサイド・ジャパン」には、ここに登場した表現者も紹介されており、2019年1月にクシノテラスで展覧会も開催されます。
今回は、足を踏み外した世界を体現している一つ栁恋路さんを取材しました。

68歳の現役美大生
1977年、頭髪から陰毛まで右半分の体毛を剃り落とし、共産圏だったハンガリーへ入国しようとするプロジェクト『ハンガリー国へハンガリ(半刈り)で行く』で、一躍その名を美術界に轟かせた現代美術家・榎忠。それから40年以上経った現在、東京都大田区西蒲田にある6階建てのビルの前で、僕の眼の前には新たな半刈りの男性が立っていた。「一つ栁恋路」と名乗るその男は、現在68歳。東京造形大学に通う大学4年生というから、おそらく最年長の現役美大生だろう。
彼に自らが所有するビルの中を案内してもらったが、居住空間兼アトリエとして使用している4階から6階部分には、画材はもちろん沢山の書物や映画のDVDなどが収集されている。特に僕が興味を持ったのは、お洒落な眼鏡のコレクションだ。すべて表参道の店舗で購入し、高いもので80万の品もあるというから驚いてしまう。
2階は作品倉庫になっており、蝉の抜け殻や手羽先の骨、ちりめんじゃこ、そしてかつて公衆電話に貼られていたピンクチラシなど、特殊な素材を使ってつくられた作品で溢れていた。


特に代表作とも言える蝉の抜け殻や手羽先の骨などで制作された「落ち武者」は、ニューイングランドで白人入植者とインディアン諸部族との間で起きたフィリップ王戦争を題材にしたもので、昆虫や生き物の<亡骸>を使って<死者>をつくった本作は、まさに切断された首が白人たちの村に約20年近く見せしめとして飾られたフィリップ王のように、「メメント・モリ(死を思え)」の言葉とともに否応なく僕の心に突き刺さってくる。
「周りからは『凄い』と言われるけど、自信がないんです。だから外見の奇抜さはカモフラージュですよ。まずは形から芸術家らしくね」
そう語る「一つ栁恋路」こと、一栁孝司(ひとつやなぎ・こうじ)さんは、1950年に埼玉県蕨市で2人兄弟の次男として生まれた。生後すぐに一栁家の養子となり、蒲田へ転居。幼少期にアデノイド(咽頭扁桃肥大症)に悩まされた一栁さんは、鼻づまりで上手く喋れないことが多かったため、「言いたいことがあるなら紙に書きなさい」といつも養母から紙とクレヨンを渡されていた。小さい頃から、常に絵を描く道具が手元にあるという特殊な環境が、一栁さんにとって表現の原点になったのかも知れない。


「ぬるま湯」より居場所を求めて
「小学校低学年のときに手術をしたんですけど、麻酔なんて無かったから、目から火が出ました」と当時を振り返る。術後は、まるで水を得た魚のように饒舌になり、活発さが講じて職員室に呼び出されることも頻繁にあった。高校時代は、夢中になって観ていたテレビドラマ『姿三四郎』に憧れ、入学と同時に柔道部へ入部。オリンピックに行く気満々だったようだが、体格も倍ほどある部員たちを前にして、すぐに力の差を感じてしまった。
高校3年生で進路を決める際に「卒業後は絵でも描こうかな」と両親に相談したところ、養父から「それじゃ食っていけない、法学部へ行け」と反対を受けた。養父はタクシー運転手や会社のお抱え運転手など運転業務に従事してきた人で、自分の学歴が無いことをコンプレックスに感じていたため、せめて息子には良い大学に入ってもらうことを望んでいたようだ。
「結局、一浪して9つの大学を受験したんですが唯一合格したのが青山学院大学法学部だったから、青学にはいまでも仁義を感じるんです。大学に入ったら両親は口を出さなくなったから、ずっと遊んでましたね。最初は講談がやりたくて落語研究会に入って『一栁亭巷た(いちりゅうてい・ちまた)』って良い芸名も貰ったんですけど、青学の落研は落語だけだったから辞めちゃったんです」

退部した大学1年生のときから、学校のチャペル裏にあった美術サークルに入り浸るようになり、そこから一栁さんは芸術にどっぷり浸かる生活を送るようになった。卒業後はオイルショックによる不況と重なり、どこの会社を面接しても相手にしてもらえず、結局、養父の知人が経営する会社へ就職。そこで総務担当として28年間働いた。
「55歳になったら、会社を辞めて絵を描こうと考えてたんです。そうしたら、ちょうど働いていた会社が吸収合併されることになって、親の介護の問題とも重なって、運良く55歳で自主退職することが出来たんです」
一栁さんが52歳のときに、認知症だった養父が85歳で他界し、7年後には養母もこの世を去った。働いているときからカルチャー教室などへ通って絵を描き続けていたが、最終的には四谷美術研究所へ仕事帰りに毎日通うほどだった。
「美術研究所に通ってた頃は、日展に出展するような真面目な絵を描いてたんですが、先生を囲んですぐに展覧会やその受付の店番の話だとか、色が綺麗で構図が良いとお互いに褒め合ったりとか、そんな話ばかりが続く『ぬるま湯』のような環境は嫌だなと思い始めたんです。ここは俺の居場所じゃないなと。どういうところか分かんないけど、やはり美大に行くべきだなと考えるようになって」

美大を志した一栁さんは、美術予備校に1年間通って、4年前に東京造形大学造形学部に入学を果たす。ところが、高校の柔道部で感じたような高い壁に一栁さんは悩まされることになった。
「中学高校のときは好きな子を描きたいとか中世の素晴らしい絵を模写したいとか動機はそんなもんですよ。でも大学に入って周りを見渡してみれば、若い子たちは抜群に絵が上手いでしょ。年の離れた同級生たちは、みんな優しく接してくれるんですが、アトリエの中で若い子たちと比較して絵を描いていくのが辛くなって屋外に出たんです。それで頭に浮かんだことをつくるようになったわけですよ」


足を踏み外した世界
自分の居場所を求めて、外に飛び出したことで、一栁さんの作風は急激に変化した。平和島公園で蝉の抜け殻を採っているときに思いついたのが、あの「落ち武者」だ。作品に使用されている公衆電話のピンクチラシは、80年代から密かに収集していたと言うし、高校のときから好きだった緊縛を大人になってから通うようになった緊縛会で自らモデルになって披露した姿も作品として写真に収めた。


自社ビルの屋上では、全裸になって体中に絵の具を塗りたくり「魚拓」ならぬ「人拓」として表現した作品だってある。作品のモチーフは骸骨が多く、「死」を想起させるが、それとは裏腹に感じてしまうのは、とてつもない生命力だ。一栁さんは、これまでの68年という人生の軌跡のなかで通り過ぎていったこの世のありとあらゆる有象無象を貪欲に表現へ取り込もうとしているように思える。
「もうすぐ卒業だけど、今後は東京芸術大学を目指したいんです。サラリーマン根性が入っているから仕事のあとは飲みたいんだけど、造形大だと駅前に何もないでしょ。でも東京芸大だと目の前は銀座だから毎日飲めるしね」
僕からすれば、芸大というアカデミックな色に染まるよりも自由にこのまま自らの表現を突き進んでほしいと願うばかりだが、きっと養父から受け継いだ学歴コンプレックスが一栁さんにも流れているのだろう。
現在は、ビルの賃料と年金暮らしで生計を立てているという一栁さんだが、高みを目指すその向上心は僕らの背中を後押ししてくれるし、人間には自己主張ができる「居場所」が必要なのだということを再認識してしまう。芸術とは、まともな人生を踏み外すために存在しているのかも知れないが、一栁さんの旺盛な姿を見ていると足を踏み外した世界のほうが絶対に楽しそうだ。



投稿者プロフィール
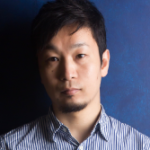
-
文・撮影
櫛野展正(くしの のぶまさ)
1976年生まれ。広島県在住。2000年より知的障害者福祉施設職員として働きながら、広島県福山市鞆の浦にある「鞆の津ミュージアム」 でキュレーターを担当。2016年4月よりアウトサイダー・アート専門ギャラリー「クシノテラス」オープンのため独立。社会の周縁で表現を行う人たちに焦点を当て、全国各地の取材を続けている。
住所:広島県福山市花園町2-5-20
クシノテラス http://kushiterra.com
最新の投稿
 アウトサイドからこんにちは!2020年4月13日#26(最終回) 彼方からの宿題
アウトサイドからこんにちは!2020年4月13日#26(最終回) 彼方からの宿題 アウトサイドからこんにちは!2020年2月10日#25 無限のサークル
アウトサイドからこんにちは!2020年2月10日#25 無限のサークル アウトサイドからこんにちは!2019年12月10日#24 永遠のトラック野郎
アウトサイドからこんにちは!2019年12月10日#24 永遠のトラック野郎 アウトサイドからこんにちは!2019年10月15日#23 「観客」から「演じ手」へ
アウトサイドからこんにちは!2019年10月15日#23 「観客」から「演じ手」へ
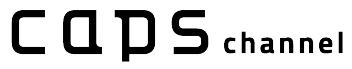

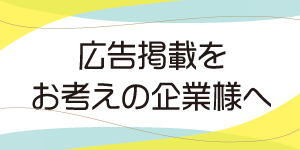


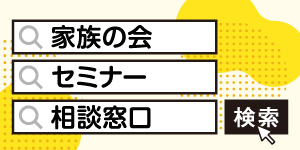





コメント